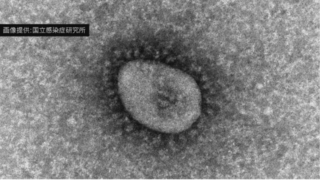米テレビ放送網が一堂に会し、CM枠の先行販売をおこなう毎年恒例のアップフロント交渉で、ここ数年必ず持ち上がる大きな問いがある。視聴率は下がる一方だが、広告主の要求は高いままの現状で、テレビ広告の価格はどれだけ上がりうるのだろうか。この問いはいまだ回答のないままだが、価格に影響を与えるひとつの要因が明らかになってきた。
エーアンドイーネットワークス(A+E Networks)が1年前に示したある前例に、今年はより多くのテレビ局が追随する気配を見せている。同社は昨年のアップフロント交渉で、「18歳から49歳」という広告主にとって都合の良いユーザー層をつまみ食いするのをやめて、全視聴者を対象とした買い付け、いわゆるトータルオーディエンス方式に切り替えるよう広告主に迫ったのだ。そして、ターゲットオーディエンスの年齢を従来型のテレビを視聴する成人全体に広げることを許容せず、年齢別の買い付けにこだわる広告主に対しては、別途割増料金を要求するとした。
「いまのところ、変化率は2桁になるだろうと推測している。これは割増料金を含まない数字だ。年齢などのデモグラフィック条件を維持するなら、2桁の割増がつくのではないか」。あるエージェンシー幹部はそう語っている。
Advertisement
主なキーポイント:
- エージェンシー幹部たちの予測によると、今年のアップフロント市場では、より多くのテレビ局が広告主にターゲットオーディエンスの年齢層拡大を迫る。
- 年齢などのデモグラフィック属性を指定した買い付けに関しては、追加料金が検討されている。
- トータルオーディエンス方式への移行は、買い手と売り手の双方に、より大きな柔軟性と効率性をもたらしうる。
ターゲットは全視聴者
アップフロント交渉において、トータルオーディエンス方式はまったく新しい提案というわけではない。実際、A+Eは昨年の予備交渉でもこの方式を導入している。複数のエージェンシー幹部によると、今年はディズニー(Disney)、NBCユニバーサル(NBCUniversal)、パラマウント(Paramount)を含む大手ブロードキャストネットワークが後に続き、売り手側の提案として、トータルオーディエンスはもはや当然の選択肢とさえいえるようだ。
広告の売り手がトータルオーディエンスを推す理論的背景は明快だ。リニア(従来型)テレビの視聴者の高齢化は今後も続く。売り手としては、視聴者が55歳を超えたからといって、彼らを収益化の対象から外すのは本意でない。若い視聴者の人数が広告主に約束したオーディエンス保証に満たないからといって、損金を出すのもできれば避けたい。一方で、トータルオーディエンスの推進は、同時に進行するほかのふたつの事象とも関連している。ストリーミングサービスの台頭と、テレビ広告の効果測定システムの見直しだ。
ストリーミングに関しては、リニアテレビのオーディエンス保証の未達分を、その年齢や性別にかかわらず、ストリーミング在庫で補填できるため、買い付け対象の属性条件を広げることは、テレビ局に有利に働く。事実上、18歳以上だろうが、それどころか「P2+」と呼ばれる2歳以上だろうが、リニアテレビで可能な限り多くの視聴者を提供して、それでも不足が生じれば、その年齢に関わりなくストリーミングで埋め合わせることができるようになる。
テレビ局にもたらされた恩恵
フューズ(Fuse)もアップフロント交渉でトータルオーディエンスを採用したメディア企業のひとつだが、同社で広告販売の責任者を務めるフェルナンド・ロメロ氏は次のように述べている。「広告主にしろ、エージェンシーにしろ、あるいはメディア企業にしろ、オーディエンス横断的な流動性のようなものを求めているのなら、あるいはリニアとノンリニアのインプレッションを集約しようとしているなら、もしくはより大規模な買い付けを検討しているなら、そこには一定の一貫性がなければならない。いずれにせよ、2歳以上であれ、18歳以上であれ、世帯単位であれ、リニアとノンリニアをひとまとめにしたインプレッションのほうが、おそらく管理は容易だろう」。
従来的なテレビ広告の買い付けで、トータルオーディエンス方式の採用が進めば、新しい効果測定システムへの移行も管理しやすくなるかもしれない。ブランド広告主にとって、リーチとフリクエンシーが重要な要素であることに変わりはないが、テレビ広告の買い手と売り手は、成果ベースの効果測定がより標準的な選択肢となることをずっと望んできた。特定の年齢層へのこだわりは、このシフトを遅らせることになりかねない。
「年齢などの縛(しば)り、さらにはリニアとデジタルの線引きをすべて取り払えば、成果ベースの議論を本格化できる。クライアントが『どこでもいいから売上につながる場所に広告を出したい』と要望するような議論だ。広告主が求めるオーディエンスに近いものを人為的に設定して保証するというような、抽象的な概念を論じるよりもよほどマシな議論ができる」。あるテレビ局の役員はそう語った。
こうしてみると、トータルオーディエンス方式への移行がテレビ局に恩恵をもたらすことはほぼ明白だ。一方で、売り手側に限らず、一部のエージェンシー幹部もこのアプローチにメリットを見いだしている。バイヤーの立場に立てば、年齢層などの指定によって発生する割増料金を回避できるうえ、より柔軟な買い付けが可能になる。さらに、大規模な同時視聴者にリーチする機会を提案するアップフロント交渉では、他社に後れを取ることを恐れるあまり、過度な買い付けに走る広告主も少なくない。この「機会を逃すことの不安」を緩和する効果も期待できるだろう。
「エージェンシーやクライアントのあいだでは、過大な見積もりが多発している。実際、クライアントは、一応アップフロントでコミットはするが、不要なら注文を減らすなりキャンセルするなりすればいい、と考えているようだ。昨年はそういうケースがかなり発生した」。別のエージェンシー幹部はそう語った。
売り手側にはマイナスポイントも
もちろん、売り手側から見れば、テレビ局が提案するトータルオーディエンス方式の受け入れにはマイナス面もある。最大の懸念材料は、テレビ局側によって、交渉の新たなベースラインが設定され、そこから広告価格が長期的に引き上げられる可能性だ。しかしその反面、クロスプラットフォームのベースラインが設定されれば、広告バイヤーたちが求めてきた「従来的なテレビ広告の在庫と、より高額なストリーミング在庫の格差縮小」にも道が開かれよう。
買い付け対象のオーディエンスの幅を広げれば、アップフロント交渉で広告予算をもっと効率的に使えるというのは理屈に合わない。そう言いたい気持ちは分かる。しかし、最初にコメントしたエージェンシー幹部は、このことについてかなり説得力のある主張を展開している。いわく、従来のテレビでは、広告主は歴史的に18歳から49歳の年齢層を指定して広告枠を買い付けてきたが、彼らの広告は、視聴者の年齢に関係なく、特定の番組を視聴しているすべての人々に向けて放送される。一方、ストリーミングに関しては、18歳から49歳の視聴者のみに広告が配信される。「すでにその時点で、ストリーミングの配信はテレビに比べて効率が悪い」とこの幹部は述べている。
結局のところ、買い手と売り手の双方にとって、テレビとストリーミングの広告売買の効率を上げるには、ある側面ではその売買の効率を下げる必要があるということだ。もうじき、2022年のテレビ広告市場の幕が開く。
Tim Peterson(翻訳:英じゅんこ、編集:長田真)