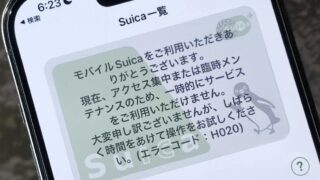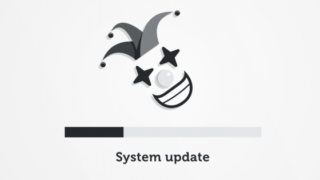「日本の外食は安すぎる」という話題がネット上でたびたび盛り上がる。
例えば、回転寿司チェーン店。
業界最大手の「スシロー」は1996年に「1皿100円均一価格」の1号店を出店、2番手の「くら寿司」は1984年に「100円で本物」をコンセプトに創業した。一部商品の値上げを除き、両社の「1皿税抜き100円」という“ベース価格”は今も変わらない。
安さを維持しつつ、売り上げも好調だ。コロナ禍の逆風をものともせず、スシローは2021年11月、くら寿司は同年12月の決算発表で過去最高の売り上げ高を記録したことを明かした。
一見、「企業は儲かり、消費者は安く美味しいご飯を食べられる」と良いことばかり。しかし、アメリカ在住の日本人ジャーナリストや国会議員に話を聞くと、その背景にある”日本経済の不健全さ”を指摘する声が上がる。
「お寿司の価格が安い」状態が続く裏で日本経済はどんな問題を抱えているのだろうか。
1皿100円が変わらない日本は不健全?

Getty Images
「日本は異常です」
そう口にするのは流通コンサルタントの後藤文俊氏だ。35年以上暮らすアメリカではレストランの価格は経済状況を踏まえて、当たり前のように上がる。「日本でモノの値段が30年以上も変わらないのは、経済循環がうまくいっていないことの表れ」と指摘する。
日本では低価格を維持するくら寿司もアメリカに展開する35店舗では価格改定を繰り返している。
「1皿100円」に当たるアメリカ・ワシントン店の現在のベース価格は3ドル15セントと設定されている。これはアメリカ初出店の2009年、1皿2ドルから比べると5割以上高くなっている。
同社によると「最低賃金の上昇などを反映」して価格改定は行われている。広報担当者は「値上げによる売り上げへのマイナス影響はなかった」と語る。
後藤氏は「アメリカでは右肩上がりで物価上昇が続いていますが、同時に賃金も上昇しているためハレーションは起きていません。この状況を市民は健全な経済の循環だと捉えているのです」と解説する。
給料が安い国・ニッポンという姿
これに対し、日本では回転寿司業界に限らず多くの業界で価格設定の低い状態が近年、維持されてきた。
物価の変化を表す「消費者物価指数」を見てみると、低い価格設定が変わらないのは回転寿司業界に限ったことではなく、日本経済全体の傾向と言える。日本の消費者物価指数は2020年を100とする指標で1991年の95.332から2021年12月は100.1と、30年間で約5%の伸びに留まる。一方、同期間のアメリカでは、1982年から1984年を100とする指標で、144.475から278.802と伸び率が90%を超えている。その差は歴然だ。
日本の平均賃金は現在、年38,515ドル(2020年,OECD発表)であり、この数字は20年前と比較しても150ドルほどしか増えていない。この間、OECDの全体平均は42,160ドルから49,165ドルと約7,000ドル、アメリカに至っては55,366ドルから69,392ドルと約14,000ドル上昇している。

つまり、日本は店で寿司を1皿100円で注文できる一方、海外と比べて「給料が安い国」になってしまっているのだ。
政治が目指すのは物価が上がらない“デフレ”からの脱却
こういった状況を政治の場はどう捉えているのだろうか。
2001年、政府は年次経済報告(経済白書)で戦後初めて経済状況を「緩やかなデフレ」と表現した。
ここでいうデフレとは物価が下がり続ける状態を指す。同報告では、「(当時の)日本経済の置かれた状況にあっては、程度が緩やかであっても、デフレは経済に悪い影響を与えていると考えられる」とされ、「早期の脱却が必要」とされている。
2013年12月以降は、月例、年次経済報告において経済状況を「デフレ」とする表現は見られなくなったが、「デフレから脱却」は未だに宣言されていない。
現状を打開するためにどのような政策が必要とされるのか。BLOGOSでは8政党に「物価目標とその実現のための政策」について、アンケート形式の聞き取りを行った。
自民党は「デフレからの脱却に向けて」政策を打ち、「2%の物価安定目標を実現することを期待して」いると回答。野党第一党の立憲民主党は、物価が上昇していることは認めるものの「賃金の増加が追いついていない(=実質賃金が低下している)」と指摘し、現状について「家計が苦しい状況に置かれている」と評価する。

BLOGOS編集部
表現はそれぞれながら8政党のうち与野党合わせて6政党が物価・賃金上昇を目標に据え、残る社民党は「物価のみで(目標を)論ずることはできない」としつつ「消費経済が活性化した結果としての物価上昇が理想」とし、共産党は「物価目標を設定する立場をとるべきでない」という回答だった。
デフレ脱却を目指した「アベノミクス」
直近の政策を振り返ると、安倍晋三元首相による「アベノミクス」(2013〜20年)がデフレ対策の筆頭に挙げられるだろう。
①大胆な金融政策
②機動的な財政政策
③民間投資を喚起する成長戦略
の“3本の矢”によって、デフレからの脱却と富の拡大を目指した。
ある程度の物価上昇など一定の成果はあったとされるが、20年、コロナ禍の影響もあり消費者物価指数が生鮮食品を除き4年ぶりのマイナスとなった。その状況下で、同年9月に就任した菅義偉首相(当時)は「アベノミクスの継承」を掲げ、同路線での物価上昇に意欲を見せた。
アベノミクスを立民議員と振り返る
このアベノミクス、効果はどのようなものだったのか。
立憲民主党の「アベノミクス検証委員会」中心メンバーとして、近年の日本経済の動向を分析してきた落合貴之議員は「第一の矢は効果があったが、物価の上昇に賃金上昇が追いつかなかった」と評する。
落合議員が問題視するのは「賃金の上昇率の低さ」だ。
2012年〜19年の7年間で物価は7%上昇、給料の額(名目賃金)は2%程度上がっている。

「しかし、物価の変化を考える際には単純な給与額ではなく“実質賃金”を見なくてはなりません」
実質賃金は額面ではなく、そのお金で何を買うことができるかという“価値”を示すものだ。そのため、落合議員は物価の上昇(7%)に賃金の上昇(2%)が追いついていない現状では「『賃金が下がった』と見ることができる」と指摘する。
「実質賃金が下がればモノやサービスを買う動きも低下し、景気は上向きません。さらに言えば、物価7%の上昇はアベノミクスの効果だけではなく、この間の消費税5%増税分が含まれます」
加えて落合議員は「実質賃金の低下によって、すべての世代で貯蓄する余裕がなくなった」と話す。

立民議員は「バブル崩壊後から変わっていない日本」を問題視
アベノミクスを始め、政府は物価や賃金を上げる政策に力を入れてきたはずだが、なぜ思うように上がっていないのか。
落合議員はその理由を「経済の仕組みがバブル崩壊直後から変化していないことにある」と語る。
1990年代前半、バブルが崩壊し多額の不良債権を抱えた銀行は企業への融資を控えるようになった。その影響で企業は株式や証券などの金融商品で資金を得る直接金融、つまり株主に依存する傾向を強めていった。
この“株主依存”の経済の大きな特徴のひとつが「企業が目先の利益を優先するようになりがちになる」ことだ。融資を受けているのが銀行であれば1年に1回だった決算報告が、証券取引法(現「金融商品取引法」)の下では3ヶ月に1回求められるようになっていった。
短いペースで利益を提示することが求められるようになった企業は人件費や会社の将来への投資もにかけるお金を削る。短いスパンで利益を株主に提示する構造が生まれ、時代が変わった現在もその形は変わらずに続いているという。
落合議員は「企業が短期的な利益を優先するあまり、持続可能な成長ができず、健全な循環が生まれない経済となってしまった」と語る。
現在、日銀も潤沢に資金を供給し、銀行融資をめぐる状況も改善している。しかしバブル崩壊後に慌てて作った資金調達の仕組みが、未だに続いてしまっていることが問題だというのだ。
「短期的な利益を重視する時期があること自体は構わない」としつつ、「それを25年も続けてきてしまったことが問題です」
企業の利益が株主への還元だけでなく、その企業の成長力の強化や個人の収入にもつながるような「経済循環」が必要だと落合議員は訴える。
岸田首相と立民が“被っている”?「デフレ脱却」政策】
アベノミクス、ひいてはこれまでの自民党政権の経済政策からの脱却を訴えるのは野党だけではない。落合議員は「実は今、立憲民主党と岸田首相の唱える政策の内容がかなり被っているところもある」と指摘する。
岸田首相も昨年9月の総裁選期間中から、アベノミクスの成果を評価しつつも「好循環を生み出せなかった」とその課題を訴えてきた。
20年10月の所信表明演説では「新しい資本主義」を実現する“車の両輪”のひとつは分配戦略だとし、「企業が長期的な視点に立って、株主だけではなく、従業員も、取引先も恩恵が受けられる三方よしの経営を行うことが重要」だと述べて、株主偏重や企業同士の取引関係の不均衡の是正を訴えた。具体的な策として、落合議員の政策と同様に「四半期決算開示の見直し」や「下請け取引に対する監督体制を強化」「大企業と中小企業の共存共栄」を掲げている。「しっかり実行できるのか見ていきたい」と語った。
さらに前出の政党アンケートでは、表現はそれぞれながら8政党のうち与野党問わず合わせて少なくとも6政党が物価、賃金上昇の目標で方向性が一致している。とりわけ政府と野党第一党が同じ方向を向く今は、足並みを揃えた政策を進めるチャンスだ。
世界の経済状況に合わせて物価を上昇させつつも、消費者が昇給した賃金からそれを支払って豊かな生活を送ることができるような、循環する経済を作り出すことができるか。外食費のような身近な数字にそれが“健全に”反映されるようになったとき、有権者は身近なところにある政治を実感できるのかもしれない。