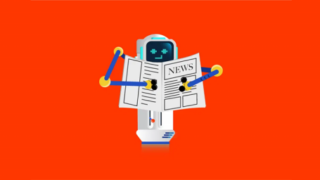アリーナを埋め尽くす観客に、10万ドル(約1300万円)を超える月給。対戦型ゲームの草創期から現在まで、eスポーツは長い道のりを歩んできた。
ビデオゲームトーナメントが初めて開催されたのは1972年、スタンフォード大学の人工知能研究所(Artificial Intelligence Laboratory)が主催した「スペースウォー!(Spacewar!)」の大会だったが、ゲームディベロッパーが製品そのものだけでなくマーケティングチャネルとしての対戦型ゲームの潜在的価値を認識するまでには、はるかに長い時間を要した。
ゲーマーたちは何十年ものあいだ、ディベロッパーからの使用停止通告書を巧みに回避し、賞金のためではなくゲームへの情熱からプレイを続けながら、日の当たらない場所でおとなしくしていた。「eスポーツ」という言葉は、2000年に韓国の文化体育観光部長官であった朴智元氏が「electronic」と「sports」を組み合わせて作りだした造語で、それ以前は存在しなかった。
Advertisement
時が流れて現在では、ゲーム関連の消費者にリーチしようと、広告主たちは何百万ドルもの資金をeスポーツ業界に投入している。eスポーツのファンたちがカジュアルゲームをめぐる活動の原動力であることを理解したゲームデベロッパーは、オーバーウォッチ・リーグ(Overwatch League)やリーグ・オブ・レジェンド・チャンピオンシップ・シリーズ(League of Legends Championship Series)、といった体系的な競技リーグを何年もかけて開発してきた。概してこの発展拡大の潮流が多くのeスポーツ企業を後押ししてきたわけだが、とはいえこのようなeスポーツの広がりがそれなりの成長の痛みを伴わなかったわけではない。
本記事では、eスポーツの草の根時代から今日の企業環境までの進化を、eスポーツ業界に詳しい関係者や専門家の言葉で紹介する。
01 初期
ゲームディベロッパーやノンエンデミックのブランド(ゲーム関連でない一般のブランド)がeスポーツ業界へ参入し始めるまで、競技ゲームのパイオニアたちの多くは隅に追いやられたまま、ただ自身の情熱とボランティアの力に頼るかたちでトーナメントを運営していた。
メディア会社ヴィンデックス(Vindex)のCEOで、メジャーリーグゲーミング(Major League Gaming)の共同創設者でもあるマイク・セプソ氏:
初めて自社オフィスでお会いする方の中に時々、「あなたのお名前は存じ上げている、停止通告書に書かれていたので」などという人がいる。つまり、認識の違いというのはそういうことだと思う。eスポーツが始まった当初は、エレクトロニックスポーツリーグ(ESL)にせよメジャーリーグゲーミング(MLG)にせよ、自分たちがやりたいことを制度化し、商業化したいと考える人間の集まりみたいなもので、誰ひとりとしてビデオゲーム業界で仕事をした経験のある者はいなかった。だから、こちらが期待する物事の進み方と、スタジオや出版社側が考えるやり方とは全く異なっていた。覚えておいてほしいのだが、ESLとMLGの初期のイベントでは観戦パスすらなかったんだ。だって、それは自分たちが参加するトーナメントでしかなくて、誰も見に来なかったから。
ヒロイックジャーニー(Heroic Journey)のトークノミクス・デザイナーであり、かつてカウンターロジックゲーミング(Counter Logic Gaming)で「リーグ・オブ・レジェンド(League of legends)」のゼネラルマネージャーを務めたほか、「大乱闘スマッシュブラザーズDX」ではトップ100にランクインするプレーヤーだったダニエル・リー氏:
文化という点でいえば、あれはただゲームへの愛だった。たいして大きな賭けというわけでもない、ああいう世界に早くから入り込むメリットのひとつは、いろんな部分で自分の好きなようにできるということだ。メジャー大会に行くと、ホテルの部屋にいたのは、そうだな……16人ぐらい。CRT(ブラウン管テレビ)の前にぎゅうぎゅう詰めに座ってプレーヤーのプレイを見た。今ではプロジェクターがあるけどね。私たちはみんな自前でやっていた。企業の興味を引くことなんて、それほどなかったからね。
eスポーツを扱うジャーナリスト兼コンサルタントの草分け的存在であるロッド・ブレスロー氏:
すべて自給自足。みんなそうやって運営していたよ。有償の単発仕事も一部あったが、みんな心底ゲーム――当時は「クエイク(Quake)」というゲームだった――への愛からやっていたね。やがて北米でウェブサイト「ゴットフラッグ(GotFrag)」が開設された。「カウンターストライク(Counter-Strike)」のメインハブだったが、その後他のゲームもカバーするようになった。欧米で、eスポーツを扱うジャーナリズムで報酬を得ることができたのは、これが初めてだった。
ゲーム・eスポーツ企業ドゥーノットピーク・エンターテインメント(Do Not Peek Entertainment)のマネージングディレクター、ジェイソン・ベイカー氏:
初期のころは、仲間たちと車に自分のPC機器を満載してでかけていき、イベント会場でLANでつないでプレイするというのが主流だった。LAN上に、各自の持ち込みPCが接続されたセクションがあるような感じで、そこで「おーい、ウルフェンシュタイン(Return to Castle Wolfenstein)のトーナメントをやるぞ!」とかいうんだ。サインアップは掲示板か何かに書いてあって、それをみてプレイに参加する。ゲームをするのにその場所まで足を運ぶのではなくて、自分のPC上で「じゃあ、自分はこれをプレイしよう」って決めるだけ。
02 eスポーツ人口の拡大
初期のeスポーツ界では明らかに白人と男性が目立っていた。もっとも、「カウンターストライク」のトッププレーヤーで、後にeスポーツ関連企業のエグゼクティブとなったヘザー・ガロッツォ氏のように、女性もそれなりの数はいた。だが今日では、eスポーツ界に属する人々が画一的であるという誤解がもはや真実ではないことは明らかだ。現在のeスポーツ界には女性も有色人種のプレーヤーも数多くおり、ブランド各社はこれに対応して、ゲームのオーディエンスにリーチするためのマーケティング費用を増やしている。
写真提供:ジェイソン・ベイカー氏
eスポーツチーム、ディグニタス(Dignitas)のコミュニティ及びイベント担当バイスプレジデント、ヘザー・ゴロッツォ氏:
「女性は男性ほど上手くない」とか「女性はトップリーグで戦えない」などと発言する人がたくさんいるという事実に、いつも胸を痛めている。私はトップリーグにいたけれど、ソーシャルメディアやストリーミングがそれほど普及していなかったので、誰もそのことを覚えていない。もちろん今は女性プレーヤーの数が増えたし、それは間違いない。ゲーマーになるということが、以前よりも文化的に受け入れられるようになった。先日10歳の姪と話をしたが、彼女の友達はみんなFPSゲームの「ヴァロラント(Valorant)」をやっているそうだ。それに、スポットライトの当たる女性が増えたことで、さらに自信を深めることができる。長年、いろいろなイベントにオブザーバーとして参加してきたが、若い女性が私のところにやってきて、泣き出したり抱きついてきたりすると、ほんとうに、どう反応すればよいのかわからなかった。
セプソ氏:
現在は間違いなく、男女平等が進んでいる。初期のころ、「カウンターストライク」とか「ヘイロー(Halo)」の時代は、女性はあまり多くなかった。今は業界全体として、ゲームというものは性別にとらわれないアクティビティだとされているので、ファン層もいちだんと平等になってきていると思う。
ベイカー氏:
かつて大多数を占めていたのは常に白人のティーン層、多くは16歳から20代前半ぐらいの人たちで、今でもそうだと思う。でもテキサスではたくさんのイベントがあって、南カリフォルニアからも多くの人たちが来ていた。ラテン系の人も多かったし、女性もたくさんいたよ。ボランティアとして参加している人、コミュニティの運営を手伝っている人、単にチームに所属するプレーヤーとして来ている人もいた。これまでもこの業界には常に女性が存在していたんだから、ここに女性の居場所はない、みたいな態度の人がいると、私はとても違和感を覚えるね。
03 競技からの転換
eスポーツのオーディエンスが拡大するにつれて、eスポーツ組織は競技に特化した筋金入りのゲーマー集団から、競技ゲーマー、コンテンツクリエイター、インフルエンサーによる混成集団へと姿を変えていった。eスポーツ業界に数年以上身を置いている人にとって、「eスポーツ」という言葉は特にハイレベルなプロによる競技大会、多くの場合メジャーなフランチャイズリーグのひとつを指すが、ほとんどのノンエンデミックブランドのマーケターにとっては、幅広くゲーミングコミュニティへの入り口になりそうなものをひっくるめた用語だ。今では、競技への参加がゲーミング関連のインフルエンサーになる最も簡単な方法というわけではない。
ガロッツォ氏:
それは必ずしも悪いことではない。100シーブズ(100 Thieves)のように最も成功している組織をみると、ある意味ライフスタイル・ブランドになっていて、彼らの競技プレーヤーたちは単に時間がないという理由からコンテンツに関わることはほとんどない。プロのプレーヤーになってトップを走り続けるのは、極めて過酷なことだ。だからクリエイターたちがいるおかげで、少しばかりフレキシブルな対応ができる。
セプソ氏:
ゲーミング業界におけるクリエイターエコノミーは、明らかにeスポーツから発展したものだ。大物クリエイターの最初の世代はオプティック(OpTic)のヘクター(Hector)や、ネードショット(Nadeshot)、ニンジャ(Ninja)などだが、彼らはみなeスポーツの競技大会に出ていた人たちだ。競技者としてはトップレベルではなかったかもしれないが、ゲーム関連のYouTube動画制作などに素早く移行して、eスポーツ業界での活動を開始した。今では大きなeスポーツチームのほとんどが有力な大物クリエイターを組織の一員として加えている。
リー氏:
最近はトッププレーヤーとして知っておくべき責任が格段に大きくなり、必要とされる技術スキルの量も大幅に増えた。そのためにかける時間や、周りについていくための労力も、非常に多くなっている。競技というのは、相対的なスキルなんだよね? つまり同業者のスキルレベルとの比較の中でおおよその評価がなされる。だけど、プレーヤーの数があまりにも多いから、他の人の上を行くためにはより多くの時間が必要になる。
eスポーツ組織、コンプレキシティ・ゲーミング(Complexity)のCEO、ジェイソン・レイク氏:
競技大会はコンプレキシティにとっての北極星、すなわち常に見定めておくべき目標と捉えているが、しかしeスポーツ業界においては多様化がますます重要性を増している。何もせずに埃まみれのつまらないブランドになってしまうよりも、どうすれば既成概念の枠を超えられるかをいつも模索している。20周年を迎えるにあたって、ティム・ザ・タットマン(TimTheTatman)やクロージー(Cloakzy)といったクリエイターたちとともに、コンプレキシティとしてのさらなる業績の拡大を目指しているところだ。
04 ダークマネーの動き
業界の成長に伴って、eスポーツ企業各社は資金調達のためにより幅広い手段を講じ始めた。そしてeスポーツのファンと投資家の双方からの、いちだんと厳しい視線にさらされている。ファンの中には、eスポーツ企業が暗号資産企業やサウジアラビア政府などの政体からの投資やスポンサーシップを受けることに批判的な人々もいる。
写真提供:ジェイソン・ベイカー氏
ガロッツォ氏:
昔は、仲間の誰かの両親がお金持ちでその人に資金を出してもらうか、個人でスポンサーを見つけてきてそれが直接プレーヤーの手に渡るかのどちらかだった。もちろん、現在では多くがVC(ベンチャーキャピタル)として出資を受けているので、スポンサーから提供されたお金が直接プレーヤーの懐に入るといったものではない。でもeスポーツに賭けてくれるお金持ちがたくさんいることは知っているし、それはエキサイティングなことだと思う。怖さもあるかもしれないが、より多くのお金が集まることは概して良いことだ。
ウェブサイト「eスポーツインサイダー(Esports Insider)」のジャーナリスト、ジョーダン・フラーゲン氏:
ダークマネーがeスポーツに新しく入ってきたというのは、ちょっと間違った前提だ。これまでも常に、eスポーツにはかなり怪しげな人々が関わってきた。モスクワ5(Moscow 5)はその最たるものだと思う。彼らはクレジットカードの窃盗の罪でFBIに逮捕されたが、あれはまさにマネーロンダリングの企てだった。だが私が思うに、変化しているのはその規模と金額だ。ちょうど今、サウジアラビアがファイスイット(FACEIT)、ESL、ドリームハック(DreamHack)を所有することで、いわばeスポーツを独占したような状態になっている。メジャーなトーナメント大会の主催者がすべてサウジアラビアの公的投資基金(PIF)に所有されているとなると、業界の空気が違ってくる。
ベイカー氏:
ESLとブラスト(Blast)は、どれも非常に疑わしいお金を受け取っている。2007年から2008年にかけての「カウンターストライク」のイベントでは明らかに問題のあるお金がたくさん使われていたし、もっと初期の「カウンターストライク」でさえも実に興味をそそる怪しいお金がたくさんあった。つまり、そういう意味では今も昔も変わっていないんだと思う。ずっと、そうだったんだと。対戦ゲーム競技をしたいという欲望はあっても、コストを回収するのは必ずしも容易ではない。だからそのリスクをいとわずに引き受けてくれる人が必要なんだ。そしてその中には、怪しい、とまではいわないが、疑わしい企業の資金というのもある――もちろん一部なんだけれども。
[原文:How esports grew up: An oral history]
Alexander Lee(翻訳:SI Japan、編集:分島翔平)
Top Image courtesy of ANDREW ARATO