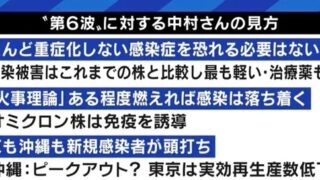アメリカでは、すでに従来型のテレビ放送よりも多くの世帯にリーチしているCTV/OTT。日本においてはまだ市場は成長途上にあるものの、OTT市場規模は約8000億円に達しており、2024年には1兆円を超えるとする予想も存在する。
それとともにCTV/OTT広告への期待とニーズも高まっており、先行して投資を行うブランドも現れている。そんなブランドのひとつ、P&Gジャパン合同会社でメディアディレクターを務める小澤佳史氏も「地上波にない可能性やメリットを感じ投資を強化している一方で、地上波をCTV、OTTで代替するほどの存在感を持つために解決すべき点は、いくつか存在すると感じている」とし、CTV/OTTに関して「リーチ」「効果計測」「プライシング」の3つの最重要項目を挙げる。
市場がさらなるステージへと成長するためには、超えるべきラインがあるものだ。そして、CTV/OTT広告の関係者全体が、小澤氏が指摘する3点こそがそのラインだと認識している。2022年5月27日にDIGIDAYとザ・トレードデスク(The Trade Desk、TTD)が共催したイベント、「DIGIDAY FORUM LIVE:CTV & OTT Ads Forum」においても、ブランド広告主である小澤氏、エージェンシーであるTBWA\HAKUHODO Hearts & Science Japanの井上喬裕氏、CTV/OTT事業者であるTVerの中川卓也氏、DSPのTTDから佐藤大希氏らの4氏が登壇し、CTV&OTT広告の可能性について、活発な議論が交わされた。
議論を経て、小澤氏は「4者とも向いている方向、見据えている未来は同じ」だと語る。では、彼らが見出したCTV/OTT広告の未来とはどのようなものなのか。本記事ではセッションの進行を追いながら、議論の内容をお伝えする。
拡大を続けるCTV/OTT広告市場
eMarketer(eマーケター)の調査によると、アメリカでは2019年時点でCTV/OTTでの視聴者数が238万2000人、日本の地上波にあたるリニアTVの視聴者数が271万6000人だったのに対し、2021年にはそれぞれ253万4000人、245万7000人となり逆転。2023年にはCTV/OTT視聴者が262万2000人、リニアTV視聴者は236万3000人となり、両者の差が拡大すると予想されている。視聴時間ベースで比較すると、その差はさらに顕著で、リニアTVの視聴時間はCTV/OTTの半分近くにまで落ち込んでいる。こうした状況を踏まえ、TTDの佐藤氏も「アメリカのメディアトレンドは日本より5年進んでいると言われることを考えると、日本においてもCTV/OTT市場の成長率は非常に高いものになるだろう」と期待感を見せる。

佐藤 大希/キーエンスを経て、デジタルマーケティングエージェンシーのアイレップに入社し博報堂常駐、その後IPO統括業務を行う。現職The Trade Desk Japan株式会社ではLead Associate Account Directorとして国内の案件を複数統括。
実際、2024年には日本のOTT市場は1兆円を突破し、CTV広告市場は2023年に1000億円を超え、2025年には1695億円にものぼるという調査結果もある。さらには、サブスクリプションモデルが主流となっていたCTV/OTT事業者が、今後一気に広告モデルも取り入れたハイブリッド型に移行していく可能性もあるのではないかとTTDの佐藤氏は指摘する。
「Netflixは、かつてCEOが『(Netflixには)広告が出ることはない』と言っていたにもかかわらず、広告プラン導入の検討を発表した。huluはすでに広告を導入しているし、ディズニープラスも広告モデル導入予定と報じられている。このようなグローバルのトレンドを踏まえると、日本のCTV/OTT広告市場も、加速度的な成長が予想される」。
先行するブランドの投資理由
CTV/OTTのプレイヤーが少ない日本にあってリーディングカンパニーとなっているのが、民放各局の共同出資のもと地上波コンテンツのリアルタイム・見逃し配信サービスを提供しているTVerだ。同社は2015年のサービス開始以来、右肩上がりの成長を続けており、2022年3月には月間再生回数が2億5000万回を超えた。中川氏は「CTV経由の視聴が全再生回数の30%近くになっており、この増加が成長の原動力となっているのでは」と話す。「録画の替わりから、地上波コンテンツを見るのはTVerだけというケースまで、視聴動機も幅広い。この多様性こそが利用者拡大につながっていると感じている」。

中川 卓也/調査会社・インターネット広告会社を経て2015年に株式会社テレビ朝日に中途入社。入社後よりインターネット配信ビジネスに携わる。2020年7月より株式会社TVerに出向。
TVerの成長について、TBWA\HAKUHODO Hearts & Science Japanの井上氏は「(広告主には)テレビCMのクリエイティブを使って、若年層にリーチしたいというニーズがある。また、TVerはどのような商材においてもおしなべてブランドリフトや購買など深い態度変容に寄与するという実績もあり、その認知も広がっている」と述べ、小澤氏もそれを裏付けるように「数年前からCTV/OTT市場には注目してきたが、今後の成長はもちろん、若年層へのリーチという点で大いに期待している」と語った。
地上波の視聴率が低下傾向にあることも、広告主のあいだでCTV/OTTへの注目度が高まっている要因として無視できない。広告主としては視聴率の低下によるリーチの減少をどこかで補完しなくてはならないからだ。とはいえ動画が流れていればどこでもよいというわけではなく、テレビ並みのプレミアムなメディアが求められる。この点でも、TVerであれば配信コンテンツは地上波と同様の品質が担保されており、信頼性も高い。さらに、利用者の能動的な視聴態度などを考慮すると、テレビの補完になり得るプレミアムメディアだと広告主が考えるのは当然だろう。
また、テレビにはないデジタルならではのメリットもある。佐藤氏が指摘するのが「ターゲティング」と「フリークエンシーコントロール」だ。「CTV/OTTはテレビの延長線上にあるメディアではあるが、TTDのような統合プラットフォームを介して広告を配信することでターゲティングも可能になる。実際にターゲティングとフリークエンシーコントロールの有無で、CPAに約5倍の差が出たこともある」。
このように地上波に替わるメディアとして期待感の高いCTV/OTTだが、小澤氏は「急成長している市場だからこそ、そのポジションを確固たるものとするためにあえて高いハードルを提示したい点がある」と明かす。それが、「リーチ」「効果計測」「プライシング」の3点だ。

小澤 佳史/P&Gジャパン合同会社マーケティング部署にて、P&G各ブランドのメディア戦略サポートに従事。
さらなるリーチの拡張を
小澤氏は現状のCTV/OTTにおけるリーチについて、「実際にすでに投資は行っている規模感ながらも、まだまだ伸長する余地があるはずだ」だと指摘する。その理由は、先にも述べたようにCTV/OTTが地上波を見なくなった視聴者の受け皿として期待されている側面があるからだ。しかし、地上波の持つ影響力を一部でもCTV/OTTで代替するためには、膨大なリーチが必要となる。小澤氏の発言はこのような認識に基づいたものだ。
これに対し井上氏は、この指摘は非常に重要だとしつつ次のように述べた。「TVerを例に取れば、成長途上という点を加味しても、エージェンシーの目線ではそこまでリーチが不足しているとは感じていない。ただ、より高い数値目標を掲げている広告主にとっては、『さらなる成長を期待している』というのも理解できる。個人的な感想だが、最近のTVerの状況を踏まえれば近い将来、そのような広告主にとっても十分なリーチを確保できるのではないかと思う」。

井上 喬裕氏/TBWA\HAKUHODO Hearts & Science Japan。メディアプランニングとバイイング、EC運用、マーケティングサイエンスが専門領域。
こうした指摘について、TVerはどのように考えるのか。中川氏は「現在、15歳~69歳で66,6%というTVerの認知率の向上、利用方法の拡充、コンテンツホルダーである放送局との連携によるコンテンツのさらなる充実などによって、リーチを拡大していきたいと考えている」。
確立された効果計測はあるか
次に小澤氏が挙げた効果計測について、同氏は「CTV単体の場合、あるいはCTVを含んだメディア横断で広告投資をした場合、CTVの効果計測の方法が確立されていない」と指摘する。「従来からのMMM、MTAなどの統計的手法やBLSのような調査、さらに最近ニールセンがローンチしたTARなどの手法でも計測可能ではあるものの、すばやくPDCAを回していくには不向きだ」。
※画像クリックで拡大
この提示について、佐藤氏も「その率直な意見は十分理解できる」と頷く。「特にリーチの計測については、CTVの場合、複数の視聴者が同時に同じ番組を見ていることが想定されるために、デジタル広告でいうところの『ユニークユーザー』という概念で把握するのが難しい。ここを正確に捉えるためには、テクノロジーとマーケティングのフレームの両方を整備する必要がある」。また、TTDを経由した広告配信であれば、Web内に限られてはしまうものの、CTVの視聴後に利用者が別デバイスに遷移した場合でもコンバージョンの計測は可能になるという。
井上氏は効果計測が発展途上な状況ではあるものの、それがCTV/OTTへの投資を控える動機にはならないとし、「もちろん、同時に検証も重ねていくべきで、最終的にLTVの高い顧客を獲得する方法を追求していきたい」と語った。中川氏はTVerIDによってデバイスを横断した計測が可能になりつつあることを示し、「TVerのリーチが伸びてくれば、第三者の計測ベンダーでの効果計測も容易になるだろう。そのためにも、リーチを拡大していきたい」と意欲を見せる。
投資効率を踏まえたプライシング
プライシングに関して、「率直に言って比較的まだ高い印象がある」と小澤氏はストレートに語る。「プライシングを検討していこうとすると、メディアバイイングの複雑さに直面してしまう。初めて投資する広告主にとっては、どうすればよいのかわからないのでは」。
井上氏は「確かに一見、高いと感じる広告主はいるかもしれない」と小澤氏の指摘に同意しながらも、適正な金額に関して時間をかけて議論したいと話す。「CTV/OTTへの投資はメディアの特性としてリターンが高い、つまり実購買につながっているという成果が出始めている。また、若年層や特殊な顧客層をターゲットとして考えた場合、地上波などと比較して必ずしも高いとは言い切れない場合もあるではないかとも思う」。
「たとえばTVerの場合であればプレミアムコンテンツを持つプレイヤーであり、また視聴者の購買リフトアップも高い。プライシングの妥当性については、投資効率という点も加味して考えてもよいと思う」とし、佐藤氏はこう続ける。「先ほどの効果計測の話にも通じるが、費用対効果がさらに正確に可視化されれば、広告主の予算配分もしやすくなり、それによってバイイングルートも収斂されていくはず。我々もそこに向けて尽力したい」。
プライシングについては、最終的にはCTV/OTT事業者の判断・意志にかかってくるもので、バイサイドの取り組みだけでは解消できないもの事実だ。中川氏は「プライシングが高いと感じられる点は、我々自身が提供している価値をより明確にしていく必要がある」と語り、その解決のために、まずは効果計測の確率に向けて尽力するつもりだという。「コンテンツを提供してくれる放送局との連携もTVerの性質上欠かせない。広告主様からの率直な意見として、今後も価値の証明を進めていきたい」。
「CTV/OTTの成長を確信している」
視聴者のライフスタイルの変化やそれに伴う地上波の視聴率低下のなかにあって、広告主をはじめ、エージェンシー、プラットフォーマーがCTV/OTTに寄せる期待は大きい。セッションの最後に小澤氏はこう締めくくった。
「CTVやOTTの将来に向けて、我々が同じ方向を向いているのは間違いない。広告主としては、CTV/OTTの成長を確信しているし、投資も拡大していきたい。そのさらなる後押しのためには、効果計測の確立とプライシングのさらなる向上が大きなカギとなると感じているし、実現することを期待している」。
Sponsored by The Trade Desk
Written by DIGIDAY Brand STUDIO(滝口雅志)
Photo by 渡部幸和