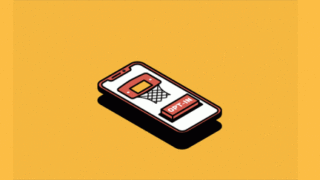家族3人でいろいろなところへ旅行した松永さん一家。平成30年には北海道へ。見渡す限りの広大な大地を3人で走り回った。
池袋暴走死傷事故の第9回公判(7月15日)で、いまだ無罪を主張する飯塚幸三被告(89)を前に、心情等の意見陳述を行った遺族の松永拓也さん。妻・真菜さん(当時31才)と長女・莉子ちゃん(当時3才)との幸せな日々から突然2人の命を奪われた事故当時を思い返して記していくという、想像を絶するような苦しい作業にも半年以上かけて向き合ってきた。
「去年末から準備をし始めて、1行書いては涙が止まらなくなって消して、書いて、また消して、それを毎日繰り返して書きました、向きあう時間は苦しい時間でした。でも、2人の生きていた姿をありありと想像してほしかった。遺族がどれくらい苦しめられているのか被告人に知ってほしかった。意見陳述を終えて、辛かったけれどやってよかったとは思います」(松永さん)。
準備された原稿はA4用紙11枚にわたって綴られていた。
【真菜とは、平成25年、沖縄の母方の親族の集まりで出会いました。私が27歳、真菜が26歳でした。二人で夕食を共にすることになり、待ち合わせで出会った瞬間に、とても美しい人だと思い、私は一目惚れしました。真菜は寡黙な性格でしたが、食事中ずっと私の話を笑顔で聞いてくれました。
温かく穏やかな真菜の人柄に惹かれ、東京に帰ってからも毎日電話をし、月に2〜3回は東京から沖縄に会いに行きました。様々な観光地や島巡りをし、これ以上無い程に楽しい日々でした。今でも色褪せない大事な思い出です。真菜は人の悪口や愚痴を決して言わない人でした。出会った日から亡くなる日まで、たった一度も聞いたことがありません。私はそんな彼女を、心の底から尊敬していました。
真菜に交際を申し込みましたが、二度断られました。後で知ったのですが、真菜はお姉さんを白血病で亡くしており、ご家族のことを想うと、どうしても沖縄を離れる決断が出来なかったそうです。
その年の11月4日、これで駄目だったら諦めようと心に決め、3度目の交際を申込みました。真菜は、「今日は何日か知っている?11月4日だよ。『いいよ』の日だよ。」と照れくさそうに言い、交際を受け入れてくれました。言葉で言い表せないほど嬉しかったです。
その後も遠距離で交際を続け、平成26年5月にプロポーズしました。「頼りない男だけど、あなたを幸せにしたい気持ちは誰にも負けません」。そう伝えると、真菜は「嬉しい」と言い、泣き出しました。その様子を見て、彼女を幸せにしようと心に誓いました。】(以下【】内、松永さんが第9回公判で述べた心情等の意見陳述より)
千葉で結婚生活を始め、ささやかな幸せを日常に重ねる日々。そして平成28年1月11日に長女・莉子ちゃんが誕生する。
【3170グラムの小さな命を胸に抱き、真菜は「かわいい」と涙を流しました。次に私が莉子を抱きしめると、小さな手で私の指を握り返してくれました。その温もりを感じながら、命が生まれることはなんて神秘的なのだろうか。我が子というのは、なんて愛おしいものなのだろうか。そう感じ、私も涙を流しました。そして、命をかけて莉子を産んでくれた真菜に感謝しました。自分が父親になったことにまだ実感が沸かないものの、「この二人を守り、絶対に幸せにする」と心に誓いました。
「莉子」という名前は、真菜と二人で考えました。香りのいい花を咲かせ、人々を癒やす、ジャスミンの花が由来です。花言葉は「愛らしさ」です。ジャスミンのように可憐で、人を癒し、人から愛される。そんな人になってほしいという願いを込めて、ジャスミンの日本語名である「茉莉花」から漢字を用い、莉子という名前に決めました。】
第8回公判で、「亡くなった私の妻と娘の名前を言えますか」「漢字で書くとどういう字ですか」と松永さんに問われた飯塚被告は、「“真”という字に、記憶は定かではないが、菜の花の“菜”。りこさんは難しい字なので書いてみることができない。申し訳ありません」 と答えている。
「名前というのは、親から子への最初のプレゼントであり、願いを込めてつけられ、一生を終えるまで大切にするもの。莉子がそうだったように漢字にも意味があります。被告人は、自身が奪った命なのに答えられませんでした」と松永さんが訴えるように、犠牲となった2人への興味がその程度、という被告人の態度がさらに遺族を苦しめる。
事故当時についても、松永さんは改めて詳細に語った。
【警察署へ運ばれた二人の元へ赴くと、葬儀屋から、莉子の顔の修復作業をするかどうか尋ねられました。できれば修復してあげたかったのですが、損傷が酷いので3日間も離れ離れになると言われ、断腸の思いで断りました。幼い3歳の娘を一人にするなんて可哀想で、一緒に居てあげたいとしか考えられませんでした。
そして二人を家に送ってもらい、自宅に並べられた2つの棺の蓋を交互に開けては、ずっと語りかけました。真菜には、出会ったときの話から始まり、どれだけ愛しているのか、感謝しているのかを。莉子には、私達の子供に生まれてきてくれたこと、沢山の幸せをくれたことに、ありがとうと。二度と出来ないと思い、大好きだったノンタンの絵本を、何度も読み聞かせしました。
眠れるはずもなく、深夜に「ちゃんと莉子の顔を見てお別れを言いたい」と思ってしまい、顔の布をめくろうとしました。しかし、少しめくっただけで分かりました。莉子の顔は完全に陥没していました。全部見たら私の精神が壊れてしまうと察知し、諦めました。最後のお別れなのに、娘の顔すら見ることが出来ない無念さは計り知れないものでした。】
これを聞いて心を締め付けられない人がいるだろうか。しかし、遺族が全身全霊を注いで書いてきた陳述を読み上げている最中に、被告側の弁護士は自分がその後読む弁論の修正をしているようなそぶりを見せたり、飯塚被告はうつむいたまま。
車両に異常や技術的な問題は認められなかったと調べつくされた上、この日の弁論が終わっても、「アクセルとブレーキを踏み間違えたことは、まったくございません。いまも、そう思っております」と飯塚被告は無罪を主張した。
検察側は飯塚被告に対し「不合理な弁解に終始し、自分の主張にのみ固執」と禁錮7年を求刑した(「禁錮」とは刑務所に入るが作業義務がない。作業義務があるのが「懲役」。高齢者や身体が不自由な人の場合は「禁錮」となる)。
2人が死亡し9人が重軽傷という大事故で禁錮7年はあまりに軽すぎると感じる人も多いだろう。しかし、現在の法律では過失運転致死罪の上限が7年なのだ。
「本音を言えば、7年で足りるものではないと思う。しかし日本は法治国家であり、過失運転致死傷の最高刑が7年である以上、仕方がない。検察官の判断に感謝したいと思います」と松永さん。遺族の弁護団の高橋正人弁護士はこう話す。
「過失運転致死罪の上限が7年というのは、“経年劣化”を起こしていると私は思います。昭和40年代の高度経済成長期、国の発展には物流が大事だ、誰でも事故は起こすものという認識だったんです。人命が軽く見られてきた。当時の社会事情はそういうコンセンサスだったが、今はそんな時代ではありません。人の命の方が経済より圧倒的に大事です。そうして見たときに、7年はどう見ても軽すぎる。危険致死傷罪の上限を上げると共に過失運転致死罪も15年くらいに上げないと社会のコンセンサスは得られません」
今回の事故・裁判はさまざまな問題を提起している。松永さんは事件から2年以上たった今でも精神的に不安定になり、眠れない日が続く。時折、手の震えが止まらなくなり、月に一度、被害者支援都民センターで臨床心理士のカウンセリングも受けているという。そんな悲嘆と葛藤と苦悩の日々の中でも、被害者参加制度で裁判に参加し、交通事故撲滅活動を続けているのは、「2人の命を無駄にしたくない」という想いからだ。
ひとりでも多くの人が交通事故や運転について考えるきっかけとなったら、真菜さんと莉子さんの命をつないでいくことになるのではないだろうか。