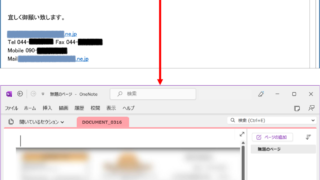イオングループはなぜ流通日本一になれたのか。その背景には、独自の出店計画と店づくりがあった。『イオンを創った男』(プレジデント社)の著者である東海友和さんが解説する――。
※本稿は、東海友和『イオンを創った男』(プレジデント社)の一部を抜粋・再編集したものです。

※写真はイメージです
写真=iStock.com/prill
ショッピングセンターができれば、他の店もできる
立地はつねに変化している。
昔、一等地といえば交差点の角で、あるのは銀行だった。が、今ではそんなところに支店を出しているところはない。
商業立地では、かつては商店街、そこからロードサイドへ、さらに郊外のショピングセンターへと変遷している。また、一方で都心回帰の傾向もある。
イオンの立地戦略の特徴は、「立地創造」である。
現在の繁華街に出店をするのではなく、「キツネやタヌキが出るようなところ」にショッピングセンターを作る。ショッピングセンターが出来上がると、周りには他の店舗や飲食などが出店してくる。もちろん他のサービス業も加わり、新しい商業集団やミニ都市が形成される。
たとえ、近隣に何もなくても、巨大な駐車場を完備したショッピングセンターをよしとする。
それは、新幹線の駅でも同様で、既存の駅につくるよりも地方都市の何もないところに巨大な駐車場付きの駅を新しく作るとしたら、どちらが乗降客が多いか? といったら、駐車場付きの駅だという。
つまり、みんな遠くからでも車でやってきて、新幹線に乗り換えて目的地まで行くからというのである。
20キロ離れたところも商圏になっていた
キツネやタヌキが人より多いというわけではないが、事実、青森県おいらせ町のイオンモール下田は、八戸や十和田からもお客様がいらっしゃる。つくった当初は20キロ以上離れたところも、十分に商圏となっていた。
当然、キツネやタヌキが出るようなところならば、地価も安い。
経営的には地価が安いことは第一条件である。土地や建物の投資は低いほうがよく、投資回収期間は短い方が良い。PL志向ではなく、BS志向、長期適合志向である。
なによりも、立地では広域を狙う。遠くから一目で見えるといった視認性がよく、駐車場もたっぷりとることができる場所。結果、工場、農地、東北地方では元果樹園だったところも多い。
「土日に客足が集中する土地」は将来性がある
もうひとつ、立地に関して「高齢か若いか」といった表現もしている。繁閑差の大きいところは立地が若いという。

撮影=プレジデント社書籍編集部
つまり、平日には客足があるものの、土日には閉店している店が多かったり、客足が少ないというのは、すでに立地としては高齢化していて、将来性は少ない。一方、土日に客足が集中し、平日との売上に差があるようなところは立地が若い。将来性があるといっている。
そして、立地が若いところは、短期的に見れば一週間のうちの二日間、土日しか儲かっていないようだけれど、中期的に見るとそうとも言えないと。こちらでも中長期的な視点で適合するか否かを見ている。
同時に、いま儲かっているところが永久に儲かるわけではないといった、現状に安住しないといった警鐘をも含んでいる。
イオンの出店戦略とショピングセンター戦略はこのように独自性をもち、他社の追随を許さないノウハウと歴史を持っている。したがって、イオンの出店基準のハードルはとても高い。
「第3セクター」方式のところには出店しない
また、岡田は世間でよくある地方自治体や地元が主導する「第3セクター」方式の店舗には出店しないと決めている。
たとえば、立地は繁華街、施設店舗の設計者は著名ではあるが商業者の使い易さを無視した構造やレイアウトなど、結果としてコストも高いところが多い。加えて施設運営も役所優先で無責任体制となる。
岡田はどうしても出店しなくてはならないところは、共有ではなく、区分所有として自社の自由度を確保するよう指示する。つまり、自社のコントロール不可能領域を最小限に抑えようとしているのである。
今日、このような施設に出店した同業者はすべて退店し、その姿はないのがほとんどである。