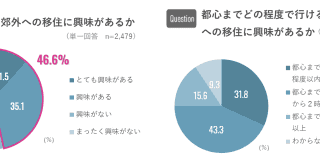東京五輪が終わって早一週間。
メディアの方は、まだ刹那的なイベントの余韻を持て余している感じで、この一週間はある種の”回顧”的な記事も目立ったのだが、そんな中、目に留まったのが、以下の数字だった。
「野球の決勝戦はテレビ中継の平均世帯視聴率が関東地区で37%を記録」(日本経済新聞2021年8月12日付朝刊・第37面、強調筆者)
全ての競技中継の中で最高視聴率を記録したのが、13年ぶりの大会復帰で悲願の金メダルを獲得した「野球」だった、という、いかにも日本人らしいエピソードなのであるが・・・。
自分は先の五輪期間中、野球の試合の中継は全く見ていない。
スコアは時々追っていたし、ダイジェスト映像にもチラリと目を通したがその程度。
全てライブではないものの、他の競技、メジャーなところで言えば卓球や体操からスケートボード、サッカーに女子バスケットボールまで。よりディープなところで言えば、馬術にアーチェリーにテコンドーに近代五種、そして終盤のスポーツクライミングまで・・・と、仕事の合間を縫ってかなりの視聴時間を費やしたのが今回の五輪。それにもかかわらず、「野球」という競技には、この大会期間中、ほとんど関心を惹かれることすらなかった。
理由は至ってシンプル。
「五輪競技、というにはあまりにドラマ性がなさすぎた」
のである。
同じホームペースを囲む球技でも、ソフトボールは違った。
誰もが知っている絶対的エース、上野由岐子投手が13年の時を経て五輪の舞台に再び舞い降り、時を飛び越えたような投球で海外の強打者たちを撫で斬る。
上野投手だけではなく、「女イチロー」などと言う失礼なニックネームを付けられていた山田恵里選手も、”本家”の引退後もなお健在で勝負強いバッティングを見せる。
そして様々な歯車が噛み合った結果、怒涛の5連勝で「連覇」を飾った。
その間、地味な国内リーグと決して注目されない国際大会で実績を積み重ねてきた30歳前後の選手たちを主力に、若干20歳の後藤希友投手まで、この13年間の無念の思いが凝縮されたような快進撃を見たら、誰もが声援を送らずにはいられない。
一方、野球はどうだったか。
バルセロナで公式競技になって以来、アマチュア時代からプロアマ混在、そしてプロだけのチームになった今まで、常に期待されて叶わなかった目標をかなえたのだから、偉業には違いない。
ただ、「国内のプロリーグのいい選手を普通に集めた」という選手たちの顔ぶれに”ドラマ”感は全くなかった*1。
自分もバルセロナの頃は「アマチュアゆえの勝負への執念」を示した代表チームを敬意をもって眺めていたし、シドニーでも杉浦正則投手を筆頭にプライドを持って参加したアマチュア選手たちと、松坂大輔投手をはじめとする初参加のプロ選手たちの融合に声援を送っていたような気がする。
しかし、そのうちにアマチュア選手の参加はなくなり、長年看板を背負っていた松坂大輔投手も渡米し、加えて大会のたびに、勝手の違う舞台で途方に暮れる高給のプロ選手たちの姿を見せられるたびに、声援を送る気持ちは薄れていった。
そして長い中断を経て戻ってきた舞台でも、試合にこそ勝ち続けたものの、「五輪ならでは」の何かを感じさせるようなことは最後までなかったような気がする。何といっても抑えをやっているのが今年入団したばかりのルーキーなのだから、チームとしての連続性もへったくれもない。
未だに国内No.1のプロリーグを持ち、潤沢に一流の選手たちを抱えるからこそ、のチーム編成は、このコロナ禍下で自国の選手を招集するのにも四苦八苦していた感があった他国のチームとの比較では圧倒的な優位性があったといえるだろうし*2、それゆえに地元開催国としては「満点」の回答を出すこともできたわけだが、それは、もはや五輪競技としての野球への関心を他のほとんどの国が失っている、という残酷な現実の裏返しでしかない。
状況を理解している者なら誰もが感じた「これが五輪での最初で最後のこの競技の金メダルなんだろうな」という残念感を打ち消そうとするかのように、
「2028年ロス五輪で再び野球は復活する!」
と声高に叫ぶ人も時々見かけたが、米国人が本当に五輪競技としての野球に興味を持っているのだとしたら、決勝戦があの時間帯に行われる、ということはあり得なかっただろう。
万が一、2028年に「BASEBALL」が奇跡の復活を遂げたとしても、夏の開催なら当地はMBLのシーズン真っただ中で、有力球団がしのぎを削る西海岸では、まともな試合会場を確保することさえ難しいのではないかと推察する。