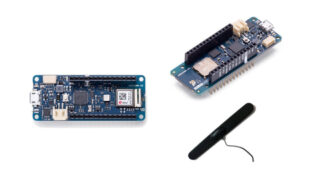ウクライナ戦争をきっかけに「侵略」とは何か、「正しい戦争」は存在するのか、といった問題が論じられています。これは哲学的にはむずかしい問題で、100年前から論争になっています。2015年3月20日の記事の再掲です。
戦後70年を総括するとき、あの戦争が<侵略>だったのかという問題ばかりが論じられるのは不幸なことだ。それは国際法的には自明だが、大した意味はない。<侵略>は戦争の敗者を罰するためにつくられた政治的概念だからである。
シュミットは「侵略」の概念を否定した
第1次大戦で戦争責任を一方的に負わされたドイツ人は憤り、カール・シュミットは「勝者の秩序」としての国際連盟の正統性に疑問を抱く。それは「法の支配」の形式をとるが、国際法に法の支配は存在しない。
国際法は、戦勝国による占領という現状維持の秩序だった。<侵略>の定義はないが、それは1928年の不戦条約以後に行われた国境侵犯と理解されている。したがって1931年の満州事変は侵略だが、1844年のアヘン戦争は侵略ではない。
国際連盟を支える国家主権の概念にも、シュミットは疑問を抱く。その加盟国は自律的でも同質的でもないので、国際連盟は脆弱だった。それは自由主義的な普遍性を建て前にしていたが、実態は国際法と称する戦勝国の論理で各国に干渉する「間接支配」の体制であり、ドイツの主権は徹底的に排除されていた。
そしてドイツ革命の失敗後も不安定な政治状況の続くワイマール体制をシュミットは批判し、例外状態について決断する指導者を求めてナチスに入党する。国家の正統性を支えるのは実定法主義による法の支配ではなく、共同体による自然法的な秩序(ノモス)だ、というのがシュミットの批判だったが、そのノモスがいかに正統化されるかは不明だった。
シュミットの「民族的同質性」の思想がヒトラーに悪用された末に、彼はナチからも追放されたが、その思想がヒトラーを生む危険をはらんでいたことは否定できない。ワイマール体制の「決められない政治」にいらだった彼が法を超える主権者を支持したとき、独裁者の直接支配が生まれた。
戦後のシュミットは学界から追放されたが、資本主義が国家を支配する「経済帝国主義」を批判し続けた。彼の死後、世界秩序は国家主権を守る国連の普遍主義から、アメリカ一極支配による正戦に回帰し、湾岸戦争やイラク戦争などによってアメリカは「世界の主権者」の地位を獲得したかにみえる。
もともと主権国家は、正戦の論理にもとづく宗教戦争をやめ、複数の宗派を認める自由主義の理念でつくられた「中立国家」だったが、今やアメリカは国連決議もなしにイラクに介入する一国主義になり、中立性も実定法主義も放棄してイスラム世界との世界内戦を始めた。それは戦後の「戦争違法化」の流れに反するものだ。
国際社会に客観的な「正義」は存在しない
本書はシュミットの国際政治論を初期から晩年に至るまで整理する概説書としてはよく書けているが、最後になって唐突に、グローバル資本主義に奉仕する「新自由主義」の国家を批判して終わるのはいただけない。むしろ今は経済帝国主義(英米の功利主義)と主権国家の利害が対立することが、さまざまな軋轢を生んでいる。
冷戦終了後、アメリカが勝手に世界の警察官を演じた状況には問題があるが、オバマ政権が世界の警察から退却した2010年代には、中東や東欧で内乱や戦争が増えた。EUがロシアとの摩擦を避けてウクライナを緩衝地帯にしたことが、その混乱の原因になった。
ウクライナ戦争もプーチンにとってはロシア帝国の中の内戦であり、NATOが経済制裁するのは内政干渉だと思っているだろう。そこでは皇帝の正統性を疑う者を殲滅して国家秩序を維持することが「正しい戦争」なのだ。
今回の戦争は、国際社会に正義は存在するのかというシュミットの問いを改めて提起した。プーチンの戦争犯罪は明らかだが、ウクライナの内戦でゼレンスキー政権がつねに正しかったわけではなく、アメリカが中立だったわけでもない。
だから今もくりかえし出てくる「どっちもどっち」論には、一面の真理がある。国際社会は本質的にアナーキーであり、客観的な悪は存在しない。すべての悪は相対的なので、この問いには誰にとっての悪かという条件つきでしか答えることはできないのだ。
あなたが人を殺すのは悪だが、犬を殺すのは悪ではない。それは犬にとっては正義ではないだろうが、われわれの社会は人と犬の間で線を引いている。シュミットが批判したように、<侵略>も英米中心のご都合主義だが、それを悪と定義しないと、歴史上もっとも激しく戦争を続けてきたヨーロッパの国家は維持できないのだ。