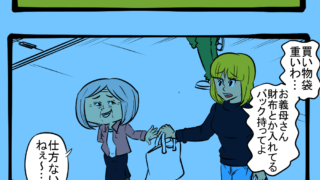「Internet Week 2021」において11月19日、恒例となっている「ランチのおともにDNS」が昨年に引き続きオンラインで開催された。今年のタイトルは「DNSの『明日のカタチ』について考える」。講演者である株式会社日本レジストリサービス(JPRS)の森下泰宏氏と芳野光氏がその全体概要を、誕生当時・今日・明日という3つに分けて解説した。
DNSの誕生は、ARPANETがTCP/IPを標準プロトコルとして採用した年と同じ1983年であり、以来、インターネットにおける基盤サービスの1つとして、重要な位置を占め続けてきた。今回のランチタイムウェビナーでは、そのDNSに起きたさまざまな変化とその理由、今後起こるであろう変化に関する考察などが述べられた。今回の発表に合わせて作られた資料は盛り沢山なので詳細はそちらに譲り、本稿では、この内容のうち主立った部分についてレポートする。
インターネットの急速な普及に対応したDNS
冒頭、「誕生当時のDNSとその進化のカタチ」を担当した芳野氏は、インターネットが始まった当時、DNSは動かすことが優先であり、悪意の存在を想定していなかったことを述べた(図1)。
動かすことが優先、悪意の存在を想定しないという「カタチ」は、当時のインターネットは利用者や利用目的が制限されており、かつ匿名ではなかったこと、コンピューターの処理能力の低さや通信環境がさほどよくなかったという背景を考えると、やむを得なかったとも言える。当時のインターネットはとにかく相手とつながることが最優先であり、通信プロトコルはシンプルで動作が軽く、実装・運用が容易であることが求められていた。
図1で示される内容は、現在もDNSの解説書でよく見かける内容である。UDPを使用し、平文による問い合わせと応答が1セット、UDPメッセージサイズの最大値が512バイトといった内容は、古くからDNSに関わっておられる方にはおなじみのものであろう(この図はあとで意味を持つので、覚えておいていただきたい)。
DNSの本来の役割は「名前解決」であり、ドメイン名とIPアドレスを紐付けることで、アクセスしたい相手と名前で通信できるようにすることである。すなわち、分かりにくく覚えにくいIPアドレスに替え、人間にとって分かりやすく使いやすい「名前」を使えるようにするというのが、HOSTS.TXTから続くそもそもの役割である。
しかしながら、DNSでは当初からドメイン名に対応するIPアドレスだけでなく、より一般的な情報を扱うことも想定していた。それを活用した代表例がMXレコードであり、「そのドメイン名宛ての電子メールを送信すべきサーバー」を情報として登録できるようになっていた。この機能は従来のHOSTS.TXTでは実現が難しく、電子メールの普及がDNSの普及を促進する原動力の1つとなった(図2)。
その後、インターネットが広く普及していく中で、DNSにおいても足りない機能の追加や新たなニーズへの対応、信頼性や利便性の向上が図られていった(図3)。機能追加の例としてIPv6アドレスや国際化ドメイン名が挙げられるが、資料では他に、DNS NOTIFYによる権威DNSサーバー間のゾーンデータ同期の迅速化やネガティブキャッシュによる名前解決の効率向上、BIND以外のDNSソフトウェア実装の登場などについても述べられている(図4)。
明日のDNSは、まだDNS
未来の予測は難しく、分からないことも多い。そこで、「明日のDNSのカタチとは」では、今起こりつつある変化から今後起こりうる変化の兆しを捉え、サービス形態や利用形態がどう変わっていくかを予測したということである。
今起こりつつある変化として挙げられたのは、HTTPSレコードとOblivious DoHの2つである(図14、図15)。
HTTPSレコードは、ゾーン頂点の別名、ウェブサーバーの優先度設定、HTTPS接続情報の提供といったHTTPSサービスの利用・提供に関するさまざまなニーズを一度に実現する「野心的な内容」(森下氏)を持った、新しいDNSリソースレコードである。
Oblivious DoHは、ユーザーのDNS問い合わせ・応答を中継するプロキシを導入し、HTTPSで暗号化した通信路にエンドツーエンドで暗号化したDNSデータを流すようにすることでユーザーのIPアドレスとDNS問い合わせの内容を同時に入手できないようにし、プライバシーを保護するための仕組みである。Oblivious DoHは、AppleがiCloud Private Relayで採用している。
どちらもインターネットのサービス形態・利用形態の変化への対応であり、今後起こるであろう変化も同様に、インターネットのサービス形態・利用形態の変化が鍵となるであろうことが説明された(図16)。
では、今後起こるであろうインターネットの変化とは何であろうか。森下氏は、現状で見られる変化の兆しとして、通信形態の変化と移動体通信の強化を挙げた(図17)。
インターネットは、ユニキャストと呼ばれる単一の相手に対してデータを送信するという形(一対一)をベースに、IPアドレスを使用したエンドツーエンドの通信を行うことで発展してきた。しかし、現在では、端末は利用者とともに自由に移動するし、CDNサービスやIoTデバイス間の通信で見られるような、一対多や多対多のコミュニケーションをより効率よく実現したいというニーズも出てくるようになった。加えて、動画配信をはじめとする大容量のデータ通信が頻繁に行われるようになったことで、通信帯域が常に圧迫されるようにもなってきている。
そのような状況下で出てきたものが「情報指向ネットワーク(Information/Content-Centric Networking:ICN)」と呼ばれる考え方である。この考え方では、欲しいコンテンツを示す「名前」を指定して要求すると、ルーターが自分のところに要求元が求めるコンテンツがあるかを確認し、持っていればそれを案内する。持っていなければ、隣接するルーターに要求を転送するという動作になる。これにより、自然にネットワーク的に近いところからコンテンツが得られることになる。
DNSではドメイン名を指定して対応するIPアドレスを得るが、ICNではコンテンツの名前を指定してコンテンツを得る、これまでとは異なる方向性を持った新しいネーミングサービスである。これが広まるかどうかは、使いやすさや実効性の面などの要考慮点や課題も多く、流動的な部分が多い。しかし、将来、DNSに替わる何かしらの強力なネーミングサービスが出現し、ユーザーは主にそれを使うようになることも、可能性としてあり得ると考えておくべきであろう(図18)。
森下氏は、もし新しいネーミングサービスが開発されるとしたらという前提で、「最低限、この3つの問題を解決して欲しい」ということを述べている(図19)。確かに「データの更新に冷たい」「運用ミスに冷たい」「切り替えがルーズ」という、DNSが「生まれながらに持ってしまった」特性に起因するトラブル事例や障害事例は、枚挙にいとまがない。
現実を見ると、DNSに替わるネーミングサービスは当分出てきそうもない。加えて、DNSはさまざまなサービスから出されるさまざまな要求を飲み込んでいく柔軟性を兼ね備えている。そうした状況を考えると、森下氏の「明日のDNSは、まだDNSであろう」という言葉には同意しかない(図20)。
今後、インターネットのサービス形態・利用形態が大きく変化し、それに適合する強力なネーミングサービスが開発され普及しても、DNSという仕組みが一気に置き換えられるということはないだろう。利用者がDNSを直接使わなくなっても、インターネットに接続されたホスト同士を結び付ける基盤技術として、重要な位置を占めていくことに変わりはないはずだ。
森下氏は、最後に「明日の、そして未来のインターネットを支えるため、一緒に頑張っていきましょう」という言葉で締めくくった。今回の資料は、すでにJPRSのサイトで公開されている。時代に伴うDNSの変化がよくまとまっているので参照されたい。