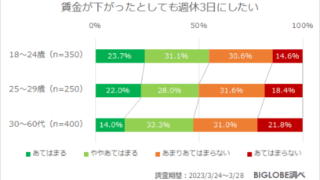こんにちは。
先日、「アメリカでマネーサプライM2の前年同期比変化率が今年の1月時点でゼロ、またはマイナスになった」とTweetしたところ、「マネーサプライM2の変化率ってなんですか?」とのご質問をいただきました。
とても重要なのに、案外正確に把握していらっしゃる方の少ない概念ですので、「超初歩からの経済学入門」コーナーで取り上げようと思います。

imaginima/iStock
M2とは実際の取引にひんぱんに使われる通貨のことです
まず、実際に何かを買ったときに支払う通貨には、現金以外にさまざまな代用品があって、その実用性の高さからいくつかの段階に分けられています。そこから確認していきましょう。

M1というと漫才日本一を決めるM-1グランプリを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、あの正式名称にはMと1のあいだにハイフン(-)が入っています。お間違えなきよう。
マネーサプライでM1というと、紙幣と硬貨からなる現金、そして要求次第で銀行は支払う義務を負っているタイプの預金(当座預金+普通預金)だけを指します。
ちょっと前までは、現金だけはマネタリーベース(あらゆる通貨の基礎)とかハイパワードマネー(強い力を持った通貨)とか言って特別扱いをする傾向がありました。
しかし、最近では日本以外の先進国では大きな金額の取引にはまず現金を使わなくなったという事情もあって、現金を特別視する風潮はすたれています。
日本でちょっと大きな金額の不動産取引で頭金と名義を書き換えた土地登記証や売買契約書の受け渡しをされた方は、次のような光景をご記憶ではないでしょうか。
今でもいちばん確実な金銭のやり取りは、買い手が口座を持っている銀行支店の個室に売り手、買い手、双方のエージェントが集まって、買い手の口座から頭金相当額を引き出し、札束の枚数を数えてから売り手の口座に入金することとされています。
欧米の口座から口座への送受金だけで済ますやり方と比べると、なんと原始的でムダな手間をかけるものかとお思いの方もいらっしゃるでしょう。
ですが、詐欺などの被害を防ぐためにはじつはこれがいちばん安全確実な金銭の受け渡し方なのです。
口座間の送受金だけで済ませると、出納係が確かめる一瞬だけ入金されていた資金が直後に全額引き出されていて、売り手が受け取ったはずの資金は入ってこず、「買い手」は売買契約書とともに行方をくらましていたといったことは、けっこうあるそうです。
日本では今でも、総額が大きな取引になるほど口座から引き出した現金を数えて確認するという作業が励行されるのは、まちがっても銀行が武装強盗団に襲撃される危険もなく、札束にニセ札が混じっている確率も限りなくゼロに近いという安全で平和な社会だからです。
あとでくわしくご説明しますがアメリカでは「現金は決済通貨からはずしたほうが、より正確にマネーサプライの実情を反映する」と主張する人たちも登場しています。そして、アメリカ経済の実態を見ると、この主張には大きな説得力があると思います。
M2が重視されるのは、決済の大半をカバーするから
M2とは、このM1に「預金者が解約する」というひと手間を加えれば、現金や要求払い預金に換えることのできる定期預金など(これをほとんど通貨と同じという意味で「準通貨」と呼ぶこともあります)を加えたもののことです。
実際の決済の大部分はこのM2の範囲内にある通貨や準通貨でおこなわれるので、M2が増加しているときは経済が発展している時期、縮小している時期は経済が停滞あるいは衰退している時期と見ても大きな間違いではないと考えられています。
「M3だってあるじゃないか」という気もしますが、やはり決済金額全体に占める割合からすると微々たるもので、M2さえ押さえておけば経済全体でどの程度の資金が循環しているかをつかめるということです。
そのM2に第二次世界大戦直後以来の大異変が
じつは今、アメリカで「今年の1月のM2の前年同月比変化率がゼロか、マイナスになっている可能性が高い」と考える人が多くなって、かなり深刻な事態だと憂慮されています。
まだ1月もあと1週間ぐらい残っているという時点で、実績見込みに近い予測として次のようなグラフが発表されました。
「1990年代前半には2度ゼロ近辺に下がったが、それはM2成長率が5%未満に低迷していた時期のことだった。今回はわずか2年前に20%台後半だったものが、丸2年で30パーセンテージポイントも下がって、マイナス2.3%になったのだから大変だ」というわけです。
もう少し長い射程で見ているビアンコ・リサーチという会社は「今回のM2成長率の大収縮は、大戦争直後や大不況のまっただ中以外にはなかった事態だ」と解説しています。
ふつう、M2の成長率がここまで下がるのは景気がはっきり悪化してからのことです。まだ景気後退に入ったかどうかが議論の対象になっている時点で、これほどマネーサプライが停滞しているのは、いったいなぜでしょうか?
ここで、先ほどちょっと触れた「なまじ現金を決済通貨の中に入れておくから、実際に決済に使える通貨量を誤解することになる。いっそM2から現金を外した数値によってマネーサプライの実情を判断すべきだ」という主張が意味を持ってきます。
「現金は通貨にあらず」説にも一理あり
この現金を決済通貨から外すという理論の有力な提唱者であるレイシー・ハントによると、M2とM2から現金を除外したOther Deposit Liabilities(ODL)の流通速度は、米国長期債金利と以下のような相関性を示すそうです。
なお、マネーサプライのいろいろな指標の流通速度とは、GDPをその指標で割った数字のことです。
具体的には、1年間のモノやサービスの取引をおこなうために、決済通貨全体が何回やり取りされたかを示す数字です。
ODLはM2から現金を引いた分だけM2より小さくなるので、双方を分母として同じGDPを分子として算出した流通速度はODLのほうがM2より大きくなるのは当然です。
また決定係数もどちらも同じような数字で、通貨の流通速度と長期債利回りには強い正の相関性があることを示しています。
大きな違いは、平均値より速い(回転数が多い)時期が長いか、遅い(回転数が少ない)時期が多いかでしょう。
M2の流通速度は、平均値より少し速い時期が長く続き、平均値より遅い時期は短いけれども大きく下がっています。逆にODLは平均値より少し遅い時期が長く続き、平均値より早い時期は短いけれども大幅に速くなります。
この差が顕著なのが、1950~70年代です。M2で見ると流通速度が平均値より速くて、ややインフレ気味の経済だったことを示唆していますが、ODLで見ると流通速度が平均値より遅くて、物価水準が安定していた中での経済成長だったことを示唆しています。
私は、それまで比較的物価も安定した中での経済成長が急激にインフレ化したのが1990年代のアメリカだったと考えていますので、両者を比べるとODLのほうが実態を正しく反映していると見ます。
この印象は、次のグラフでさらに強まります。
この2つのマネーサプライ指標を、ともに消費者物価上昇率によって実質化して比べると、増加率のピークや減少率のボトムが、ハイテクバブルが膨張しはじめた1990年代末以外では一貫して、ODLのほうが大きくなっています。
つまり、それだけM2よりODLのほうが、経済全体の好不調に対する感応度が鋭いわけです。さらに、日常生活でこまごまとしたものを買う以外には、ほとんど現金決済はおこなわれていないのが実情です。
決済通貨から現金を外すという一見乱暴な議論は、アメリカのマネーサプライの実態に迫るためには、むしろ必要な変更ではないでしょうか。
なお「たとえ実際に決済通貨として使うことはなくても、現金を注入してもらわなければ銀行は融資をしたくても貸し出す原資がないという事態もあるので、やはり現金は決済通貨から外すべきではない」という反論は成り立ちません。
アメリカの銀行業界全体として預金額に対する融資額の比率(預貸率)が50%前後という現状では、銀行が融資のための資金に困ることは、ほとんどあり得ないのです。
もし、決済通貨から現金を外しても差し支えないどころか、そのほうが決済通貨の量を正確に判断できるとしたら、金融市場の実情はどういう姿に見えてくるでしょうか?
中央銀行に決済通貨量を決める権限なし
中央銀行がいくら現金の供給量を増やそうが、減らそうが、ODLだけではなくM2もほとんど反応しないのです。
このへんの事情を劇的なかたちで示したのが、2020年春ロックダウンで経済活動全体が委縮してしまったことにうろたえた連邦準備制度が正気の沙汰とは思えないほど現金の供給量を増やしたときに、ODLとM2がどう変わったかでしょう。
上段のグラフは1959年代末からの長期変動で、2020年から約1年半のM1の増加ぶりがどれほど常軌を逸していたかを示しています。
下段はこの大激増近辺の拡大図ですが、M2はほんの少しばかりM1に上積みしたのに対し、ODLはM1の伸び率を抑制した伸びになっています。
前年同期比の変化率で見ると、M1とM2・ODLでは同じグラフの中に収まらないほど、大きな差が出ています。
こちらのグラフではっきり変化がわかるのはM1だけで、増加率のピークでは前年同期比360%弱になっています。M1総額は1年で4.6倍になったということです。
M1を外して、ODLとM2の変化率を比較したのが、下のグラフです。
こちらも上段が長期、下段がM1変化率のピーク近辺となっています。ちょっと意外ですが、M1増加率のピークではM2よりODLの増加率のほうがやや高く、逆にその後の縮小局面ではODLのほうがM2より減少率が大きくなっています。
決済通貨ではない現金をなぜばら撒くのか?
ここでも現金という実際の決済にはほとんど使わない部分を含むM2のほうが景気刺激策に対する感応度が鈍く、その分だけ反動減も小さく済んでいるわけです。
ということは、アメリカの中央銀行である連邦準備制度(FedまたはFRB)としても、どうせ現実の決済通貨量は大して変わらないことを承知の上で「ロックダウンによる景気悪化を避けるために、こんなに大胆な政策を取っている」というジェスチャーとして、あんなに大量の現金をばら撒いたのではないでしょうか。
連邦準備制度だけではなく、世界中の中央銀行が自分たちは流通している決済通貨の量も金利水準も決定する権限を持っていないと知っているのだと思います。
ただ、世間にはまだ自分たちがそういう権限を持っていると思いこませるために、景気がよくなりそうだと思うと、金利を低下させながら通貨供給を増やし、景気が悪化しそうだと思うと、金利を低下させながら通貨供給量を絞りこんでいるのではないでしょうか。
それだけでも、本来であれば景気変動をなるべく平準化して安定成長を目指すべき中央銀行の使命を怠っているどころか、景気の振幅を拡大しているのですから、採点すれば零点どころかマイナス点です。
それだけではありません。中央銀行による現金のばら撒きは経済成長のための資金循環を円滑にするという役割は果たせない「見せガネ」ですが、特定産業には莫大な利益をもたらすという不公平な仕組みを支えているのです。
その特定産業とは、言うまでもなく金融業界です。
新型コロナ対策としてのじゃぶじゃぶの現金供給がピークに達した頃から、Fedによるリバース(逆)レポ契約を利用する金融機関が激増したというニュースをご存じでしょうか。
実際には、次のグラフでご覧のとおり、とんでもない勢いで伸びています。
去年6月末の段階で総額2兆3300億ドルに達していたリバースレポによって、アメリカの金融機関は1日当たり1000億ドル強、日本円にして13兆円という高額の利子収入を得ていました。
なぜ、こんなボロ儲けができるのかというと、それにはいろいろと複雑な事情があります。
まずリバースではない、ふつうのレポとは何かからご説明していきましょう。金融機関にはたった1日だけでも一定額の米国債を持っている必要があるけれども、手元にそれだけの金額分の米国債がない場合があります。
そのときは、1日だけFedから米国債を借り入れるのですが「翌日には日割りの金利分だけ安くした金額で売り戻す」という約定で、いったん買い入れる形をとります。これを売り戻し特約付き購入と言います。
で、もしFedが1日だけ金融機関から米国債を借り入れるとすれば、金融機関にとって売り戻し特約付き購入とは逆に、買戻し特約付き販売ということになります。
売り買い双方の対称性を保つためには、売り戻し特約付き購入で金利を取られるのなら、買戻し特約付き販売のときには日割りの金利分安い金額で買い戻す、つまり1日分の金利収入があって当然だという理屈になります。
ただ、Fedには金融機関から米国債を借りなければならない理由はまったくないわけですから、これはもう強引に金融機関に楽をして儲けさせてやるためのへ理屈に過ぎません。
金融業界全体に奉仕するFed
それでも、こういうへ理屈が通るのは、アメリカの金融機関の中には階級があって、Fedに口座をつくってそこに余剰資金を預けておく権利がある銀行と、Fedに口座を開設する権利を持たない金融機関があります。
そして、Fedに預金をできる(これをFedに準備を積むと表現します)銀行は、法定準備率を超えた超過準備の金額に対する金利をFedから受け取れるのです。そして、超低金利の世の中でFedから受け取る年率1%強の金利収入はバカにならない金額となっていました。
2020年3月に、Fedは法定準備率を0%に引き下げました。そうなると法定準備と超過準備の区別はなくなり、したがって超過準備に対する利子供給もなくなるはずですが、Fedは銀行がFedに預け入れている準備は全額超過準備として金利を払っています。
そこで、Fedに口座を持っていて、自行の預金のうち融資や投資で運用できない分は全額この口座に準備として預け入れている銀行がFedから受け取る金利収入は激増しました。
そうすると、Fedに口座を持てない金融機関は「自分たちにもノーリスク・ノーワークの金利収入をくれ」と騒ぎ出します。
もともと純然たる政府機関ではなく、金融業界から政府に送りこまれた利益代表であるFedとしても、そういう声に応えることこそ本来の使命ですから、リバースレポというカネの成る木を広く一般金融機関に提供しているわけです。
上段に書きこまれた「ロックダウンによる経済活動全般の低迷で……」というのは上っ面だけの理由です。
銀行によるFed準備激増のほんとうの理由は、法定準備がゼロになったのでFed口座に預けている金額全部が金利収入を得られることになったことなのは、すでにご説明しました。
それにしても、アメリカ国民はFedによるじゃぶじゃぶの通貨供給で不況下のインフレが続くリスクが高まるだけではなく、毎日2400億ドル強(約31兆円)をFedが金融機関にばら撒いていることのツケもいずれ支払わされるのです。
腐れ縁はFedと金融業界にとどまらない
しかも、1946年にロビイング規制法という名の贈収賄合法化法が通って以来、あらゆる官公庁の官僚たちは自分たちが監督しているはずの業界から巨額のワイロをもらい、官職を去ったあとはスポンサー企業に高給で雇われるので、業界の都合最優先の行政をしています。
その点は、金融業界だけではなく、軍需産業も、製薬産業もまったく変わりません。こんなに既得権益集団の横暴がまかり通る国の経済は、お先真っ暗でしょう。
■
増田先生の新刊「人類9割削減計画」が発売されました。ぜひご覧ください。
編集部より:この記事は増田悦佐氏のブログ「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」2022年2月2日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方は「読みたいから書き、書きたいから調べるーー増田悦佐の珍事・奇書探訪」をご覧ください。