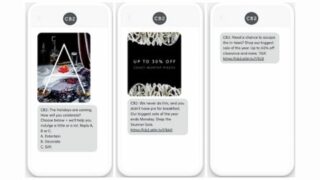東京オリンピック・パラリンピックは、日本が国際社会で生き残れるかどうかの大きな試金石になるかもしれない。

電通本社ビル Wikipediaより
小山田圭吾氏に続き、絵本作家のぶみ氏がオリパラの役職から辞任し、開閉会式の「ショーディレクター」を務める小林賢太郎氏も米ユダヤ系団体「サイモン・ウィーゼンタール・センター(SWC)」から抗議を受けて、電撃的に解任された。
国際社会の標準的な価値観に真っ向から挑戦している内容を伴っており、いずれも深刻である。女性蔑視発言による辞任が相次いだオリパラだが、開会直前になってメガトン級の価値観をめぐる争いを、日本の電通・博報堂が主導するオリパラ準備チームが仕掛けている流れだ。
「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開会式および閉会式コンセプト」なるものが、開会式直前になって出された。

「復興五輪」などの従来から語られてきた理念が盛り込まれなかったことが話題になるとともに、謎めいた英単語が羅列されていることへの違和感が表明されている。
たとえば閉会式では、「Worlds we share」という概念がテーマとされた。だがなぜ「世界(World)」が複数形になっているのか。
地球人と火星人の戦いや、冷戦時代の米ソ対立の様子を描写するときくらいでなければ、普通は「世界(World)」を複数形にすることはない。
公式説明は、「“Worlds we share”という表記は、本来『世界』は『The World』と表記するところを、『Worlds』と表記することで、一人ひとりが異なる世界を持っている様相を表し、『一人ひとりの持つ異なる世界を共有しあって生きている』ということを表現しています」、とする。
しかし通常は、多様性(diversity)を包含する(include)することができるのは「世界(The world)」という一つの共通の場があればこそだ。「世界」それ自体が複数になってしまうと「共有する場」が失われてしまう、というのが、普通の国際社会の考え方である。80億近い人々全員が自分たちだけの「世界」を持っているという考え方は、ラディカルな相対主義であり、国際社会の標準的な価値規範に真っ向から対決を挑むものだ、と言わざるを得ない。
開閉会式のプロデューサーチームを統括する日置貴之氏は博報堂の出身だ。今回のオリパラでは、電通・博報堂などの広告代理店が運営に深く食い込んでいる様子が目立っている。

オリンピックが延期になって電通などに巨額の損失が発生していると指摘された昨年から、さらにいっそう広告代理店に新規契約が回っている印象を受けざるをえない。その結果、広告代理店が取り仕切る人事で、開閉会式を構成する人物たちが、総入れ替えになった。そして、次々と価値観をめぐるスキャンダルが発生するようになった。
この背景に「複数形のWorlds」があるように思えてならない。日本の広告代理店の見込みでは、世界中の人々はバラバラだが、なぜかわからず何となくオリンピックの「感情(emotion)」だけで結びつく、ということらしい。「複数形のWorlds」の背景には、深刻にいがみ合っている人たちもオリンピックを見れば仲良くなる、といった超楽観主義的な考え方があるようだ。
現在進行形の価値観をめぐる騒動をみると、この日本の広告代理店が突きつける考え方に、果たして根拠があったのか、甚だ疑わしい。
日本の島国社会の「ムラ文化」では、価値観の体系的な表明や議論をへることなく、「腹芸」的な「あうんの呼吸」による「空気を読む」同調主義の文化で、不文律の規則が適用されていく。この社会の特徴と弊害は、新型コロナの「自粛」ムードの中で、日本人自身も痛いほど感じているところだ。
「世界はバラバラ、共通の価値観なんかない、でもオリンピックを見ると理由もなく皆仲良くなる」、というメッセージが、「ムラ社会」日本人の世間離れした不文律の同調主義を強要する態度によるものではないかには、深刻な疑念の余地がある。
本当の世界では、人々は価値観をめぐる深刻な争いをしている。いわば生きるか死ぬかの状況の中で、何が最も正しい価値観なのか、を議論しあっている。
そこに日本の広告代理店が現れて、「女性蔑視するのも一つの世界、共有しあおう」、「凄惨ないじめも一つの世界、共有しあおう」、「ホロコーストをギャグにするのも一つの世界、共有しあおう」といった世界観を、同調主義的文化の態度にもとづいて、各国の人々に強要しようとすることは、控えめに言って、相当に冒険主義的なことである。
巨額の財政赤字を抱えながら、広告代理店に大型契約を発注し、誰も責任をとらない仕組みを拡大再生産しながら、日本は「複数形の世界」を求めるオリパラを実施しようとしている。
果たして日本はこのオリパラを乗り切れるのか。
そもそもなぜ、日本はこんな冒険主義的な試みをしているのか。
議論が必要だ。