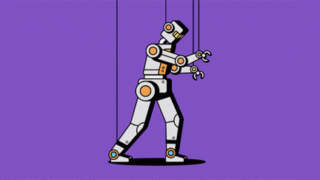ふるさと納税で稼いでも「焼け石に水」
「ふるさと納税」の季節がやってきた。お気に入りの自治体に「寄付」することで、自分が本来払う地方税から控除される仕組みで、ほとんど負担なしに「寄付」ができ、そのお礼に地域の特産品などの「返礼品」が手に入るため、人気を博している。年間の所得に応じて控除上限が決まるので、年末に向けて手続きをする人が急増する。年々寄付総額は伸び、自治体側も工夫次第で「収入」が増えるため、魅力ある返礼品を用意するなど、ふるさと納税獲得競争に力を注いでいる。

※写真はイメージです – 写真=iStock.com/okugawa
何せ、人口減少が深刻化し、地方税収が増える見込みが立たない中で、「ふるさと納税」が唯一といって良い「増収策」になっているのだ。住民の高齢化で社会保障費が増え続ける中で、道路や公共施設などインフラの老朽化が進んでも修繕する財源すらなかなか確保できない自治体が増えつつある。残念ながら、ふるさと納税が増えているとは言っても、その収入増では「焼け石に水」。国から配られる「地方交付税交付金」への依存度はますます高まり、自治体からは「自立する」意欲がどんどん失われている。このままでは多くの自治体が、座して死を待つ運命なのだ。
ふるさと納税制度の「生みの親」菅前首相が官邸を去った
だが、国は抜本的な自立策を立てないまま、ふるさと納税の拡大にも背を向ける。ふるさと納税制度の「生みの親」だった菅義偉前首相が官邸を去ったことで、制度そのものの先行きも危ぶまれる。いったい、自治体はどうなっていくのか。
「ふるさと納税」は第一次安倍晋三内閣だった2007年に、菅総務相が創設を表明した。働いて稼げるようになってから、自分が生まれ育った故郷に税金を納める仕組みが作れないか、というアイデアは多くの自治体首長などから出されていた。集団就職で上京した菅氏はその思いに共鳴したのだろう。以来、官房長官、首相としてふるさと納税制度を擁護し続けた。
2008年に始まった制度によって、寄付額は年々拡大。2020年度に自治体が受け入れた「ふるさと納税(寄付)」の受入総額は6724億円となった。2019年度は制度変更の影響で18年度を下回ったが、20年度は1.4倍に拡大、過去最高額を記録した。
人気の理由は何と言っても自治体が競って提供する「返礼品」の魅力だが、そうした「返礼品目当て」の寄付を総務省は批判的に見てきた。識者の中にも、「寄付なのに返礼品を出すのはおかしい」「ほとんど負担せずに返礼品をもらう仕組みは問題」という声があった。一方で、自治体からは「地元の特産品をアピールする一方で歳入も増え一石二鳥」「ふるさと納税を増やそうと創意工夫するカルチャーが役所の中に生まれた」と言った肯定的な声もあった。
“成果”を上げた自治体を目の敵にした総務省
もともとこの制度に乗り気でなかった総務省は、2018年に過度な返礼品競争はけしからんとして、制度の見直しを実施。返礼品を地元産品に限定し、寄付額に対する返礼品の金額に30%という制限を設けた。その上で指導に従わなかった大阪府泉佐野市など4自治体を新制度から除外する強硬措置に出た。泉佐野市はアマゾンギフト券などを返礼品に人気を集め、497億円もの寄付を集めていた。除外措置が不当だとして泉佐野市は訴訟を起こし、最高裁で勝訴。新制度に復帰するというすったもんだを演じた。

大阪府泉佐野市のふるさと納税新制度への復帰決定を受け、記者会見する千代松大耕市長=2020年7月3日、同市 – 写真=時事通信フォト
総務省が「ふるさと納税」で“成果”を上げた自治体を目の敵にしたのは、地方交付税交付金制度に風穴を開けかねないと感じたからだ。地方交付税交付金は、国が地方自治体の財政力に応じて分配支給するもので、その分配権限は総務省が握っている。自治体の生殺与奪の権限を総務省が握っていると言っても過言ではない。言うことを聞かない泉佐野市の交付税を大幅に減額したのが端的な例だ。
「返礼品のない寄付」をする人が増えている
せっかく平等に税金を配ろうとしているのに、ふるさと納税で大きな収入を稼ぐところが出てきては制度の根幹に関わる、というのが総務省の正直なところだ。実際、地域の住民税収よりふるさと納税の収入の方が多い自治体がいくつも誕生している。
だが、制度の見直しでふるさと納税人気が鎮静化すると見た総務省の思惑は外れる。2020年度に再び「ふるさと納税額」が大きく増えたからだ。「返礼品競争ばかりが強調されますが、災害復旧などで、返礼品のない純粋な寄付も増えています」とNPOの責任者は語る。本当の意味で地域を応援しようという人たちが増えてきたというのだ。また、地域の魅力をアピールする自治体の努力も実ってきている。寄付した金額の使い途を指定できる自治体も大きく増えている。
大きく増えてきた「ふるさと納税」だが、残念ながら自治体が「自立」の道を探るほどの収入源にはまだまだなっていない。相変わらず国から配られる地方交付税交付金が自治体の大きな収入になっている。「国頼み」から脱却できる状況ではないのだ。
財政的に自立できる自治体が大きく減っている
2021年度の地方交付税交付金の総額は16兆3921億円。それに比べれば、ふるさと納税の6724億円は微々たる金額だ。しかも、2018年には15兆円あまりにまで減少していた地方交付税交付金は3年連続で増額となり、2021年度は新型コロナ対策の名目で5%以上増えた。自治体財政の国依存はむしろ急速に高まっているのである。
ちなみに、地方交付税交付金をもらっていないのは47都道府県では東京都のみ。1718ある市町村のうちもらっていない「不交付団体」は53しかない。2007年には142あったから、数で見ても財政的に自立できている自治体は大きく減っている。

※写真はイメージです – 写真=iStock.com/metamorworks
ふるさと納税制度の導入を決めた第一次安倍内閣では「三位一体の改革」が方針として掲げられ、国庫補助負担金改革、税源移譲、地方交付税の見直しを一体的に行うとされた。だが、最近はすっかり死語になり、地方への権限移譲、税源移譲はまったく議論に上らなくなった。「地方にできることは地方に」という掛け声もまったく聞かれない。むしろ国におんぶにだっこの自治体が増えつつある。
「地方を抱え込む余裕」は国にはない
総務省など霞が関の役人からすれば、権限を地方に移せば、自分たちの仕事が減り、権限を失うことになる。だから、地方分権には取り組まず、自治体を自立できないようにする方向へと進んでいく。
だが、国の財政が隆々としているならともかく、国自身も財政難に喘いでいるのが実態だ。いわゆる「国の借金(国債、借入金、政府保証債務の合計)」は1200兆円を突破している。つまり地方を抱え込む余裕は国にはないはずなのだ。
地方交付税交付金制度は、財政状態が悪くなれば、国が手当てをしてくれるわけで、財政を立て直すインセンティブが働かない。つまり、多くの自治体が国に頼ることばかりを考え、自立しようとは思わないのだ。
「いやいや財政的に自立なんて到底無理です」と真顔で答える首長は少なくない。国の公共事業を頼りに、国会議員に陳情する仕組みは今も変わっていない。
ふるさと納税が、自治体の「自立心」を高めた効果はあるだろう。だが、地方交付税交付金の巨大さに効果を削がれていると言っても過言ではない。地方を再編して一定規模にまとめる「道州制」の議論もいつの間にか雲散霧消した。このままでは、人口減少で税収が減る自治体が続出し、国が支えられなければバタバタと破綻していくところが増えていくことになりかねない。自治体の財政が詰まれば、住民生活を根底から揺さぶることになる。
———-
磯山 友幸(いそやま・ともゆき)
経済ジャーナリスト
千葉商科大学教授。1962年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。日本経済新聞で証券部記者、同部次長、チューリヒ支局長、フランクフルト支局長、「日経ビジネス」副編集長・編集委員などを務め、2011年に退社、独立。著書に『国際会計基準戦争 完結編』(日経BP社)、共著に『株主の反乱』(日本経済新聞社)などがある。
———-
(経済ジャーナリスト 磯山 友幸)