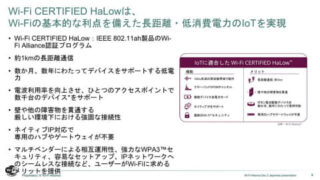様々な業界で進んでいるデジタルトランスフォーメーション(DX)だが、その進み方や内容は会社やよってかなり異なる。そうした中、特色あるDXを進めているのが、コンテンツ産業の雄であるKADOKAWAグループだ。同グループでは、グループのDXを推進し、そのノウハウを社外にも展開していく子会社「KADOKAWA connected」を設立。社内外あわせた「コンテンツ産業のDX」を推進している。そこで今回は、同社でDXを推進する塚本 圭一郎より、「DXは魅力的なコンテンツ作りにどう貢献するか」をテーマに寄稿いただいた。(編集部)
私は、KADOKAWAグループのDX推進を行う子会社、KADOKAWA connected(以下、KDX)のChief Data Officer(CDO)として、 グループ全体のデータマネジメントを担う仕事をしています。
KADOKAWAと聞くと「出版社がなぜDX?」と思うかもしれません。この連載では、KADOKAWAグループのDXの取り組みを通じて、コンテンツ創出においてDXが果たす役割や、これまでデジタルとは無縁だった企業にとってもDXが大きなメリットになることをお伝えしていきたいと思います。
ビッグデータの活用でニコニコチャンネルの会員数増加に貢献
2014年にKADOKAWAとドワンゴが経営統合した時から、グループとしてのシナジーを生み出すための模索が始まりました。
KDXは、グループシナジーをデジタルの側面から活性化させるために、2019年に設立されました。その目的は、インフラ開発・運用や、ICTコンサルティング、システムの設計・構築・運用、クラウドサービス、ビッグデータサービス、働き方改革支援など多岐にわたるDXの推進です。
現在、私が部長を務めるIntegrated Data Service部(以下、IDS部)は、KDXの一部門としてKADOKAWAグループ全体にデータ活用のサービスを提供しています。KDXはドワンゴとKADOKAWAの二社からDXに関連する人員が集結して設立されているのですが、IDS部のルーツは、ドワンゴです。ドワンゴ時代は、ニコニコ事業のチームの中で、ビッグデータサービスを提供していました。
ドワンゴでは、ニコニコ動画やニコニコ生放送などのサービスから生み出されるデータをデータ分析基盤に収集し、そのデータを事業部門がセルフサービスで可視化したり分析できる環境を構築しました。また、そのために必要な講習も社員に行いました。今では、社内でダッシュボード(データを視覚化して確認できるツール)を使って毎週KPIの報告を行い、それに基づいて会議が進む状況が当たり前になっています。この状態をKADOKAWAグループ全体に広げ、普段からデータを活用して仕事をできる環境の構築を目指しています。
データを活用することで、実際にどんなメリットが得られるのでしょうか? 例えばドワンゴのニコニコチャンネルでは、さまざまなファンクラブによってチャンネルが運営されています。ファンクラブを主催するオーナーが気になるのは、そのチャンネルに入会したユーザーの目的や、どうすれば入会を継続してもらえるかということです。
そこで、私たちがデータを収集・分析して可視化したダッシュボードを見られるようにしたことで、データの裏付けによってどんなコンテンツが支持されているかがわかり、入会目的が可視化され、入会の増加や継続につながるような新たなコンテンツづくりに活かせるようになりました。その結果、ニコニコチャンネルの会員数を現在まで継続的に増やすことができています。
社員は「何から始めればいいのかわからない」そこに寄り添い、どんな質問にも応える
ドワンゴには元々ITリテラシーの高い企画職やエンジニアがいますので、私たちがシステムを提供しさえすればデータ活用をスムーズに進めることができました。
しかし、KADOKAWAグループ全体を見ると、事業によってITリテラシーが異なり、これまでデジタル技術を頻繁に使用してこなかった事業だと「DXやデータ活用といっても、何から始めたらいいのかわからない」というKADOKAWAグループの社員も存在します。そこでIDS部では、データ活用で困っていることがあれば、どんなことでも相談してもらえれば対応できるチーム体制を構築しました。
DXのサービスでよく見られるのは、コンサルタントはこちらのニーズを聞いて企画をうまくまとめてくれるのですが、開発自体は別のベンダーが行い、システムが出来上がると、今度はさらに別の会社が運用する、というパターンです。このように複数の事業者をコントロールするには、ある程度DXの知識を持っていないと難しいでしょう。
そこで私たちは、ビッグデータを分析したり、機械学習を実行するようなシステム開発から、「顧客」となるKADOKAWAグループの社員がかかわるビジネス課題をヒアリングするコンサルティングまで、一気通貫で対応できる体制を取ることによって、「顧客」に寄り添い、どんな相談にも応えられるようにしています。
ただ、私たちが全てお任せで相談を引き受けていると、私たちの仕事が肥大化してしまいます。そこで、KADOKAWAグループの社員のデータ活用スキルを向上させるための講習プログラムも提供しています。システムの使い方の理解度を高めることで、顧客自らがデータ活用の目的を意識した上で、データの収集、分析ができるようになるという、セルフサービス化へと徐々に近づけるような支援活動をしています。
また、依頼を受けた案件には、KADOKAWAグループのデジタルビジネスを推進する部門と連携し、役割分担をして対応するようにしています。もし私たちだけで対応しようとすると、グループとしての全体最適から外れてしまう可能性があるからです。例えば、グループ内から「デジタルマーケティング施策をやりたい」という依頼があった際には、マーケティング施策についてはデジタルビジネス部門にお願いし、私たちはエンジニアリングを受け持つことで、うまく施策を打つことができました。こうした連携を取ることによって、相談する側は一度の相談で済ませることができ、私たちは全体最適を前提としながら個別の課題に対応することができます。
データ活用の4段階、「何が起きたか」「なぜ起きたか?」「何が起きるか?」「何をすべきか?」今は「何が起きたか」=可視化のニーズが高まる
KADOKAWAグループ全体に関わる取り組みとしては、データ分析基盤「Trinity(トリニティ)」(グループ内のコードネーム)が挙げられます。
会社や事業が分かれていると、システムも分かれていることが多いものですが、グループシナジーを生み出そうとした場合、ちょっとしたデータの連携にもかなりの手間がかかります。そこで、グループ内で共有・利用できるデータ分析基盤を構築しました。Trinityを利用することで、会社をまたがる事業におけるデータ連携がしやすくなり、複数の会社をまたぐことが多いメディアミックスを進めていく上でデータがますます活用しやすくなると考えています。
「AIや機械学習を利用したい」というニーズは多くありますが、データ活用は段階を踏んで行う必要があります。IT分野のリサーチで知られるガートナー社は、データの分析を4つの段階に分類しています。
▼記述的: 何が起きたか
▼診断的: なぜ起きたか?
▼予測的: 何が起きるか?
▼処方的: 何をすべきか?
第1段階(記述的)は、現状がどうなっているかを把握すること。そのためには、データを可視化することが必要です。第2段階(診断的)は、可視化されたデータを見て、なぜこの数値が上がり、あるいは下がっているのか、その原因を究明するデータサイエンスです。そして、原因がわかった上で行うのが、第3段階となる未来の予測です。最終の第4段階は、予測された結果をもとに行うべきアクションをAIが示してくれるというものです。
現在は、データ活用の第1段階であるデータの可視化が最も盛んな時期だと思います。
これまでずっと表計算ソフトで集計してきたことを、手作業なしでも見られるようにすることへのニーズが増えているのです。私たちが受ける依頼でも、データを可視化するダッシュボードに関する内容が多くなっています。今後は、徐々にデータサイエンスによる分析や予測のニーズが高まっていくと見ています。KADOKAWAグループでも現在、売れ行き予測を見られるようにするための機械学習を進めています。
無駄な機械学習で「PoC貧乏」にならないために
データ活用、特に機械学習の分野において今、問題になっているのが「PoC貧乏」です。
PoC(Proof of Concept:概念実証)とは、機械学習の場合、新しいモデルが高い精度が得られるかどうかを検証することです。顧客は機械学習に対して100%や95%といった高い精度を求めがちですが、機械学習で95%の精度ということはほとんどありません。
そのため、高い精度を前提とした機械学習プロジェクトの場合、そこまで精度が上がらずに行き詰まってしまうことがよくあります。そうすると、データサイエンティストはコストが高いですから、コストばかりかかって期待した成果が得られず、「PoC貧乏」になってしまう、というわけです。
そこで、機械学習を行う場合は、その特性を踏まえて、どうすれば使えるかを顧客と一緒に考えることが、データサイエンティストにとって重要な役割になっています。
例えば、本の売上を予測する場合、ジャンルによって顧客層が異なるため、予測精度は変わってきます。それを無視して、全てのジャンルの売上を機械学習によって予測しようとすると、正確な予測が一向にできないことになってしまいます。
しかし、高精度で予想できる特定のジャンルが見つかれば、その部分だけは機械に任せて、他のジャンルにより多くの時間を割くことで、人力による売上予測の精度を高めることができるかもしれません。
一般に、機械学習モデルの開発を請け負ったデータサイエンティストが、このようなビジネスプロセスの改善まで含めた提案を行うのは、なかなか難しい面があります。その点、KDXはKADOKAWAグループの子会社として、事業に貢献することが求められているため、業務改善の領域にまで入り込んで、事業部門と一緒に改善に取り組むことができます。そこにこそ、グループ子会社としての私たちの価値があると考えています。