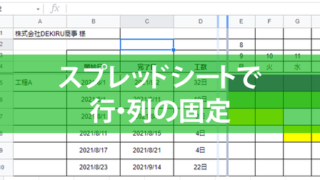新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックのなかで、「共感」や「共感性の高い上司」が好意的に取り上げられるようになった。なにしろ我々は、生涯で経験するなかで最悪の、グローバルな公衆衛生危機に直面しているのだ。こんなときに、理解と思いやりを示してくれる上司を望まない人なんているだろうか?
驚くにはあたらないが、ほとんどの人は上司に共感を望んでいることが、会計会社EYの最新調査で判明した。心ある上司の存在は、社員の幸福や生産性の向上につながるだけでなく、大量離職を食い止めるのにも役立つ可能性がある。
米国の労働者1000人以上を対象とした、EYの「ビジネスにおける共感性調査(Empathy in Business Survey)」では、90%の回答者が、共感性のあるリーダーが仕事の満足度の上昇につながると答え、さらに79%が離職率を下げると答えた。
Advertisement
雇用者にとっての朗報はこれだけではない。回答者の圧倒的多数(85%)が、共感性の高い上司の存在は社員の生産性を高めると考えていた。
顧客のごとく従業員を扱うべき?
「もう何年も、『雇用者は従業員を顧客のように扱うべきだ』という意見を耳にしてきた」と、グローバルPR企業エデルマン(Edelman)の社員体験担当グローバルチェアを務めるシンディ・ローチ氏はいう。「共感をもって顧客の感情に耳を傾けることは、顧客の信頼とロイヤルティを勝ち取ろうとする企業にとっては通常業務のひとつだ。このような共感を(部下に対しても)実践し、誠実に話を聞く雇用者は、従業員の感情を認識し、それを社員体験に取り入れることで、成功のために必要なタレントを獲得し維持できる見込みがより大きくなるだろう」。
広告は、こうした共感が必要とされている業界のひとつであると、ニューヨークのエージェンシー「テリー&サンディ(Terri & Sandy)」の共同創業者、サンディ・グリーンバーグ氏は指摘する。士気の低下、社内政治、長時間労働、社員の感情の無視といった、業界に蔓延する問題の解決のため、同氏はパートナーのテリー・メイヤー氏とともにエージェンシーを立ち上げ、ディズニー(Disney)やキーブラー(Keebler)などのブランドと仕事をしてきた。「我々は、ただ社員を『大切に考えている』というだけでなく、本当に大切にする会社をつくりあげた」と、グリーンバーグ氏は語る。
たとえば、社員一人ひとりが不可欠な役割を担う小規模エージェンシーでありながら、テリー&サンディでは、社員が家族の看病や自身のメンタルヘルスのために有給休暇を取れるよう最大限の努力がなされている。こうした場合、フリーランサーを臨時雇用することになるため、収益に影響はあるとグリーンバーグ氏は認める。しかし、そうするメリットは、デメリットをはるかに上回るという。たとえば、業界に蔓延する高い離職率は、同社には無縁だ。
共感を信用できるかは別問題
だが、誰もが共感性の高いボスを求めているのは確かだとしても、上司が示す共感を信用できるかどうかは別問題だ。
EYの調査の回答者たちは、上司の共感性を重視する一方で、約半数(46%)が、社員に対して共感をもとうとする企業の努力を見せかけだと感じていた。同様に、調査対象の社員の42%は、会社がこうした約束を守っていないと回答した。
こうした問題の解決策は、単純に管理職が有言実行することだと、多くの経営者たちが述べている。
「言動の不一致があると、社員は当然ながらそれに気づき、批判する」と、ピーポッド(Peapod)やDKNYをクライアントにもつニューヨークのエージェンシー、ジャニュアリーデジタル(January Digital)で最高人事責任者を務めるサラ・エンゲル氏はいう。「これまでよく目にした例は、あらゆる方針を定めて、あらゆる行動規範を書面にして、このうえなく積極性を示している会社であっても、管理職や経営幹部たち自身は企業が掲げる共感性に合致した行動を示しておらず、信頼があっという間に崩壊してしまう、といったものだ」。
メンタルヘルスデーなど、会社が吹聴しがちな福利厚生は、社員の目には表層的で問題の核心を突いていない解決策と映っていると、エイミー・スモール氏も指摘する。スモール氏は、パーキンソン財団(Parkinson’s Foundation)やナショナルパークトラスト(National Park Trust)などの非営利団体との仕事を手がけるサンフランシスコのエージェンシー、メディアコーズ(Media Cause)で、クリエイティブおよびブランド担当エグゼクティブバイスプレジデントを務めている。「社員からみれば、上司はもっと積極的な対策を講じ、そもそもメンタルヘルスデーが必要になるほど事態が悪化しないようにすべきだ」と、同氏はいう。「雇用者は、予防的・積極的リソースと、治療的・支援的リソースの違いを理解し、企業カルチャーのなかでどちらも必須であることを強調すべきだ」。
上司たちだって手探り状態
ボスがどれだけ共感をもとうと思っていても、生活のすべて(管理職の生活も含め)を大混乱に陥れたパンデミックによって、上司がいつでもすべての社員に求めるものを提供することができないような環境が形成されてしまった、という意見もある。
社員の心配事に耳を傾ける管理職の重要さを強調しつつ、「残念ながら、この2年間、地図のない場所を旅してきたのは、雇用者も従業員も同じなのだ」と、グローバルメディアエージェンシー、マインドシェア(Mindshare)で米国担当最高顧客責任者を務めるダニエル・コッファー氏はいう。「どんな業界の社員でも、まだ方針が揺れている状態で具体的な答えが得られないと、不満がたまるのは理解できる。従業員ははっきりした答えを求めるが、雇用者はこの不確実な世界を手探りで進んでいる最中なのだ」。
「すべては真正性、リアルに感じられるかどうかの問題だ」と、製薬会社UCBの米国部門インサイト・トゥ・インパクト担当責任者キム・モーラン氏はいう。「上司が自分と同じ行動をしているところを見れば、部下は自分の現実や弱みについて相談しやすくなる」。たとえば、子どもが病気になって一睡もできなかったと、上司のほうから打ち明ければ、部下たちは朝のミーティングで上司がぼんやりしていた理由がわかる、といった具合だ。
「共感は人事だけの問題ではない。企業が日常業務のなかで推進していくべき、カルチャーの転換なのだ」と、モーラン氏は話す。
一方、やりすぎる上司もいる
上司にとって、「Zoom画面の向こうに人がいる」ことを理解するのは重要だが、共感に関して多くの管理職はかなり努力していて、場合によってはやりすぎている。そう指摘するのは、Googleやフリトレー(Frito-Lay)を顧客にもつロサンゼルスのデジタルエージェンシー、ウィルドビースト(Wildebeest)の共同創業者でマネージングパートナーを務めるラン・クレイクラフト氏だ。
パンデミックのあいだに同社で制度化された、2週間に1度の上司と部下の面談は、部下がふだん考えていることを上司に話す機会になっただけでなく、上司にとっても悩みを打ち明ける場になったと、同氏はいう。「共感は双方向にはたらく。測定するデータが増えていくのにつれて、共感性を高めようという取り組みの一部は、過剰対応だと判明するかもしれない。最適水準は、そのあいだのどこかにあるのだ」と、クレイクラフト氏は述べた。
[原文:Why empathy works: We love bosses who care, but why do so many of us doubt their sincerity?]
TONY CASE(翻訳:的場知之/ガリレオ、編集:長田真)