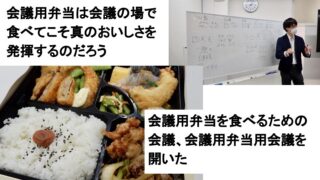NiseriN/iStock
コロナウイルスの感染急減の仕組みを「ガラクタウイルス」と「RNAi」の2つの仮説で説明します。
前置き①
説明の前に、コロナウイルスについて、仮説に関連する事項について簡単に説明します。
ウイルスは外被の中に+鎖のRNAを持っています。ヒト細胞に感染すると、+鎖RNAを細胞内に注入、+鎖RNAの情報を基に、ヒトの酵素合成システムを利用して、RNA複製酵素を作ります。この酵素は+鎖RNAと対応する – 鎖RNAを合成し、一時的に2本鎖状態のRNAを作ります。そして2本鎖RNAの中の – 鎖RNAを参考にして、+鎖RNAを大量に作ります。RNA複製酵素は短いRNAも何種類か合成、ウイルス外被を含む各種部品タンパク質を合成します。
最後に、ウイルス外被タンパク質は、+鎖RNAをそれぞれ1本取り込み、成熟ウイルスを作ります。細胞外に放出されたウイルスは、近接の未感染ヒト細胞に再感染、同様のサイクルを繰り返すことになります。
前置き②
もう一点この話で理解していただきたいことは、コロナウイルスRNAには、多数の突然変異が蓄積されていると言うことです。
デルタ株を例に取ると、ウイルス感染にかかわるスパイクタンパク質遺伝子に限って、約10ヶ月で13個の塩基置換型突然変異の蓄積が指摘されています(米国微生物学会、2021年7月)。
1273アミノ酸で構成されるタンパク質であることを考えると、30000塩基の長さのコロナウイルスRNA全体では、概算として120〜150個の突然変異が蓄積されていると考えられます。突然変異の蓄積は、コロナウイルスを強毒へと導くことはほぼ無い、むしろ脆弱へと導きます。
仮説その①
「ガラクタ(junk)ウイルス」モデル。コロナウイルスは宿主細胞に感染、100倍量以上の子供ウイルスを放出、隣接細胞に再感染のサイクルを繰り返すと前置きで説明しました。
この部分をもう少し丁寧に言うと、自然界での感染サイクルにおいても、正常ウイルス粒子と共に、ほんの少しのガラクタウイルス粒子も同時に作られていることが解っています。インフルエンザ感染細胞ではよく知られた事実です。
ガラクタウイルスというのは、正常ウイルス外被の中に機能喪失のガラクタRNAが取り込まれたウイルスのことです。生成の仕組みを説明します。感染に関して正常なデルタ株RNAがヒト細胞に感染します。複製を繰り返して+鎖RNAを作るのですが、この時、正常RNAのほかに、低い確率ではあるが、複製の間違いで、切れたRNAとか、大きな突然変異が挿入されたRNAなど、多種の「ガラクタ」RNAも作られます。
正常デルタ株RNAから作られた外被タンパク質は、正常RNAを取り込み、正常なデルタ株を作るほかに、ガラクタRNAも全く同様に取り込み、結果としてガラクタウイルスを作ります。中身は異常であるが、外身は全く正常なウイルスです。
パンデミックが最大になるような時季、変異が蓄積したRNAを基質に複製すると、中身がガラクタのウイルスが大量にできると言うことです。このようにしてできたウイルス集団は、隣接する未感染ヒト細胞に感染しますが、もしガラクタウイルスが過剰にあると、隣接細胞の受容体が外身は正常なガラクタに先に占拠されてしまいます。すなわち、感染機会を逃した正常ウイルスは死滅してゆくことになります。陣取り合戦に負けたと言うことです。そして、デルタ株は消えて行きます。
パンデミック後期の変異蓄積RNAは初期のきれいなRNAに比べて脆弱で、ガラクタを作る割合も増え、2ヶ月、3ヶ月と感染を繰り返すうちに、作られる子供ウイルスの中に占めるガラクタ頻度は上昇すると予想されます。ウイルス感染の期間が長引くにつれて、ウイルスRNA中の突然変異数も増え、ガラクタRNAが作られる割合も増え、結果として、ガラクタウイルスの存在比が増えると言うことです。
仮説その②
「RNAi」モデル。ガラクタよりはタイトルだけではあるがかなり洗練された仮説ではあります。
前置き1で述べたように、コロナは感染すると、ヒト細胞内で複製して2本鎖RNAを作ります。すると、ヒトを含めたほとんど全ての生物で見られる現象ではありますが、Dicerと言う名前のRNA分解酵素が結合し、おおよそ20塩基長の小さな断片に分解します。小断片中の一方のRNA鎖は、Argonauteと言うタンパク質を中心とする集合体と結合し、RISC複合体を形成します。小RNA断片を含むRISCは全長のウイルスRNAに結合し、ウイルスRNAを分解します。
この現象をRNAi (interference)と言い、ウイルスに対する防御システムとして知られています。RNAiに対して、ウイルスの側は、RNAi抑制(suppressor)タンパク質を保持して対抗しています。つまり、ウイルス感染というのは、RNAiとRNAi抑制とのせめぎ合いと言うことになります。
RNAiのシステムは実際にヒト細胞で機能しているのでしょうか。このシステムは、線虫やショウジョウバエの世界ではよく知られており、人にも備わっているシステムです。ウイルスRNAi抑制もきちんと機能していると思われます。なぜならRNAiが働くヒト細胞でも、コロナの感染は成立するからです。
とは言え、コロナウイルスRNAi抑制の実体は今現在不明です。研究進行中の分野です。RNAi抑制タンパク質を仮定すると、パンデミック最盛期のウイルスRNAは前置き2で述べたように、突然変異が蓄積、抑制タンパク質の活性も徐々に低下していると考えられます。あるレベルの突然変異蓄積で、RNAiの攻撃が抑制の防御に勝る状況となり、感染の波が沈静化します。つまり、デルタ株は死滅したわけです。
ここで述べた2つのモデルは、例えば、100年前に忽然と消えていったスペイン風邪ウイルスの消長を説明する事もできます。あるいは、今は誰一人話題にもしない2019年12月の武漢での最初の発病にかかわったコロナウイルスの行方を説明することも可能です。アルファー型コロナやベータ型コロナの減少も同じ仕組みかも知れません。
まとめます。
パンデミックのひと山約3ヶ月の間にRNA内部に多数の突然変異が蓄積しました。
その結果、
- 不完全なRNAを持つ、しかし外身が正常なガラクタのウイルスが大量にでき、正常ウイルスの感染を阻害した。感染できないデルタ株は死んでいった。
- ウイルスのRNAi抑制の効果が薄れ、ヒトRNAiのシステムに抵抗できなくなってデルタ株は死滅した。
■
山本 和生
大学 元教授
突然変異の生成機構を、PCR等を用いて解明する研究を行った。