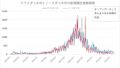映画「サマーフィルムにのって」――、時代劇マニアの女子高生が時代劇映画の撮影にひと夏をかける青春映画、という情報に吸い寄せられて、8月6日の公開初日、グランドシネマサンシャイン池袋へ向かった。
正午を回ったばかりの池袋はほぼ垂直の陽射し。この日、豊島区の最高気温は35℃。東口からサンシャイン方面に向かう道は、降りそそぐ、照り返す、全方位が熱。中年には歩くだけで罰ゲームの路上になっていた。太陽の角度に削られたわずかな日陰に飛び込みながら小走りで映画館へ。

映画「サマーフィルムにのって」
だが、この映画を観終えた帰り道は、陽射しの真ん中を歩く自分がいた。カラダの内にそれ以上の熱がこもった。そういう映画だった。まずは概要を公式サイトから――、
< 映画「サマーフィルムにのって」公式サイトより STORY >
時代劇オタクの女子高生監督が主役に抜擢したのはタイムトラベラー!?
勝新を敬愛する高校3年生のハダシ。
キラキラ恋愛映画ばかりの映画部では、撮りたい時代劇を作れずにくすぶっていた。
そんなある日、彼女の前に現れたのは武士役にぴったりな凛太郎。
すぐさま個性豊かな仲間を集め出したハダシは、
「打倒ラブコメ!」を掲げ文化祭でのゲリラ上映を目指すことに。
青春全てをかけた映画作りの中で、ハダシは凛太郎へほのかな恋心を抱き始めるが、
彼には未来からやってきたタイムトラベラーだという秘密があった――。映画『サマーフィルムにのって』公式サイト|2021年8月6日(金)より新宿武蔵野館、渋谷ホワイトシネクイントほか全国公開 (phantom-film.com)
現実離れした主人公を「あり」にした元乃木坂・伊藤万理華の少年性

BLOGOS編集部
主人公で映画部の女子高生ハダシは、祖母の影響で古き良き時代劇映画にハマり「勝新が尊すぎて」と勝新太郎を最上級でリスペクトし、過去の名画に囲まれながら、阪東妻三郎、長谷川一夫、三船敏郎など、思いあふれてその名を口にする高校3年生。
この「時代劇が好きすぎる女子高生」「自分で時代劇映画を撮りたいと思っている女子高生」というのは、現実にはいそうにない、かなりの変人設定であり、監督・脚本の松本壮史と脚本の三浦直之が考案した「もしもこんな女子高生がいたら」の夢想設定だ。
だが、その夢想にリアリティをもたらし、ハダシという少女を主演女優の伊藤万理華が「あり」にしてみせた。
ちなみに自分はこの映画を観終えてパンフを開くまで、伊藤万理華という人がどういう人か知らなかった。ああなるほど、元乃木坂46の人なのか・・・という具合で。御勘弁。だから映画が始まり、ゴムボールのような頬をした丸顔で、周りと比べてもひときわ小粒な少女が、主役をどう担うのかまっさらに眺めていたのだが、ハダシが映画撮影に乗り出し七転八倒しながら監督としてチームを引っ張り始める頃、主役の磁力がぐいぐい増していくのを感じた。
ハダシというキャラクターはどう見ても難しい。何しろ高校3年生の女子で、時代劇オタクで、勝新リスペクトで、自ら書いた脚本を推敲しながら演出して映画を撮るのだ。現実離れしたキャラ。説得力に欠ければ上滑りになりかねない。思いだけで演じられるような役ではない。面倒な役柄だ。
この面倒な役を伊藤万理華が「あり」にしてみせたカギは伊藤が全身で持ち合わせる少年性だ。小柄な体躯は少年に通じ、ボーイッシュなショートカットがその要素を高め、土手で棒切れを振り回し勝新をマネる姿は少女だが少年だった。この伊藤の纏う少年性が、時代劇に夢中な女子高生というあり得ないキャラクターの説得力を大いに補完していた。伊藤万理華にこの役をあてたキャスティングに感心する。
加えて、伊藤万理華の芝居も魅力的で、サブカル愛が強すぎて恋愛経験希薄な女子がリアル恋愛話を受け止めきれない表情や、女子っぽさが枯渇しきった歩き方などはツボを突く可笑しさで、ハダシというキャラを身近に感じさせてくれた。
松本壮史監督「ラストシーンのための映画」
ハダシを囲む周りのキャストも個々に見せ場があり、物語に膨らみをもたらしていた。ハダシの親友であるビート板(河合優実)、ブルーハワイ(祷キララ)はそれぞれの恋愛観で。ハダシとは真逆の存在でライバルに配置されラブコメ映画を監督する花鈴(甲田まひる)は、女子と女子の青春をブーストさせる「いい」場面を重ねていた。
そして、物語のキーマンである凛太郎(金子大地)は、武士に扮した劇中映画で「映え」のギアがグッとレベルアップする存在感を見せ、女子高生が撮る時代劇のクオリティを担保する重役を果たしていた。
片や時代劇、片やSF、過去と未来がうねりながらテンポよく進むストーリー。松本監督いわく、「『ウォーターボーイズ』の尺が91分なんですけど、あのスピード感をかなり参考にしましたね」と言うとおり全体で97分が心地いい。
ネタバレ回避だが、「サマーフィルムにのって」はラストシーンで、全世代を問わず問答無用で、最高に針が振りきれる。青春の胸アツと時代劇の緊迫が交錯し、まばたきを許さず息が止まる悶絶ラスト。
松本監督は「ラストシーンのための映画」であると発言しているが、まさしく(!)だった。
昭和を知る世代のほうが世界観を深く楽しめる

映画「サマーフィルムにのって」
改めて、主人公のハダシが勝新太郎をリスペクトしている設定を筆頭に、この「サマーフィルムにのって」は様々な先人や名作へのリスペクトが散りばめられて劇中に固有名詞が飛び交う。それ以外にも、連想を掻き立てられる過去作があれこれと頭に浮かび、あの映画を見返したい、あの小説を読み返したい、そんな思いがあふれてくる。
過去へ連想の枝葉が伸びるという点で、青春映画なのに、その同世代たちよりも、それなりに昭和を知る世代のほうが世界観を深く楽しめる作品だったりする。一番古い処で阪東妻三郎だから、それこそ1925年の『雄呂血』あたりからが連想年表の始まりだ。いやはや古い。それもあったので映画好きの70代にさほど迷わず本作を勧めた。
夏があり、ボーイミーツガールがあり、冒険とチャレンジがあり、切ない別れがある――、「サマーフィルムにのって」は、そういう青春映画の様式とか公式をまっすぐに駆け抜けていく。
そして、胸撃つ青春映画に欠かせない最大の要素としてヒロインの無名性もある。見知らぬヒロインとフルスクリーンで出会う、時にそれは未知ゆえの強烈な衝撃をもたらしてくれる。
乃木坂ファンにとって伊藤万理華はメジャーな存在だろうから無名性などと言われたら失礼な話だろう。だが、乃木坂ゼロでこの映画を観た自分にとって、伊藤万理華は突然現れたヒロインであり、そのファーストインパクトはすこぶる痛快だった。
痛快で愉快で、そして爽快。「サマーフィルムにのって」は2021年夏に現れた傑作の青春映画だった。