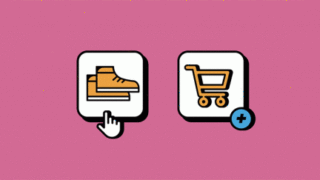「鳥の巣」と呼ばれる中国国家スタジアムを覆い尽くした、北京冬季五輪の開幕を告げる緑と青の光。世界はその美しさに圧倒され、「外交ボイコット」をはじめとした北京冬季五輪を取り巻く論争のことなど忘れてしまったかに見える。しかし外界は今こそ、この背後に隠された政治的な意図を深く考えるべきである。
緑と青の開会式の背後にあるもの
まず、緑と青で見事な統一感を実現した開会式の光景は、総監督を務めた張芸謀氏をはじめとした制作スタッフが広く共有する中国ナショナリズムの信念と、五輪に関する全てを自ら指揮・監督すると称する習近平国家主席の信念が高度に結合したものである。
それは第一に、「緑の水と青い山は金の山、銀の山」という、環境保護をめぐる習近平語録の明確な再現である。習近平はかつて浙江省トップとして「環境保護とエコビジネスに力を入れてこそ健全な経済発展を加速できる。環境破壊の後でいくら金銀を積んでも豊かな環境を買うことはできない」と主張した。これが今や、風力・太陽光発電や電気自動車(EV)の推進などエコビジネスで世界を主導しようとする中国の指導思想となっている。
第二に、この開会式は中国が掲げる「人類運命共同体」の構築に向けた強力なメッセージである。『人民網』に掲載された解説によると、各国代表団の入場行進で掲げられた雪の華をつなげ合わせて最終的に聖火のトーチが差し込まれた巨大な雪の華は、「世界が団結してともに未来に向かう人類命運共同体の構築を体現したものであり、古い文明を誇る中国の《世界大同・天下一家》という人文精神を表現したものである」という。そして「世界は北京冬季五輪を通じて、一つの真実の中国を感じ取り、中国の前進の歩みがさらに自信に満ち、従容たるものであることを感じ取る」よう期待されているという。
なるほど、この雪の華は、中国の聖火を中心に、世界中の国・地域の名前が取り囲むようになっている。「天下」の中心に「正しい」中華の文明を体現した天子=皇帝が君臨し、四方のあらゆる国々の王が恭順を示して朝貢し、皇帝がその誠意を評価して恩恵を加えることで、「天下」の人々は差異を超えて「大同」「一家」の喜びを享受するという、前近代の「中華」中心の世界観を何と巧妙に表現していることか!
五輪を裏で貫くのは黄河が生んだ中華文明
この発想は、「黄河の水、天上より来たる」という紹介のもと氷の立方体が現れ、それが割れる中から「中国北京」という文字が現れたことからも見て取ることができる。
黄河は、皇帝権力による専制の歴史の象徴である。
かつて1989年の六四天安門事件に先立ち、中国は文革の反動と改革開放草創の気風の中で、かつてなく「自由」な議論の時代を迎えていた(共産党体制のもと、完全な自由ではないが、今日と比べれば明らかに自由はあった)。その中では、毛沢東専制を許してしまった中華文明そのものの是非が問われ、中国中央テレビのドキュメンタリー『河殤』(黄河の未成熟な死を意味)は、専制の文明を生んだ黄河も最後は青い海に至り、西側で生まれた自由で開かれた海洋文明に合流するというイメージを提起し、89年の民主化運動を激発した。
中国共産党はそれを戦車で全面的に封殺し、ナショナリズムを徹底的に強調しつつ経済発展を押し進めた結果、今や圧倒的な国力で世界に君臨し、それを可能にさせた黄河文明・中華文明の力を誇っているのが現実である。
黄河の源流がチベット高原から発した時点では、氷のように冷たく青かった流れは、やがて黄土高原を貫く中で、灰色とも茶色ともとれる黄土色に染め上げられ、「中国化」してしまった。そして今実際に、チベットをはじめ多くの少数民族、ならびに多様な文化や思想が「中国化」の圧力にさらされ、「一帯一路」を通じて多くの国が中国に従属させられている。
開会式の「観客」はいったい誰だったのか?
そして今や、その対象は全世界になりつつある。中国は開会式にて、この五輪は疫病の発生以来はじめて予定通り、観客を入れて「正常に」開催される五輪であることを宣言した。中国こそ、いまや東京五輪を開催した日本を歯牙にもかけず、「中華文明の智慧」に基づく管理が世界に正常な秩序をもたらすと言いたいのであろう。
しかしこの「観客」は、自由な意志で集った全世界のスポーツ愛好者ではなく、あくまで中国の党と政府によって組織された特殊な集団に過ぎない。そのことは、中国が包容しようとする、あるいは高く評価する特定の国・地域の入場の時のみ大歓声が響き渡ったことから明らかである。
筆者は少なくとも、中華台北、中国香港、パキスタン、ロシア五輪委員会の入場時に、観客席からの大歓声を聞いた。中国に評価される者、そして従うべき者には恩恵を与え、中国と距離を置く者に対しては冷淡な対応しかしないという、上下関係と差異を専制権力の側が意味づける中華文明のやり方が、疫病下の特殊な状況のもとであからさまに表現されたといえる。