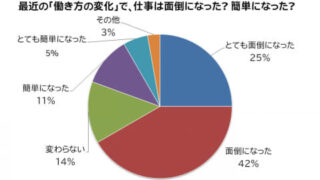南インドで40~50年前まで当たり前に食べられていた雑穀料理をいただきました。
日本でも誰もが毎食白米を食べられるようになる前は、より安価な麦飯や雑穀を食べていたという。同じく米が主食である南インドでも、雑穀を日常食にしていた時代があったそうだ。
そんな時代の食事を再現する会で、今や失われつつある南インドの家庭料理をいただいた。
初めて食べる異国の味ながら、そこには日本人の舌にも伝わる確かな郷愁が存在していた。
南インドの庶民が白米を食べられるようになる前の家庭料理を食べる会
南インドの雑穀家庭料理を特別に作ってくれたのは、祖師ヶ谷大蔵にある「スリマンガラムA/C」のマハリンガムさん。通称マハさん。A/Cはエアコンが効いている店という意味らしい。
マハさんはインド最南端の東側に位置するタミル・ナードゥ州の田舎町が出身で、この店はミールスというお米を中心とした定食や、ティファンと呼ばれる軽食が、現地の味そのままで食べられる貴重な場所だ。ヘルシーなベジ料理だけでなく、酒が欲しくなるノンベジも取り揃えている。
スリマンガラムは元々は経堂にあったが、そちらは2022年9月に閉店し、現在はこの店に注力しているそうだ。



今回の企画者はビリヤニやファルーダの記事で話を伺った、調理器具や食器の輸入販売をしているアジアハンターの小林真樹さんだ。
小林さんは一体どういう意図で、このマニアックな会を開いたのだろうか。
小林:「現在のタミル・ナードゥ州では、どんな場末の安食堂に入っても、ミールスを頼めばおかわり自由の白メシが当たり前に出されます。でも一昔前、農業改革以前の40〜50年前までは、白米は一部のバラモン(司祭階級)、富裕層、米作農家のみが日常的に口にできる贅沢品だったといいます」
――日本と同じく、南インドでも白いご飯が高級品だった時代があるんですね。

小林:「では当時、庶民層は日々何を食べていたのか。タミルの地方出身者に幼少期の家ごはんの記憶を聞くと、たいてい価格の安い雑穀(ミレット)を食べていたという答えが返ってきます」
――雑穀ですか。日本でも昔はヒエやアワやキビを食べていたといいますね。今は健康食品みたいな感じですけど。
小林:「インドでも雑穀はヘルシー志向の人々に見直され、意識の高い都市部のレストランのテーブルに登場する時代ですが、もともとは庶民の間で『安い』という理由で食べられていたんです。
また雑穀は家庭内で食べる粗食料理であり、わざわざ飲食店で食べるようなものではなかったともいいます。あってもラギ・クールの屋台くらい。というか、タミルの田舎には外に食べに行こうにも周囲にレストランそのものが存在しなかった」

小林:「そこで今回は、ただ『安い』から食べていた時代の日常食の中にこそ、リアルなタミルの生活の味があるのではと考え、タミルの地方人であるマハさんに、彼が幼少期に食べていた雑穀料理を忠実に再現して出してもらうこととしました。ヘルシー志向の意識の高いレストラン料理ではなく、まさに家庭の味です」
――和食の鉄人に大根飯と菜っ葉の味噌汁を作ってくれと頼むような話だ。たとえ私がインドに行っても、外食では食べられない料理だから絶対にたどり着けない貴重な味ですね!
これが南インドの雑穀だ
マハさんが作ってくれた料理は、雑穀のお粥と素朴なおかずが数品ずつ。実際の食事ではこんなに品数は並べないそうだが、色々な味を知ってもらうためにと、たくさん用意してくれた。

小林さんから料理名の一覧をいただいたのだが、どれがどれだか全くわからず、対応させるのに苦労した。



現地では味わって食べるタイプの料理ではないのだろうが、それぞれをじっくりと噛みしめて、貴重な味を理解する努力をしていく。
南インドの雑穀料理なんてもちろん初めて食べるのだが、そこには日本人の舌にもその景色が伝わってくるような、確かな郷愁が存在していた。
食べたことがないけど懐かしく思える味、でも明らかに異なる食文化の味付け。これは楽しい体験だ。