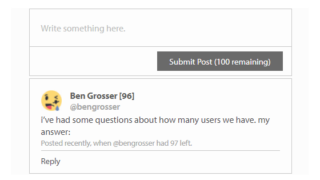日本電信電話株式会社(NTT)、株式会社NTTドコモ、日本電気株式会社(NEC)の3社は10月31日、28GHz帯を用いた分散MIMOにおいて、エリア内の無線伝搬状況や移動端末の位置などの環境情報をシステム自身が把握し、環境に応じて基地局の分散アンテナを動的に切り替える技術の実証実験を実施し、世界で初めて成功したと発表した。
分散MIMO(Distributed Multi-Input Multi-Output)とは、1つの基地局から多数のアンテナをエリア内に分散して配置したうえで、移動端末との間で複数のアンテナによる同時通信を行うこと。アンテナを分散する理由は、28GHz帯の電波が遮蔽物に弱いことにある。
28GHz利用の課題である「遮蔽物による減衰」を克服
高周波数帯である28GHz帯の電波は、遮蔽物による減衰が大きい。そのため、アンテナを分散させ、複数の角度から同時に端末と通信可能にすることで、通信強度を確保しやすくる。また、高周波数帯の電波は距離による減衰も大きく、所要の無線伝送距離を確保するには、アンテナの電波放射を特定方向に集中させる必要がある。そのため、環境に応じて分散アンテナを選択する動的な無線伝送制御が必要になる。
無線通信の更なる高速化・大容量化を実現するため、現在の5Gよりもさらに周波数が高いミリ波帯やサブテラヘルツ帯を移動通信に活用することが検討されている。28GHz帯は5Gにも割り当てられている周波数帯だが、前述のように遮蔽物の対策が有効活用のための課題となっていた。
遮蔽物を回避し、端末に向けて電波放射を集中させるには、GPSやカメラで得られる情報を利用して移動端末の位置を推定する方法もあるが、これらの方法では外部システムに依存した運用となる。そこで、システム内の情報だけで、遮蔽物による通信切断に対し、適切な分散アンテナを選択できる技術が求められていたという。
遮蔽物による受信強度低下の軽減を確認
この課題に対し、NECは、分散アンテナを活用して分散MIMOシステム自身が移動端末の位置を予測し、適切な分散アンテナを選択する技術を開発した。
具体的には、エリア内の各位置で、各分散アンテナの無線品質を持続的に測定し、最適な分散アンテナを学習しておく。そして、運用時に分散MIMOシステム自身が、各分散アンテナの無線品質を随時観測し、機械学習により移動端末の位置を推定。さらに、過去の移動端末の推定位置から未来の移動を予測し、次の無線品質情報を取得するまでの移動端末の位置と、最適な分散アンテナを予測する。
これにより、現在の無線品質情報から取得した分散アンテナだけでは移動に伴う遮蔽により伝送性能の急な低下や切断の可能性がある場合でも、移動端末の予測位置をもとにして分散アンテナを選択し、無線伝送を継続できるようになる。
3社は6~9月に、次のような実証実験を行った。
広さ25×15m、天井の高さ3.5mで、柱が4本存在する実験室において、移動端末を台車で移動させながら、6本ある分散アンテナごとの無線品質情報を取得し、伝送性能を評価する。
従来の方式では柱で遮蔽される位置の受信強度が平均13dB程度低下した一方で、本技術による移動予測に基づいて分散アンテナを選択した場合は、同じ位置における受信強度の低下を5dB程度に留められ、従来に比べて平均8dB程度改善できたという。このことから、高周波数帯分散MIMOで懸念される瞬断の回避が可能であることを確認でき、移動時でも安定した、高周波数帯を用いた高速大容量通信の実現を期待できるとしている。
人間など「移動する遮蔽物」の影響を予測
関連して、NTTとNTTドコモは、分散MIMOのシステム内で取得可能な無線品質情報から遮蔽物の位置推定を行う無線センシング技術を考案した。これは、人間などの「移動する遮蔽物」の影響を予測し、対応するためのもの。固定された遮蔽物の影響は事前に学習できるが、移動する遮蔽物に対しては、別の方法により検出し、影響を回避する必要がある。
具体的には、次のようなものだ。分散アンテナ間で定期的に取得したCSI(Channel State Information:無線電波チャンネルの応答)から、アンテナ間の相関情報に基づく時系列情報を抽出し、この情報を特徴量とした事前データに基づく機械学習により、遮蔽物の位置を推定する。
前述の実証実験と同じ環境で、人体模型を遮蔽物に見立ててエリア内を移動させ、このセンシング技術の実証実験を行った。NTTによると、高周波数帯分散アンテナの系で、無線端末を搭載しない物体の検出を行う実証実験は世界初だという。
実証実験の結果、人体模型の位置推定誤差は中央値で約0.6m、平均値で約0.9mとなり、分散MIMO自身で、遮蔽物の位置も把握できる可能性が確認できたという。この技術は、高周波数帯分散MIMO伝送を支える環境情報の取得だけでなく、物体検知などのセンシングサービスへの活用も期待できるとしている。
同軸ケーブルによる減衰を回避する「A-RoF」技術も実験
基地局装置とそれぞれ分散アンテナを同軸ケーブルで接続する場合、同軸ケーブルは通過損失が10mあたり数dB以上と大きいため、設置できる範囲に限界があるという。そこで、光回線を使用して、基地局装置からのIF(Intermediate Frequency:中間周波数帯)信号をアナログ信号のまま伝送する「A-RoF(Analog-Radio over Fiber)」技術の活用が検討された。
分散MIMOを実現するには周波数同期用のローカル信号、5G通信のためには下り伝送と上り伝送を時分割で行う「TDD(Time Division Duplex)方式」のための制御信号を、それぞれ基地局装置から各分散アンテナへ、データ信号とともに伝送する必要がある。そのため、ローカル信号、TDD制御信号、データ信号を、シングルモード光ファイバーで伝送するサブキャリア多重伝送方式技術を、NTTとNTTドコモが開発した。
前2つの実証実験と同じ環境を使用し、A-RoFおよびサブキャリア多重伝送方式技術の実証実験も行った。基地局装置から20mの同軸ケーブルおよびA-RoFを介して2本の分散アンテナに接続し、TDD方式を用いて下り方向と上り方向のスループットを同時評価する。NTTによると、高周波数帯分散アンテナの系で、A-RoFを用いた上下双方向無線伝送の実証実験も世界初だという。
結果、A-RoF適用時も同軸ケーブルとほぼ同じスループット特性が維持できており、1波長にデータ信号とローカル信号、TDD制御信号を多重伝送しても、上下方向とも伝送特性が劣化しないことが確認できたとしている。
A-RoFはケーブル長を100~1000mと延長しても、通過損失が0.5dB以下であり、同軸ケーブルと違って、本特性がそのまま維持できることが期待できるという。このことから。ショッピングモールや工場のような大規模屋内環境でも高周波数帯の分散MIMOを適用可能となる可能性が示せたとしている。
これらの技術は、11月16日~18日に開催予定の「NTT R&Dフォーラム Road to IOWN 2022」で紹介される予定だという。
今後について3社は、28GHz帯より高い周波数帯、人体など遮蔽物が変動する環境、多数の移動端末収容下での検証を進め、高周波数帯分散MIMOの適用周波数やユースケースの拡大に向けて、実証実験を引き続き進めとしている。また、無線センシングによる移動端末位置や周辺遮蔽物の自動認識の高度化技術、A-RoF活用による分散アンテナの展開技術の検証も進め、高周波数帯分散MIMOのセンシング活用や、設置運用なども検討するという。