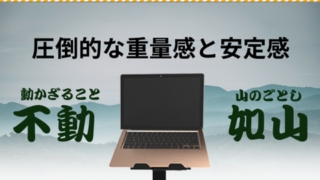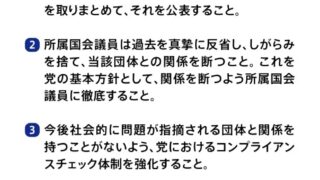日本が台湾を植民地支配した50年は筆舌に尽くしがたく、台湾についてあれこれ言う資格はない。
中国国防省の呉謙報道官は5月26日の定例会見で、自民党青年局の議員団訪台を受け、戦前の日本による台湾統治をこう評した。
日本が台湾を統治していたのは、下関条約で清国から割譲されてから太平洋戦争が終わるまでの半世紀に至る。当時は建国すらしておらず、現在に至るまで台湾を主権下に置いたことのない中華人民共和国にとって、台湾の日本統治は「筆舌に尽くしがたい」もののようだが、当事者の台湾と日本は相互に友好関係を築いている。1月に日本台湾交流協会の台北事務所(日本大使館に相当)が行った調査では、「台湾を除いた、最も好きな国」に過去最高となる60%の台湾住民が「日本」と答えた。

Oleksii Liskonih/iStock
良好な関係が続く日本と台湾だが、一方で台湾の歴史を深く知る日本人は多くない。なおさら日台の歴史的なつながりについては、「知っているようで知らない」方が多いかと思う。
本稿では、太平洋戦争期には日本本土で戦闘機を作り、戦後は日本を「第二の故郷」と慕い現在に至るまで日台交流に尽力してきた「台湾少年工」について、拙著『台湾少年工 戦闘機を作った子どもたち』(日本橋出版)より紹介する。
1944年4月、神奈川県厚木基地の近辺に「高座海軍工廠」が正式に完成した。工場設置は「雷電」など旧日本海軍の戦闘機生産が目的だったが、最大の特徴は主力工員が台湾人少年であることだった。工廠の設置計画が進む1940年ごろには、日本本土の労働力不足が深刻化しており、海軍は日本語ができる台湾の少年たちでその不足を補おうとした。
少年工は、1943年から1944年にかけて複数回に分かれて海軍によって募集された。募集の多くは国民学校や同高等科などの学校を通じたもので、担任教諭などから勧められたという。子どもたちにとって、募集の条件は魅力的だった。「一定の賃金がもらえる上、働きながら工業分野などを学ぶことで、数年後には上級学校の卒業資格も得られる」と聞かされたのだ。向学心があり、日本語ができて優秀な台湾人の少年たちが応募し、難関の試験を通じて選ばれた。
集まった少年の数は計約8千人に及んだ。多くはまだ幼さの残る13~15歳の子どもたちだった。日本本土にいた台湾人の数は、終戦直後の1945年11月で2万5千人ほど。約3分の1が彼ら「台湾少年工」だったことになる。
日本本土に渡った少年工は、高座海軍工廠を中心に名古屋の三菱重工業や群馬県の中島飛行機など全国各地の軍需工場へ派遣され、海軍軍属として働いた。当初は飛行機の生産従事や事務などの仕事以外に、学習の時間も用意されていた。ある少年工の回想によると、「工廠では同じ日本人として扱われ、台湾にいるときよりも台湾人への差別がなかった」と言う。
高座海軍工廠には、東京帝国大学の学生だった三島由紀夫も勤労動員で働いていた。三島は後に小説『仮面の告白』(1949年)で、台湾少年工と自身の交流を述懐している。
部品工場を疎開するための大きな横穴壕を、台湾人の少年工たちと一緒に掘るのだった。この十二三歳の小悪魔どもは私にとってこの上ない友だった。(同作より)
しかし、戦争末期は戦況が悪化し、ほとんどの時間を局地戦闘機「雷電」や「ゼロ戦」などの航空機生産や整備に費やすことになった。空襲の被害を受ける者もいて、名古屋では三菱工場で約25人が犠牲になり、高座海軍工廠周辺でも少年工が6人亡くなった。
1945年8月15日に戦争が終わると、高座海軍工廠でも残務処理が行われ、手続きが終わると日本人の職員たちはそそくさと故郷へ戻っていった。一方で、海の彼方の台湾へ帰れずにいる少年工は、全国の工場から戻ってきた者を含めて、高座海軍工廠に取り残されてしまった。
終戦により、少年工の国籍は「日本」から「中華民国」になり、日本の被支配者から戦勝国の一員へと変身した。日本人職員が去り、管理する者がいなくなった工廠周辺では、解放感や復讐心から戦時中に虐められた日本人へ報復したり、食糧不足から農作物を強奪したりする少年工も出た。
乱れた秩序を回復し、そして自分たちが台湾へ帰る交渉をするために、少年工は「自治会」を結成。自制の甲斐もあり、戦時中から続く地元住民との交流も多くは良好なまま続き、中には風呂を借りたり縫物を手伝ってもらったりした少年工もいた。
少年工は1946年1〜2月に台湾へ戻った。その後は仕事に就いたり、復学したりとそれぞれがそれぞれの人生を歩むことになる。しかし、翌47年には、中国国民党政権による台湾人知識層の虐殺事件「228事件」が発生。台湾は1980年代まで言論が弾圧される暗黒の時代に入る。国民党政権にとって「敵」だった日本で戦闘機を作っていた事実は弾圧の理由になりかねず、多くは少年工として働いた経歴を隠して過ごした。
一方、高座海軍工廠で働いた日本人の中には、少年工への思いを絶やさず抱き続けた者がいた。米軍による空襲で少年工6人が亡くなった時に同工廠で当直職員として働いていた早川金次は、「少年工の霊を慰めたい」と1963年に現場近くの善徳寺境内に慰霊碑を建立。翌64年には日本に住む元少年工を中心に同窓会が発足し、犠牲者の法要を続けた。
1980年代にかけて台湾で言論や集会への抑圧が緩和されると、台湾各地でも同窓組織が作られ、1988年には台湾全体をまとめる台湾高座会が発足した。
戦中は食料難や本土の寒さに苦しんだ少年工だが、多くは当時を恨まず、前向きに振り返った。出身や民族を問わず、同じ方向を向いて働いた日本人との友情。当時最先端だった飛行機を直接自身の手で作っていたという自負。戦後の腐敗した国民党政権との対比・・・。還暦前後の元少年工は、高座海軍工廠があった厚木基地周辺を「第二の故郷」と呼び、懐かしんだ。
台湾高座会はその後毎年大きな大会を開き、1990年代以降は日本を定期的に訪れている。1993年には少年工の第1団の渡日50年周年を記念して、計3千人が参加する大会が神奈川県で開かれ、日本人の関係者とともにかつてを懐かしんだ。
2011年の東日本大震災では多額の義援金を会内で集め、日本へ送った。直近では2018年には平均90歳の少年工20人がはるばる神奈川県を訪れ、関係者との親睦を深め、交流は次世代の子孫たちへと発展を続けている。
8千人もの大勢の植民地の子どもたちが飛行機を作っていた事実は、日本の近現代史でも注目されるべきだ。なおさら、当時は被支配者と支配者の関係にいた彼らと日本人がその後、対等な友人として交流を深めた事実は、現代の殺伐とした国際社会の模範になり得るはずである。
日本と台湾の友情は一朝一夕でできたものではない。台湾少年工をはじめ、両国の複雑な歴史を経て醸成された、深い絆で結ばれたものなのだ。
■
林 篤志(はやし・あつし)
『台湾少年工 戦闘機を作った子どもたち』(日本橋出版)著者。1995年、愛知県生まれ。東京大学文学部卒。在学中に国立台湾大学へ留学した。東洋史学を専修し、特に日本統治時代の台湾について研究。元北海道新聞記者。