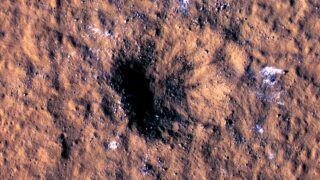コロナ禍は、あらゆる学問の分野に挑戦状を突きつけた。これまで蓄積した知見を総動員して、いま、何が言えるのか。あるいは、これまでのアプローチに欠けていたものは何だったのか。コロナ禍は、歴史学の分野でも、再考を迫っている。
昨年12月、『コロナの時代の歴史学』(績文堂出版)という本が刊行された。歴史学研究会が編集し、16人の歴史家がコロナ禍に向き合って思索を重ねた論文集だ。まだ感染の行方が定まらない時期に企画し、執筆依頼から締め切りまで2か月もない慌ただしさのうちに出版された。長い時間軸を前提に過去を振り返る歴史家たちが、感染が同時進行中のこの時期に、なぜ緊急出版を目指したのか。監修にあたった中澤達哉・早稲田大教授と、三枝暁子・東大准教授のお二人に2021年7月21日、Zoomでお話をうかがった。
歴史家の「当事者性」
歴史学研究会は、1931年2月、東京帝大文学部史学科の若手ら数人が結成した「庚午会」の流れを汲み、翌32年12月に結成された民間学術団体だ。それまでの権威主義的な歴史学に対して進歩的、近代的な立場をとって33年には機関誌「歴史学研究」を刊行。急速に「皇国史観」に染められる学界に対して抵抗した。
1931年9月には満州事変が起こり、国内の言論は急旋回しようとしていた。1935年には、それまで通説だった美濃部達吉の「天皇機関説」に対する排撃が始まり、「国体明徴運動」が盛んになった。東大も国史科の平泉澄らが中心となり、日本思想史講座で「皇国史観」を説くようになる。こうした動きに対し、南原繁は、1939年に法学部内に東洋政治思想史の講座を設け、津田左右吉を講師に招いて抵抗するが、津田の本も発禁処分になり、講座を託そうとした弟子の丸山真男も二度にわたって召集される。歴史学研究会も、44年には活動停止を余儀なくされ、戦後の1946年にようやく活動を再開して今に至る。
2020年5月、歴史学研究会は毎年恒例になっている大会を、コロナ禍で延期せざるを得なかった。これは1944、45年の戦争末期を除けば、90年近い歴研の歴史においても初の出来事だった。
その5月に、新旧四役会議がオンライン方式で開かれ、この本の企画が持ちあがった。コロナ禍であらゆる活動は停滞しつつあったが、「感染症の流行に、ただ影響されているばかりでよいのか。このような状況だからこそ発揮すべき歴研、歴史学の力があるのではないか」という意見が出された。
新年度委員会は、若尾政希委員長、北村暁夫編集長が留任し、本の企画は旧年度事務局長の中澤達哉さん、研究部長の三枝暁子さんに託されることになり、事務局員の増田純江さんの協力も得ながら刊行作業を進めることとなった。それが、この本ができるまでのいきさつである。
もともと2020年度の大会で予定していた全体会のテーマは、「『生きづらさ』の歴史を問う」だった。結局、大会は延期され12月に開かれたが、今回の企画の前提としてあったのは、歴史家が「当事者性」をもって歴史をとらえることの重要性だったという。研究部長だった三枝さんはこう話す。
「非正規雇用の急増や、うつの増加、学生や院生が貸付型の奨学金に頼らなければ学業を続けられないなど、私たちの周りにも、『生きづらさ』は身近に迫っている。歴史学も新自由主義のひずみを問題にし、その起源を探る試みを続けてきましたが、より強い当事者性をもって『生きづらさ』に向き合うべきではないか。そんな問題意識を抱いて大会を準備していたところに、「コロナ禍」が広がった。後から歴史として振り返られる事件に私たちは立ち合っている。歴史家にも、現在をどうとらえるか、という問題が突き付けられている。そうした一種の使命感が芽生えたところに、『こんな時こそ、何かできないか』という執行部の思いが重なり、企画が動き出した。短い時間に完成できたのは、異様な緊張に包まれていたからだと思う」
続けて中澤さんはこう語る。
「今世紀になって、リーマン・ショックや東日本大震災など、後で振り返ると歴史に残る出来事が多く起きた。しかし今度のパンデミックは死者数からいっても、大戦に匹敵する大きな衝撃だった。歴史学は予言の学ではないし、未来を予測することを目的に過去を調べているのでもない。でも、歴史学ほど現状認識とかかわる学問もない。だから、今後の歴史学はどうあるべきか、という点については、同時進行の今においてこそ議論すべきではないか、と思った」