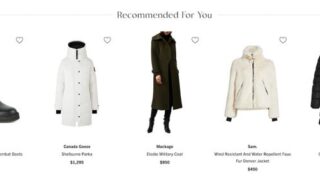ローマ・カトリック教会では8日、「聖母マリアの無原罪のみ宿り」で教会の祝日だ。8月の「聖母マリアの被昇天」と共に、聖母マリアの2大祝日に当たる。

ラファエロ画「大公の聖母」(ウィキペディアより)
「聖母マリアの無原罪の御宿り」の場合、1708年にクレメンス11世(在位1700~21年)が世界の教会で認定し、1854年、ピウス9世(在位1846~78年)によって正式に信仰箇条として宣言された。「マリアは生まれた時から神の恵みで原罪から解放されていた」という教えだ。
キリスト教会はカトリック教会でもプロテスタント系教会でも聖書が聖典だが、その聖書の中には聖母マリアの無原罪誕生に関する聖句は一切記述されていない。新約聖書「テモテへの第1の手紙2章5節には、「神と人間との間の仲保者もただ1人であって、それはキリスト・イエスである」と記されている。聖母マリアを救い主イエスと同列視する教義(無原罪の御宿り)は明らかに聖書の内容とは一致していない。
にもかかわらず、カトリック教会は「聖母マリアの無原罪のみ宿り」を教義とするだけではなく、「聖母マリアの被昇天」と共に聖母マリアを称え、お祝いする。聖母マリアが無原罪で生まれたとすれば、罪なき神の子イエスと同じ立場となり、「第2のキリスト」という信仰告白が生まれてくる一方、キリストの救済使命の価値を薄める危険性が出てくる。だから、中世のトマス・アクィナスらスコラ学者は聖母マリアの無原罪説を否定してきた。
ちなみに、プロテスタント教会や正教会では聖母マリアを「神の子イエスの母親」として尊敬するが、「マリアの処女懐胎」を信じていない。一方、カトリック教国のポーランドでは聖母マリアを“第2のキリスト”と見なすほど聖母マリア信仰が活発だ。ちなみに、マリアは父ヨアキムと母アンナの間に生まれている。
ところで、キリスト信者は何を信じている人々だろうか。創造主としての神を信じ、イエスを救い主と信じ、イエスの十字架救済を信じている人をキリスト者というのだろうか。それではイエスが処女マリアから出生したという話や、十字架の死の3日目後、復活したという話をキリスト信者は本当に信じているのか。多分、多くの信者は信じているのだろう。
カトリック教会はその後、イエスの母親マリアを聖化し、「聖母マリアの被昇天」、「聖母マリアの無原罪のみ宿り」という教義を打ち立て、聖母マリアを第2のキリストの地位まで奉ってきた。キリスト者はこれらの聖母マリア像を本当に信じているのか。多分、多くの信者はそれを信じているのだろう。
世界には13億人以上のカトリック信者が登録されている。幼児洗礼を受けた後、教会の礼拝にはもはや通わなくなった信者も教会に正式に脱会届を提出しない限り、統計上、カトリック信者だ。また、「イエスの復活」を信じていなくても、神父から「あなたはイエスが復活したことを信じていないので教会から出て行ってください」とはいわれない。教義と信仰は常に一つということはないのだ。
はっきりいえば、多くの信者はカトリック教会の教義にあまり関心がない。教義について、ああだこうだという人は聖職者か神学者、それに数少ないが聖書を通じて真理を探究する人々だけだろう。教会の礼拝に規則正しく参加する敬虔な信者は教義にはあまり関心を示さない一方、教会主催の慈善やコンサートなどイベントには小まめに参加する。教会は社交の場となり、サークル、コミュニテイーとなっていく。
一方、非キリスト者や無神論者は、死んだ人間が再び生き返るとか、死後、肉体と共に天国に引き上げられたといった話を聞けば、非科学的なおとぎ話だと冷笑する。ユダヤ教から派生したキリスト者たちは初期教会時代、ユダヤ教のセクトと呼ばれ、中傷、誹謗されてきた。
当方は先日、ドイツのヴェルトの動画「信仰と天文学者」を見た。そこに登場する天文学者の多くは宇宙が整然と存在し、無限の広さと秩序を有していることに驚嘆し、「人類が知っている宇宙は微々たるものに過ぎない」と強調、宇宙は人間の想像を絶したものであるという意味から、「サムシング・グレート」の存在を考えている。多くは神を否定しない。彼らが不可知論者にならないのは、宇宙が余りにも整然とした秩序のもとに存在し、運営されている、という意味から、宇宙の創造者として神なる存在を想定せざるを得ないからだ。
それでは、可能かどうかは別として、人類が宇宙の成立プロセスを完全に理解した暁には、ひょっとしたら「神」という存在は消滅するだろうか。世界的ベストセラー「サピエンス全史」の著者で、“現代の知の巨人”と呼ばれるイスラエルの歴史家、ユバル・ノア・ハラリ氏は、「人類の進化は続いている。科学技術の発展によって、人類は神のような存在に進化していく」という「ホモ・デウス説」を主張している。同氏はエルサレムのヘブライ大学で教鞭をとっている歴史学者だ(「人類は“ホモデウス”に進化できるか」2017年3月26日参考)。
同氏は「人類はある日、神のような存在となる」というが、決して「神を発見する」とか、「神と出会う」とは考えていない。同氏によると、人類は神を創造し、最終的には神になるというのだ。人類が「神のような存在」となることで、有史以来、囁かれてきた「神」がその役割を終え、歴史の舞台から消滅する。同氏は人間至上主義から「データ至上主義」へと歴史が進化していくと考え、生命を「アルゴリズム」とみている。

イスラエルの歴史学者ユバル・ノア・ハラリ氏(同氏の公式サイトから)
話を「8日」に戻す。聖母マリアは無原罪で生まれ、イエスが復活した話は多分、聖書の多くの部分がそうであるように、人類が歴史を通じて語り続けてきた「神話」だろう。神と人間をつなぎ、教義と信仰を結びつけるために、「神話」が必要となる。神話を通じて、人類は神の存在を身近に感じ、個人的、民族的に独自のナラティブ(物語)を綴ってきた。
 興味深い点は、多くのナラティブの中には一定の共通性があることだ。「洪水神話」や「兄弟殺人」(カインとアベル)物語は世界の至るところに類似した話を見出せる。心理学者カール・グスタフ・ユングの「集合的無意識」にも通じる。
興味深い点は、多くのナラティブの中には一定の共通性があることだ。「洪水神話」や「兄弟殺人」(カインとアベル)物語は世界の至るところに類似した話を見出せる。心理学者カール・グスタフ・ユングの「集合的無意識」にも通じる。
まとめるならば、聖母マリアの無原罪出生説もイエスの復活も無限で広大な宇宙を創造した神の存在を理解する助けとなる限り、「神話」として生き続けていくだろう。一方、ハラリ氏の「ホモ・デウス」は「神話」を必要としない世界、ポスト「神話」時代を示唆している。人類は「神話」の世界で生きていくか、「ポスト神話」の世界で生きていくか、歴史的な選択の時を迎えようとしているのだろうか。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2022年12月8日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。