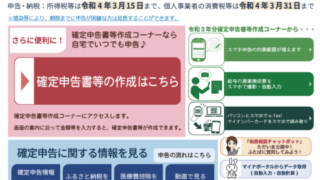KDDIは昨年9月に米国SpaceX社との業務提携を発表し、衛星ブロードバンドインターネット「Starlink(スターリンク)」をauのサービス通信網の一部として活用していくことを明らかにした。先般おこなわれたInterop Tokyo 2022の基調講演において、KDDI 執行役員 経営戦略本部長 兼 事業創造本部長の松田浩路氏が登壇し、その後の進捗や宇宙ビジネスへの取り組みについて語った。
KDDIの衛星通信サービス事業は、旧KDD(国際電信電話)時代からこれまでに50年以上の長い歴史がある。1963年に茨城宇宙通信実験所を立ち上げて、初の日米間テレビ伝送を成功させた。その後1969年に山口衛星通信所を開所し、同所では現在23基のアンテナが稼働している。その間に同社は、「地上局アンテナの開発や移動衛星通信システムの開発、衛星最適配置プログラムの開発、国際イベントで映像伝送をリードするなどの貢献をしてきた」と松田氏は説明する。

衛星通信の現状を説明すると、昨今注目されているSpaceXのサービスが後述する「低軌道衛星」を活用したものであるのに対し、現在の主流は「静止衛星」を活用した通信形式である。静止衛星は、地上から静止して見える衛星を経由して情報伝送をおこない、地球の上空3万6千kmという高い軌道を周回するため、「理論上3機あれば世界中で通信ができる仕組み」(松田氏)となっている。

KDDIでは現在、山口衛星通信所でそれらの静止衛星と通信をして衛星通信サービスを提供している。一例を挙げると、同署からNHKの国際テレビ放送を世界に発信し、160の国と地域に対して日本のニュースを届けている。
そのほかの用途としては、南極の昭和基地にアンテナを設置し、24時間365日現地とつないで昭和基地の生活基盤を維持。その際に、毎年一人同社の社員が南極越冬隊員として参加して保守作業をおこなっているという。また災害時への対策として、自衛隊に通信端末を納め、復旧活動にも役立てられている。
このほかに、携帯電話基地局の「バックホール」区間に衛星回線を利用している。バックホール回線は、山奥などの光回線がつながりにくい場所に補助的に使われる回線である。同様につながりにくさの改善に関する取り組みとしては、2011年の東日本大震災以降、海上から船を基地局とする取り組みも展開しており、「2018年9月の北海道の地震や2019年の台風の際にこれらを使って実際にエリア復旧ができた」(松田氏)としている。
低軌道衛星時代の幕が開けた
これらの静止衛星を利用したサービスが主流である中で、現在宇宙ビジネスの世界では、「低軌道衛星時代の幕開け」を迎えている。その現状について松田氏は、「1960年前後にも衛星が打ちあがって世界との通信が実現し、宇宙に抱いていた夢を現実にしたいという人類の挑戦心があった。今まさにそれが民間主導で行われている」と説明する。

その際にKDDIは、スタートアップとの共創で宇宙ビジネスの新規創造に取り組んでいるという。大企業パートナーのアセットとスタートアップのアイデアや技術をマッチングさせる「KDDI ∞ Labo」を約10年前から展開しており、ラボの卒業生には民間商用超小型衛星を開発したアクセルスペースがいる。そのほかにもコーポレートベンチャーキャピタルを運用し、資金を提供している。「これらのスキームを活用して、宇宙ビジネスの潮流に乗っていきたい」と松田氏は話す。
身近になった人工衛星と衛星通信ビジネス
現在宇宙ビジネス、衛星通信ビジネスが盛り上がりを見せる理由として松田氏は、「衛星打ち上げと人工衛星の民主化」を挙げる。まず打ち上げコストが下がり、昔のスペースシャトルは、27トンのロケットを15億ドルくらいかけて送っていたが、現在はSpaceXの「ファルコン9」ロケットを使えば、1kgあたり2940ドルで飛ばせるようになっているという。また衛星自体も小型化し、製造コストも安くなっているとのこと。
それに伴い、人工衛星の打ち上げ数も増えている。「1957年以来、全世界で1万数千機が打ち上げられているが、その中で30%近くがこの2-3年の間に打ちあがっている。それだけ民主化され、身近なものになった」と松田氏はいう。
その背景にあるのが、低軌道衛星の普及である。低軌道衛星は上空550kmの軌道を周回するが、静止衛星と比べて地球との距離が65分の1に縮まっている。距離が短い分、低遅延・大容量通信が可能になるが、カバレッジが狭くなるために大量の衛星が必要になる。低軌道衛星のメリットはこれまでも理解はされていたが、大量に打ち上げるのが大変だったため参入を試みた企業が挫折してきたという歴史があるが、SpaceXの登場によって新しい時代が切り開かれつつある状況である。

続々と低軌道衛星が打ち上がるとどうなるか。まず、衛星と地上を結ぶためのゲートウェイである地上局と、そこから地上を結ぶネットワークやクラウドが必要になってくる。衛星間光通信の実現に向けては、1個1個の衛星ごとに地上局を作っていくと手間もコストもかかるため、宇宙空間上で光通信を使ってデータのやり取りをして、まとめて地上局に送る形になる。その際には「受け皿となる地上局と、地上のネットワークやクラウド環境が大事になる」と松田氏は説く。
また、これまでの静止衛星通信と共存するためのルールの策定も必要となる。静止衛星と低軌道衛星の軌道が交わる部分が出てくるために、その際に低軌道衛星側で電波を止めてお互いの電波の干渉を防ぐ形をとっているが、国際電気通信連合(ITU)の世界無線通信会議において同社の河合宣行氏が議長を務め、ルール作りに取り組んできたのだという。
Starlinkをau基地局のバックホール回線に利用
これらの衛星通信の実績を踏まえた上で松田氏は、SpaceXとの提携による新たな取り組みについて説明した。SpaceXは、ロケットの製造から打ち上げから積載する衛星の開発まで、垂直統合型で全ておこなっているベンチャーである。同社が開発したファルコン9ロケットの上部には輸送庫があり、そこに50-55機のStarlink衛星が格納されて低軌道上に打ち上げられる。
SpaceX社は、総務省の資料によると4408機の低軌道衛星を配置し、複数の人工衛星を連携させておこなう衛星通信システムを運用している。通信速度は、「ダウンリンクで100Mbpsを超える。低軌道なのでその分遅延も短く帯域も太くとれる」(松田氏)。イーロン・マスクCEOの5月のツイート情報では32か国でサービスを提供し、随時拡張していく予定で、その中でKDDIは同社と日本国内でサービスを展開するために共同で技術検討を行っているという。
KDDIは昨年、Starlinkをauの通信網に採用することを発表したが、au回線での活用は端末と宇宙空間の衛星をつなぐ直接通信型ではなく、従来の静止衛星と同様にバックホール回線での採用となる。「スマートフォンが通常通り基地局と通信をして、光通信が入るところでは光を使うが、そうでないところをStarlinkを使って我々のコア網につなぐ」(松田氏)形となっている。
具体的には、Starlink衛星からの通信を受ける地上局が山口衛星通信所に設置されていて、そこから地上回線を使い、コアネットワークを経由してインターネットやクラウドにつながっている。現在は、そのエンドツーエンドの性能評価を一緒に行っているとのこと。衛星の移動に伴う電波のカバレッジに併せて基地局のアンテナを自動的に切り替えるシームレスな接続が可能になっているという。

昨年9月の提携発表以降、Starlinkの活用に関して多くの引き合いや問い合わせがあるという。ニーズや想定されるユースケースとしては、まず自治体での活用を挙げる。「通信がプアなエリアでのデジタルデバイドの解消、防災対応などのニーズがある」と松田氏はいう。その他にも、建設会社が山間部などの新しいエリアを開拓・開発する際に、職場の環境改善や安全確保のための活用や、老朽化する社会インフラに対するリモート監視やメンテナンスをおこなう際のインフラとしての活用などが見込まれているという。
気になるサービスの開始時期については、「年内開始に向けて急ピッチで準備をしている」(松田氏)とのことである。
(この記事はUchuBizからの転載です)
Source