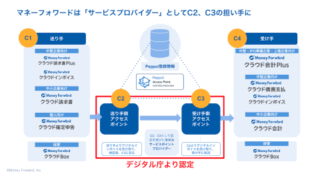デジタル通貨の概要を解説した前回に続き、今回は海外のデジタル通貨の取り組みを紹介したい。
デジタル通貨を、「デジタル化され、ドルや円などのソブリン通貨単位を用い、広く支払いに使える手段」と定義すると、(1)民間デジタル通貨、(2)価値の安定を図った暗号資産である「ステーブルコイン」、(3)中央銀行デジタル通貨、の3種類を考えることができる。
(1)民間デジタル通貨
民間債務の形をとるデジタル決済手段は、日本の「Suica」などを含め、世界中に多くの事例がある。とりわけ、市場経済が発達し、民間がサービス提供を競ってきた先進国で発達をみてきた。もっとも最近では、新興国で近年急速に拡大した通信ネットワークや巨大テック企業(ビッグテック)が、デジタルマネーの分野に参入する事例が目立っている。
1:PayPal(米国)
民間デジタル通貨の先駆的なものとして、1998年に登場した米国の「PayPal」が挙げられる。これは、中古品などの売買プラットフォームである「eBay」の発達に伴い、その決済手段として拡大した。利用者はPayPalのアカウントに銀行口座やクレジットカードを紐付け、アカウントから支払うわけである。これにより、買い手は自らの銀行口座やクレジットカードの番号を見ず知らずの売り手に知らせずに済む。PayPalは、創業者の一人Elon Musk氏がその後自動車企業Teslaを創業するなど、多くの起業家を生んだことでも知られる。
2:Swish(スウェーデン)
民間銀行によるデジタル通貨の取り組みとしては、2012年に登場したスウェーデンの「Swish」が挙げられる。Swishは民間銀行が共同で構築したものであり、ユーザーはSwishのアカウントと銀行口座や携帯電話番号とを紐付けることで、スマートフォンなどを通じて個人間送金や店舗での支払いを行うことができる。
3:M-PESA(ケニア)
新興国や途上国におけるデジタル通貨の先駆的な取り組みとしては、2007年に登場したケニアの「M-PESA」が有名である。M-PESAは、携帯電話網を運営するサファリコムが提供するプリペイド型携帯電話から始まった。このプリペイド残高を人々が携帯電話を通じて個人間で直接やり取りできるサービスが、決済手段としても使われるようになっていったものである。M-PESAは、デジタル通貨が金融包摂を大きく進めた例として知られている。
4:巨大テック企業(ビッグテック)のデジタル通貨(中国、インドネシア、南米など)
近年、「ビッグテック」と呼ばれる巨大企業が一斉にデジタル決済分野に参入している。有名なものとしては、中国の阿里巴巴(アリババ)の子会社アントグループが提供する「Alipay」や、同じく中国の騰訊(テンセント)グループが提供する「WeChat Pay」、東南アジアのGrabやGoJekが運営する「GrabPay」や「GoPay」、南米のMercadoが運営する「Mercado Pago」などが挙げられる。
例えば、2013年に登場したWeChat Payは、もともとはメッセージをやり取りするSNSである「WeChat」に、少額のお年玉を送れるサービスを付加することから始まった。これが支払や個人間の送金サービスとして広く使われるようになり、その後10年足らずの間に、約10億人の利用者を持つ世界最大規模の支払決済インフラに成長した。
(2)ステーブルコイン
次に、暗号資産が裏付け資産を持つことなどにより価値の安定を図る「ステーブルコイン」が挙げられる。
2-1:リブラ(ディエム)
近年話題を集めたステーブルコインとしては、米国のFacebook(現Meta)が主導する形で2019年に計画が公表された「リブラ」が挙げられる。リブラは複数の先進国通貨建ての安全資産を裏付けとすることで、これらの通貨バスケットに対する価値を安定させることを狙った。
もっとも、リブラ計画には各国当局から強い警戒感が示された。Facebookは全世界に20億人を超えるユーザーを有する。一方で、世界には自国通貨への信認が十分でない国々もある。このような国では、海外送金にとどまらず、国内取引でも自国通貨の代わりにリブラが使われることも想定される。そうなると、リブラを通じて実質的な資本流出が起こり得ることになり、これは、とりわけ新興国や途上国には受け入れがたい。
各国当局からの警戒感を受け、リブラは名称を「ディエム」へと変更し、米ドル建てのステーブルコインの発行を目指した。さらに最近、リブラの事業そのものが米国の銀行に譲渡される旨が発表された。
2-2:ソブリン通貨建てステーブルコイン(USDCなど)
この間、リブラの動きと並行して、米国を中心に、ドルやユーロ建ての価値の安定を図ったさまざまなステーブルコインが発行されている。代表的なものとしては「USD Coin(USDC)」などが挙げられる。
ステーブルコインは、価値が安定し、かつ、ブロックチェーンや分散台帳技術(DLT)などの技術を使ってセキュリティトークンやNFT(非代替性トークン)などの新しい資産の取引に有用となり得るものとして、近年注目されている。米国をはじめ各国当局も、その決済手段としての可能性に鑑み、これをいかに規制監督すべきかといった議論を活発化させている。
ステーブルコインは、価値を安定させるメカニズムが十分かどうかを問われることになる。例えば、裏付け資産の保有を減らし、リスクの高い資産を混ぜるほど、発行者は発行益を得やすくなるが、一方でステーブルコインの価値が損なわれるリスクも高まる。この問題は、規制監督上も重要な論点となる。
(3)中央銀行デジタル通貨(CBDC)
中央銀行が自ら発行するデジタル通貨は「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」と呼ばれる。国際決済銀行(BIS)が昨年夏に公表した文書では、中央銀行デジタル通貨を公式に発行した国としてバハマと東カリブ中央銀行加盟国が挙げられている。また、その後2021年秋には、ナイジェリアも中央銀行デジタル通貨を発行している。
この間、世界第二位の経済大国である中国が「デジタル人民元(e-CNY)」の実験を積極的に進めており、世界的な注目を集めている。
中央銀行デジタル通貨については、預金からの資金シフトを起こし、銀行貸出や民間主導による資源配分に影響を与えないか、また、民間のイノベーションやデータ活用などを阻害しないかといったさまざまな論点がある。これらは、とりわけ発達した銀行システムを持つ先進国では大きな論点となるため、慎重な検討が進められている。
3-1:サンドダラー(バハマ)
バハマは2020年10月20日、中央銀行デジタル通貨「サンドダラー」を世界で初めて正式に発行した。
サンドダラーは、砂浜に生息するヒトデの仲間の生物の名前であり、中央銀行のシンボルマークにもなっている。カリブ海に浮かぶ人口約35万人の小国バハマは、米ドルと通貨レートを一定に保つバハマドルを法定通貨としている。バハマはハリケーンに見舞われやすく、これによって現金の供給網が分断されることがあった。この観点からもデジタル技術を活用した決済インフラ構築が求められており、バハマを代表する動物の名前を冠した中央銀行デジタル通貨が開発されたという経緯がある。
サンドダラーは、民間銀行が提供するアプリやカードを通じて人々や企業に提供されており、用途などに応じた複数のアカウントが用意されている。
まず「個人用I」である。これは、銀行口座を持たない人々や旅行者向けであり、残高上限は500バハマドル、月当たりの取引量上限は1500バハマドルと少額に制限されている。一方で、本人確認は緩い。
次に「個人用Ⅱ」である。これは銀行口座と紐付けられており、残高上限は5000バハマドル、月当たりの取引量上限は1万バハマドルと、個人用Ⅰに比べ引き上げられている。
さらに「商業用」がある。これは法人が高額の取引にも使えるもので、やはり銀行口座と紐付けられる。残高上限は保有者の性質に応じて8000~100万バハマドルに設定されている。取引量に上限はない。
なお、サンドダラーは海外送金には使えないため、海外に送金をしたい人は、サンドダラーを預金に替え、銀行を経由して送金する必要がある。
バハマ中央銀行は、サンドダラー発行の目的として、効率化などに加え、銀行サービスに十分アクセスできていない人々に決済手段を提供する「金融包摂(きんゆうほうせつ:financial inclusion)」の推進を掲げている。同時に、現金を廃止するつもりはないとも明言している。
3-2:デジタル人民元(中国)
中国は2020年春より、国内主要都市で「デジタル人民元(e-CNY)」の試験発行を開始している。具体的には、抽選で当選した人々に200元程度のデジタル人民元を配布したり、公務員への支払いの一部をデジタル人民元で行い、これらの人々に店舗や通信販売などで使ってもらったりするといった実験を進めている。
デジタル人民元は、バハマのサンドダラー同様、個人や企業に対し、民間銀行などを通じて間接的に発行される。アプリやカードも民間銀行が提供しているが、2022年1月からは中国人民銀行も試験用のアプリをローンチしている、ただし、このアプリを使うには、民間銀行の口座から資金を移動させる必要がある。
デジタル人民元についても、サンドダラー同様、本人確認の厳格さや用途の違いなどに応じた複数の種類のアカウントが用意され、用途や性格に応じた金額制限が課されることが想定されている。
デジタル人民元は、2月の北京冬季五輪の会場でも試験的な流通が行われており、注目を集めている。
このように、デジタル通貨を巡っては、世界中で数多くの取り組みが行われている。その内容は国により違いはあるものの、「新しいデジタル技術を活用し金融インフラを高度化しなければ」という問題意識は各国で共通している。
山岡浩巳
フューチャー株式会社 取締役 兼 フューチャー経済・金融研究所長。ニューヨーク州弁護士。民間企業により構成される「デジタル通貨フォーラム」座長。86年東大法学部卒、90年カリフォルニア大バークレー校ロースクール修了。日本銀行調査統計局景気分析グループ長、企画室シニアエコノミスト、金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを経て現職。この間、IMF日本理事代理、バーゼル銀行監督委委員なども務める。