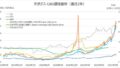ドイツの著名なウイルス学者クリスティアン・ドロステン教授(シャリテ・ベルリン医科大学ウイルス研究所所長)は南ドイツ新聞(SZ)とのインタビュー(2月9日)で新型コロナウイルスの武漢ウイルス研究所(WIV)発生説について、「コロナウイルスSarsCov-2が武漢のウイルス研究所から発生した可能性を排除したくないが、それはありそうにはないと思っている」と語った。

ドロステン教授(NDR公式サイトから)
教授は、「これまで自分は動物界からウイルスの自然発生説と武漢研究所発生説の2通りの説を排除してこなかったが、動物界からのウイルスの自然起源がより妥当であると考えてきた。Sars-CoV-2と同じ種に属するSars-1ウイルスを知っている。Sars-1はコウモリに由来する。ウイルスはジャコウネコとタヌキなど中間宿主を経過して変化し、人間にも感染するようになった可能性がある」と説明する。実験室起源説の仮説については「比較的質の高い科学的証拠はまだない」という。
そのうえで、「武漢から公表されたプロジェクトから危険な実験が行われたことが分かるが、その実験でSars-2が生まれてはこない。科学者たちはコウモリに新しい特性を組み込んだだけで、それをSarsCov-2の前身とみなすことは出来ない。遺伝子工学を使用して新しいスパイクタンパク質がコウモリウイルスに組み込まれた『機能獲得実験】で、ウイルスはよりよく増殖する可能性があることを示している。コロナウイルスはスパイクタンパク質にフューリン切断部位(PRRAR)を持っている。フューリン切断部位を挿入することは理論的に考えられる実験室での実験だ」
同教授は、「コロナウイルスの発生源問題では自然起源がはるかに可能性が高いと考えている。(WIV起源説を)完全に除外したくはないが、それは現在時点では一つの可能性だ。いずれにせよ、中国が全面的に協力した場合にのみ、全容が明らかになるが、残念ながら、中国側は実験内容の全容を隠蔽している」と指摘、コロナウイルスの起源解明には中国側の協力が不可欠であると強調している(「WHO調査団長エンバレク氏の証言」2021年8月22日参考)。
同時に、「武漢での実験について早い段階で発表しなかったことは大きな間違いだ。何よりも、米国の一部の人々はこれらの実験について知っていたが、その実験内容を積極的に伝えることを避けた。私を含む多くの科学者はプロジェクトについて知らされていないかった。それを知っていれば、少なくとも質問があった」と述べている。
ドロステン教授はインタビューでは「米国の一部の人々」と述べ、名前を挙げていないが、少なくとも2、3人の科学者の名前がすぐに思い出される。調査ジャーナリストとして著名なシャリー・マークソン女史(Sharri Markson)は、「中国共産党政権は世界の覇権を握るために世界のグローバル化を巧みに利用し、最新の科学技術、情報を手に入れてきた。武漢ウイルスはそのグローバル化の恩恵を受けて誕生してきたのだ。それゆえに、というべきか、国際社会はそのグロバリゼーションの痕跡を辿ることで、武漢ウイルス発生の起源を解明できる道が開かれる」と述べている(「武漢ウイルス発生源解明は可能だ」2021年11月2日参考)。

ピーター・ダザック氏(ダザック氏のツイッターから)
ウイルスの機能獲得研究、遺伝子操作の痕跡排除技術は、米ノースカロライナ大学のラルフ・バリック教授、そして英国人動物学者で米国の非営利組織(NPO)エコ・ヘルス・アライアンス会長のペーター・ダザック氏らとの共同研究で中国側が獲得していった内容だ。ダザック氏らは米国の税金でWIVのコウモリ研究を支援してきた。米国の感染症対策のトップと言われるアンソニー・ファウチ博士も、WIVと関係を有してきた。ちなみに、機能獲得研究とは、ウイルスの感染力、致死力をアップするための研究で、ウイルス学者からは「非常に危険な研究」といわれてきた。米国のオバマ政権はその研究を禁止したが、数年後、再び許可されたという。ファウチ博士はウイルスの機能獲得研究を支持していたという(「ダザック氏解任は何を意味するか」2021年7月1日参考)。
中国共産党政権がWIVでの実験内容と関連文書を公表することは期待できない。ドロステン教授は武漢ウイルスの解明を阻止しているのが中国側の隠蔽姿勢にあることを明確に指摘したうえで、「実験を知っていた米国の科学者たちの責任」に言及している。共産党政権下の中国とは違い、米国は世界の民主国家のリーダーを自認する大国だ。バイデン米政権はコロナウイルスの発生起源問題を解決すべき責任がある。世界で12日現在、武漢ウイルスで580万人以上の死者が出ているのだ。
編集部より:この記事は長谷川良氏のブログ「ウィーン発『コンフィデンシャル』」2022年2月13日の記事を転載させていただきました。オリジナル原稿を読みたい方はウィーン発『コンフィデンシャル』をご覧ください。