国産超伝導量子コンピュータの初号機が、2023年3月27日から稼働した。
理化学研究所(理研)などの共同研究グループは、埼玉県和光市の理研(和光地区)に、64量子ビットの集積回路を採用した超伝導量子コンピュータを整備。理研は、量子コンピュータをクラウドで公開し、「量子計算クラウドサービス」として、外部から利用できるサービスの提供を開始する。
同日午前10時から行なわれた記者会見で、理化学研究所 量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長は、「量子コンピュータの発展は想像以上のものであるが、今回の国産初の超伝導量子コンピュータの稼働は、富士山にたとえれば、まだスバルラインに乗ったぐらいのところである。大規模な量子コンピュータの実現は、長期的なものであり、チャレンジングな課題である。だが、貢献できる要素は大きい」などと語った。
なお、今回稼働した量子コンピュータは、64量子ビットのすべてが動作しているわけではなく、53量子ビットだけが動作している状況であることも明らかにした。
「64量子ビットのうち、1量子ビットが壊れており動作しない。また、運転のために冷却した段階で、配線の問題で2カ所の増幅器のノイズが大きく、その周辺の8量子ビットが動いているが測定ができない状況にあるため使用していない。さらに、2つの量子ビットの周波数が設計からずれてしまい、隣接する量子ビットの周波数が衝突し、うまく制御できない状況にある。これらが回復する時期は明確ではない」とし、「11量子ビットが動かせない状況にあるが、Googleでも、54量子ビットのうち、53量子ビットしか動作しなかった。奇しくも同じ量子ビット数になった」と述べた。
コヒーレンス時間は10~20μsとなっているほか、量子ビットの周波数が設計からずれていることで、隣同士の量子ビットが双方向でつながっていなかったり、動かしにくかったりといった状況が生まれているという。
今回の国産初号機となる超伝導量子コンピュータは、理化学研究所量子コンピュータ研究センターの中村泰信センター長や、産業技術総合研究所3D集積システムグループの菊地克弥研究グループ長、情報通信研究機構超伝導ICT研究室の寺井弘高室長、大阪大学量子情報・量子生命研究センターの北川勝浩センター長および藤井啓祐副センター長、富士通量子研究所の佐藤信太郎所長、NTTコンピュータ&データサイエンス研究所の徳永裕己特別研究員などで構成する共同研究グループによって開発を進めてきた。
100人以上の研究者が参加し、超伝導量子ビット集積回路技術のほか、パッケージ実装、マイクロ波制御・読み出し配線、マイクロ波変調復調装置、デジタル制御エレクトロニクス、制御ソフトウェア、量子ゲート回路、量子誤り訂正プロトコル、量子アルゴリズム、量子応用計算といったさまざまな技術レイヤーにまたがり、研究開発を進めてきた。
今回の量子コンピュータで採用されている超伝導方式は、超伝導材料を用いた電子回路上で、ジョセフソン接合によるトンネル接合素子を用いて量子ビットを実現。ゲート型量子コンピュータの中では、将来有力とされている方式の1つだ。
理化学研究所では、2001年に、巨視的量子コヒーレンス研究チームを発足し、量子情報科学に関する研究を開始。2021年からは、中村泰信博士のもと、量子コンピュータ研究センターを発足し、研究を継承してきた。
2021年には、富士通と共同で量子コンピュータ研究センター内に理研RQC-富士通連携センターを設置。理研が取り組む超伝導回路を使った量子コンピュータの先端技術と、富士通が保有するコンピューティング技術、顧客視点に基づいた量子技術の応用知見を統合し、研究開発を進めており、今回の超伝導量子コンピュータにもこれらの知見が活用されている。
大規模化を見据えた2次元集積回路と垂直配線パッケージ技術
今回公開した超伝導量子コンピュータは、64量子ビットの集積回路を搭載。「2次元集積回路」と「垂直配線パッケージ」の2つが特徴となっている。
理研の中村センター長は、「超伝導量子ビット集積回路を開発し、そこに垂直配線を組み合わせてパッケージングした。平面上に量子ビットを大規模に敷き詰めた環境に、量子ビットを越える形で配線を行なうと大きな問題が生じることになる。今後の拡張性にも対応するために、2面から垂直方向に配線を設けるパッケージング方法を開発した。また、量子ビットはマイクロ波の電気信号で制御・読み出しを行なうが、この信号を正しく届けるように同軸ケーブルをしている」と説明する。
2次元集積回路では、正方形に並べた4個の量子ビットが、隣り合う量子ビットをつなぐ量子ビット間結合により接続。正方形の回路の中には、読み出し共振器や、多重読み出し用フィルター回路などを配置している。4つの量子ビットで構成する基本ユニットは、正方形の四隅に量子ビットが並び、中央に読み出し回路を配置。この基本ユニットを2次元に16個並べることにより、量子ビット集積回路を作ることができる。
「ユニットセルをタイル状に並べていくだけで拡張が可能になる構造としている。2×2の4ビットがユニットセルの単位になっており、そこに読み出し共振器が接続し、それがフィルター共振器につながり、読み出すことができる。量子ビットは0.2μmでのジョセソン接合を用いている」という。
今回の64量子ビット集積回路は、16個の機能単位(ユニットセル)から構成され、2cm角のシリコンチップ上に形成。回路の開発については、情報通信研究機構(MICT)が超伝導薄膜の成膜、産業技術総合研究所(AIST)が基板に貫通する穴の作るプロセスなどで協力したという。「ユニットセル(チップ)は、まだ研究開発の途上であり、進化を遂げていくことになる」という。
また、個々の量子ビットに対する制御や読み出し用の配線では、2次元平面に配置した量子ビットへの配線をチップに対して垂直に結合させる垂直配線パッケージ方式を採用し、さらに量子ビット集積回路チップへの配線を一括で接続できるようにした。これにより、量子ビットに対する制御・読み出し用配線が、信号用コンタクトプローブを介してチップに対して垂直に接続され、この配線を通してマイクロ波信号の送受信が行なわれる。
「垂直配線パッケージは、上の部分に剣山のように電極が飛び出しており、その上にチップを乗せ、チップの裏側が電極とつながることになる。さらに、チップの上にカバーを乗せて、ノイズなどを遮蔽する。その上に金属カバーで蓋をして、電極に強く固定する構造になっている」という。
「2次元集積回路と垂直配線パッケージにより、容易に量子ビット数を増やすことができ、今後の大規模化においても、基本設計を変えることなく対応できる」と述べた。
2次元集積回路と垂直配線パッケージを用いた64量子ビット集積回路チップは、中央の円筒型磁気シールド内に格納され、制御配線および読み出し配線を接続。真空断熱容器の内部に収めて、希釈冷凍機で冷却する。運用時にはマイナス273.14℃でチップを冷却するという。
「64量子ビット回路の制御と読み出しのために入力配線を96本、出力配線を16本の合計112本でつないでいるほか、低温低雑音増幅器を16台、低温ジョセフソンパラメック増幅器(JPA)を16台搭載。磁気遮断付き試料パッケージや極低温熱輻射遮断などの各種フィルターも活用している。それらに真空断熱のカバーを装着し、冷却することになる。絶対零度から0.01度高い温度で冷やすことになる」としている。
配線では量子ビット制御に64本、読み出し信号入力に16本、JPA駆動マイクロ波入力に16本使用。また、量子ビットを制御するための信号には、マイクロ波の周波数(8~9GHz)で振動する電圧パルスを用いている。
「量子ビットごとに異なる周波数のマイクロ波を必要としているため、高精度で位相の安定したマイクロ波パルス生成が可能な制御装置を、大阪大学とともに開発した。マイクロ波のパルスを正確に送出し、受信することができる。これを動かすためのソフトウェアの開発についてはNTTの協力を得た」という。
制御・読み出しの忠実度については、2022年の段階で、目標としていた99%以上を達成しており、高い精度で実現することができているという。
研究機関や企業向けにクラウドサービスも提供
稼働させた64量子ビットの超伝導量子コンピュータは、量子計算クラウドサービスとして提供する。ここでは大阪大学が協力し、フレームワークを構築した。
利用者は、理研の外にあるクラウドサーバーに接続することで、超伝導量子コンピュータへのジョブ送信や計算結果の受信を行なうことができる。具体的には、利用者が量子計算プログラムをクラウドサーバーに送信すると、制御パルスに変換されて、超伝導量子コンピュータの量子ビットを制御。得られた信号が計測され、計算結果がネットワークを介して、ユーザーに送られるという仕組みだ。
3月27日からサービスを開始するが、当面は、量子計算などの研究開発の推進および発展を目的とした非商用利用とし、利用申請を行ない登録した大学や研究機関、企業などの研究者や技術者だけが、無料で利用できる。
「システムがより安定したり拡張したりすれば、ユーザーの対象や用途を広げていくことになる。さまざまな考え方を持った人に使ってもらい、フィードバックを得ながら改善をしていきたい」としている。
量子コンピュータの利用分野としては、物流・交通、科学計算、AI、金融、創薬・医療、化学、材料開発、セキュリティ、情報通信、エネルギーなどを想定している。
「量子コンピュータは、量子力学の原理に基づいた新たな計算手法であり、従来のコンピュータを凌駕する高効率な計算を実現する。さまざまな社会課題の解決に貢献したいと考えている。特に、表面化学における触媒反応、生体化学による酵素反応など、計算量が多く、現在のスーパーコンピュータでも難しい化学分野での応用に期待している」などと述べた。
次は144量子ビットへの拡張。富岳との融合や多方式の研究も
今後の取り組みとしては、継続的に利用環境の整備を行ない、運用の利便性を向上するほか、社会実装に向けてRQC-富士通連携センターにおいても、今回と同等の64量子ビットの量子コンピュータを整備し、2023年度に実機を公開する予定を明らかにした。
「技術は少しずつ改善をしていくが、ハードウェアは今回のものとほぼ同等である。商用利用にはならないが、もう少し企業での利用を想定することになる」という。
また、さらなる大規模化を可能にするハードウェアおよびソフトウェア技術の開発を促進。実機を利用したエンドユーザーを巻き込んだアプリケーションの開発、ハードウェアやソフトウェア量子人材育成のプラットフォームとして運用していくと述べた。
「拡張容易性を追求しており、次のステップは144量子ビットへの拡張を想定している。これはそんなに難しいことではない」と語った。
今回開発した技術では、4量子ビットで構成される基本ユニットを平面上に周期的に並べることで、集積化された量子ビットの数を増やすことができる。そのため、64量子ビットをさらに4✕4に並べると、計算上では1,024量子ビットの実現が可能になる。
さらに、富岳などのHPC技術との融合による計算可能領域の拡大、誤り耐性量子計算の実現を目指した高度化にも取り組む。「古典コンピュータとの融合は理研の中でも重要な取り組みの1つに位置づけている」という。
ちなみに、共同開発グループに参加している富士通と大阪大学では3月23日、量子コンピュータにおける量子エラー訂正で確保する物理量子ビット数を大幅に減らすことができる「高効率位相回転ゲート式量子計算アーキテクチャ」を発表しており、これも、今回の超伝導量子コンピュータに採用する考えを示している。
なお、理化学研究所量子コンピュータ研究センターでは、今回稼働させた超伝導方式による量子コンピュータのほかに、光量子計算研究チームチームリーダーである古澤明博士らが取り組んでいる光方式、半導体量子情報デバイス研究チームチームリーダーである樽茶清悟博士らが取り組む半導体方式の研究も行なっている。また、真空中の原子を用いる方式など、物理系に基づくハードウェア研究を同時並行で進めている。
また、量子計算理論や量子アルゴリズム、量子アーキテクチャなどのソフトウェア研究も進めており、今後も、量子コンピュータに関する研究開発に、多面的に取り組んでいく姿勢をみせている。











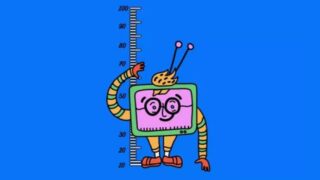









コメント