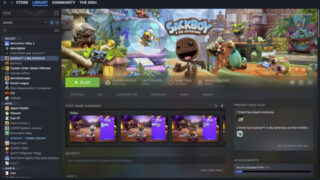VRChatとは、VR空間上で世界中のユーザーとコミュニケーションを楽しめるサービスである。
Facebookが社名を「メタ」に変更したことで、世界で大きく注目されることになった「メタバース」だが、その言葉が注目を浴びる以前から、VRChatはユーザーが活発なサービスだ。2022年現在、世界で最も接続者の多いVR空間として人気を集めており、VRChatをきっかけにVRの世界に魅了されたというユーザーも少なくない。
世界で最も“カオス”なVR空間「VRChat」とはなにか–その魅力から始め方までを解説(2021年7月15日掲載)
筆者自身も、VRChat上で、学校コミュニティ「私立VRC学園」を立ち上げたりしていたなか、プロの画家である植村友哉さん【ウェブサイト】【Instagram】から「VR・メタバースを使った美術館、個展を開きたい」という相談を受け、VRChat上で展示会を公開している。植村友哉さんの作品やその他のアーティストの作品を複数点展示し、いまでは美術や作品についてプロの解説を聞くことのできる人気のイベントとなった。
デジタルアートを描くユーザーが、自身の作品をメタバース上に展示することは昨今見受けられるようになったが、プロとして活動している画家が、油絵やアクリル絵の具を使った自分の作品をメタバース上に展示することは珍しい。そこで今回は、メタバースに活動の幅を広げている画家の植村友哉さんにお話を伺った。
コロナ禍にスタートしたVR美術館「WESON MUSEUM」
小学校は柔道、中学校~大学はレスリング部に所属しスポーツに没頭する傍ら、小学生の頃から自由帳に模写を始め、独学で絵を描くようになった植村友哉さん。画家になる以前は植村さんは、大学卒業後は食品メーカーに就職し、営業をしていた。人と話すことは得意だったため、営業職を楽しんではいたものの、2016年に縁あって訪れたパラオ共和国の地で、日本では見られないような綺麗な景色に言葉を失う。「自分もこのパラオの景色のように自分らしくいられたら楽しいだろう」と感動したことが画家を志すきっかけとなった。この時にパラオ現地でスケッチし、日本に持ち帰って油絵に直した作品は、植村さんの画家としてのキャリア初の受賞作となった。
画家として活動していくなか、世間はコロナ禍になり、リアルでの個展の開催やパラオとの文化交流が困難になった。そのなかで「どうにか低接触型での展示会の開催やパラオとの美術を通じた文化交流ができないか」と思い、メタバース上で美術展を行いたいと考えたという。
周囲に相談していくもなかなかテクノロジーに詳しい人に出会えず苦労したが、筆者である齊藤大将と知り合い、VR美術館「WESON MUSEUM」がスタートする。
文化交流、国際交流としてのVR美術館
VR美術館で目指しているところとしては、絵を美術文化として、各国の交流として美術を活用できるのではないかということ。そして、 各国の作品をいつでもどこでも見れるというボーダレスな展示空間、と植村さんは答える。
メタバースを使って作品を展示することは、メディアとしての機能が大きい。しかし植村さんは、ただ単に自分や周囲の作品をメタバース上に展示するのではなく、美術文化としての側面を意識している。メタバースの技術の側面をうまく活用すると、それは美術文化発展に繋がる可能性もある。
前述したように、植村さんはパラオ共和国との親睦が深いアーティストであり、パラオを表現した作品も数多く制作している。アナログの作品を画像データなどに変換し、メタバース上に展示すると、作品の見え方やテクスチャ、想いや制作の背景などは伝わりにくくなる。美術文化や美術史の観点からすると、素直に喜べることではないだろう。
しかし、メタバースを使うことでの役割は別のところにある、と植村さんは考えている。
毎週世界中からの訪問者と自身のVR美術館での交流を通し、場所や時間的な縛りが少ないVR美術館だからこそ、リアルで開催する個展よりもコミュニケーションが取りやすく、多種多様な人に美術というものを知ってもらう機会を生むという考え方だ。
VR美術館「WESON MUSEUM」には、パラオ人アーティストの作品も数点展示してある。日本にいては触れることがない作品であり、またパラオにいる方も日本に来ないと観ることができない作品もある。そういった物理的制約を無視して、新しい領域や文化に触れることをVRやメタバースは可能にしている。
文化は積み上げていくもの。メタバースを使うことによって新しい感動、それをテーマにして新たな作品が生まれるかもしれない。
VRで美術に関わる人の裾野が広がる
パラオとの国際交流で進めた植村さんと、それを支える筆者齊藤のVR美術館の活動。実際の作品との見え方を比較すると色なども鮮やかさは下がってしまうが、一番の利点は「会話ができること」と植村さんは答える。観に来たあらゆる人とアーティストが双方向のやりとりができるという点は、これまでにあまり見られない展示会のスタイルである。
実際、リアルで個展を開催しても、その訪問者の多くが自分のファンや同じ業界の人、あるいは所属する芸術コミュニティの人間である。一方で、VR美術館に訪れるユーザーのほとんどは、美術に全く関わってもなければ、美術館にもほとんど行かないというような人々だ。毎週のように参加していただいているユーザーさんにも「全く美術に興味がなかった。でも、VRで美術への敷居がだいぶ下がり、気軽に来れるから行ってみようという気持ちになる」と話していた。
美術館や展示会に実際に足を運ぶとなると、たどり着くまでに障壁が多い。週末の予定を確認し、時間を確認し、ネットでチケットを購入し、電車で現地に向かい、順番に作品を観る。休憩などを挟めば半日から1日かかってしまう。だがVRであれば、ネット環境があれば自宅からいつでも作品を観ることができる。美術がわからないって人にも届きやすいこのメタバースという切り口が、美術に関わる人の裾野を広げることに役立つ。
VR美術館「WESON MUSEUM」には4つあるワールドがあり、それぞれ違ったテーマで構成されている。空に浮いた美術館に入り芸術体験ができる「天空美術館」や森林にいそうな鳥などを題材にした「森林美術館」、南国の植物などを題材に大きな植物の葉っぱをのぼりながら鑑賞し、落ちると最初からというゲーム性も取り入れた「雨降る美術館」などが体験できる。そして、パラオの美しい景色の中に美術館をつくった「パラオ美術館」。
作品の見え方や色合いは、直接作品を観ることと比べると、どうしても質が下がってしまうが、一方で、展示空間自体を作品に合わせて制作することで、より見に来る人を楽しませやすくなる。近年では、美術館へ足を運ぶ若者の数が減少傾向にある中、デジタルアートなどの展示会は人気傾向になる。その事実を踏まえると、VR美術館を使った作品の展示は、多くの人々にとって敷居の高そうな美術との距離を縮める役割を担えるかもしれない。
VRで美術を展示するからこその制約
VRで美術の展示をすると良いことばかりに見えるが「全体的には批判的な意見が多い」と植村さんは答える。もちろん新しいことを始めると批判や意見はつきものである。
メタバースを美術展示に活用することは、現状あくまでメディアとしての効能は感じるが、美術的な技術が広がるわけではない。
デジタル絵画は、アナログ絵画と違って色彩などを数値化することができる。つまりデジタル絵画は再現性が高い。一方で、アナログ絵画は異文化ならでは違いや、湿気や時間経過などが反映されるため、再現性が低い。また、描く人の筋力差によるタッチの違いをはじめとして細かく複雑に絡み合った要素が作品に影響するのである。
美術的制限もメタバースではより強く働く。例えば、アクリル画と油絵の違いもメタバースでは見てる人からはわかりにくい。美術の表現が与えることが、観る人に100%伝わってるかは微妙なところである。そのため、鑑賞者の意識に作家の想いや気遣いが届くかは作家としては自信があまりないと植村さんは言う。
メタバースを作品発表の場としようとしてなかったのが良かった
植村さんは自分の作品発表としてメタバースを活用しているというよりは、作品を使って誰かと繋がりたいという想いでメタバースを活用している。
自分の表現方法が絵であり、それを使って人と繋がる場としてのメタバース。表現したい概念がまず作品にあり、作品を誰かに納得してもらいたいという気持ちは少ない。色と形を使って表現しようした結果、その絵になっただけである。
そのような想いのもとに生まれた作品は、VRゴーグルを通して鑑賞された場合、それでは伝わない細かな気遣いや想い、感情や背景にあるストーリーがたくさんある。作品を作った当初の想いと、メタバースでの見せ方に矛盾が生じる。この点は、絵をただ上手く描けば良いというだけの人にはわかりずらい部分かもしれない。
そのため、メタバースを使うことで美術の文化や技術発展には繋がらないだろうという意見を否定することもできないし、メタバースを活用して美術の裾野広げる活動を納得してもらうべきかもわからないと植村さんは付け加える。
「以前、桜の絵を木の額にしれて、その木の額に穴を開けて桜の香料をいれたことがあったんです。桜の絵から桜の匂いがしたら面白いと思いまして。エンターテイメント的なものですね。ですが、だいぶ批判されました」
絵は布などに絵の具がのったもの。その中で小細工をせず、どうやって自分の感情を表現するかということが求められる。つまり、VR美術館は作品表現の域にはまだ達しておらず、現状は植村さんが考えるように、作品を通じて人と繋がる場、メディアとしての空間が最適なのかもしれない。
一方で、近年では多くのアーティストがSNSに自分の作品を載せ、作品を売ったり、作品発表をすることが当たり前になった。その現状を切り取ると、数年後、VR美術館がアーティストにとって当たり前になる可能性もある。
そもそもデジタル上でアナログ作品を扱うというのが難しい。しかし、人と繋がる場やメディアとしてのメタバースの使い方は、芸術に関わる人たちにとっても無視できないものになるのかもしれない。
齊藤大将
Steins Inc. 代表取締役 【http://steins.works/】
エストニアの国立大学タリン工科大学物理学修士修了。大学院では文学の数値解析の研究。バーチャル教育の研究開発やVR美術館をはじめとするアートを用いた広報に関する事業を行う。
Twitter @T_I_SHOW