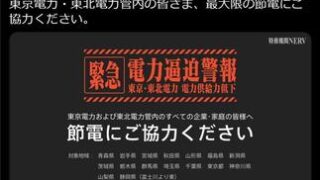「IEEE 802.3cn」を前身とする「IEEE 802.3ct」が2021年に標準化
今回は「IEEE 802.3cw」の話。とはいえ、まだTask Forceの段階なので、IEEE P802.3cwという扱いだ。
このIEEE P802.3cwにまつわる話はこちらで紹介したが、要するに当初は「IEEE P802.3ct」として検討されていた規格の中から、「400GBASE-ZR」だけを分離した格好になる。
元々IEEE P802.3cwの前身は、前回紹介した「IEEE 802.3cn-2019」である。
このIEEE 802.3cn、Study Groupの名称は”IEEE 802.3 Beyond 10 km Optical PHYs Study Group“で、ここから50G/200G/400Gの規格の標準化を行うという話になったが、いずれも到達距離が80kmで、100GのDWDM、および400GのDWDMの2つについてはIEEE 802.3cnから落とされた。
これらが落とされた行く先となったのが、2018年11月に形成されたIEEE P802.3ct Task Forceである。ちなみに以前の記事の際はまだTask Forceの作業が完了していなかった。
しかしながら、その後も順調に作業が進み、2021年5月の電話会議をもってTask Forceの作業はすべて終了。6月にはIEEE 802.3ct-2021として標準化が完了している。
「IEEE 802.3cn」から分割された「100GBASE-AR」と「400GBASE-AR」、「IEEE P802.3cw」として2023年8月に標準化が完了?
ということで、分離されたIEEE P802.3cwについて。Task Forceの結成は2020年4月であるが、実際は3月に最初のミーティングが開催されている。
といっても元々IEEE P802.3ctである程度作業が進んでおり、オマケにTask Forceのメンバーもほとんどど同じということもあって、確かにTask Forceは分かれたがものの、実質的な作業はあんまり変わらないのでは? という感じになっていた。実際、3月のミーティングで示された電話会議のスケジュールは以下のようなものだった。
ただし実際は、IEEE P802.3cwの事実上最初のミーティングは2020年6月まで伸びた。その最初に示されたTimelineが以下だ。
この案がそのまま通れば、2022年6月には標準化が完了するはずだったが、もちろんそんなスケジュールで進むはずもなかった。
以下が現時点でのTimelineであるが、2022年1月にLast Featureの提案が、2022年9月に技術的な変更がそれぞれ締め切られ、うまくいけば2023年8月に標準化が完了するはずだ。ということで見込みから1年遅れになっている。当初が楽観的過ぎた、という気もしなくもない。
OIFの400ZRをベースにPMDの仕様を定義した400G DWDM規格
スケジュールの話をおいておけば、以前も説明したように「400BASE-ZR」として策定予定になっている400G DWDM規格は、基本、OIFの400ZRをベースにしたものを使うが、ここで細かい仕様を見直すとともに、400ZRには含まれていないPMDの仕様を定義する必要がある。
もっともPMDの仕様より先に紛糾し始めた、というか検討が始まったのはむしろクロストークに関する議論だ。こちらでも触れたが、元となるOIFの400ZRの場合、DWDMの波長間隔として75GHzと100GHzの両方が検討された結果、75GHz帯はFuture Workとして見送りになったが、こちらで以前触れているように、400GBASE-ZRではこれも利用する方向で議論が行われた。
さて、75GHz間隔で64本の場合、何が問題になるかと言えば、WDM MUX/DEMUXをどう開発する(できる)のか? いう話が大きい。だが、これは、仕様を作る側からすれば、実はあまり問題にはならない。
もちろん、あまりに現実離れした仕様を作ってしまえば、実現できなくなってその規格が使われなくなるので、現実的に可能な仕様を定めなければ意味がなく、その意味で現実への歩み寄りが必要なのは間違いない。だからといって実際の量産コストについて、あまり真剣に考えても仕方がないわけで、このあたりは割り切りが必要だ。
PMDを75GHz幅にしたことで信号のCrosstalkの影響は?
話を戻すと、今回問題となったのは、むしろ75GHz幅にしたことによる信号のCrosstalkの影響である。このスライドなどが分かりやすいと思うが、チャネルの幅が狭まった結果として、ある波長の信号が75GHzの帯域に収まり切らずに、ほかのチャネルまで信号が広がることがあり、この結果として受信した信号が劣化する、という問題である。
この例で言うなら、WDMのMUXの手前にpre-mux Filterを入れてやることで、チャネルの範囲外に信号が広がらないように工夫すればCrosstalkは防げるという話だが、この信号が広がるという要因は、何もMUX部だけではなく、80kmものファイバーとなれば、ファイバー内の色分散もあるだろうし、もし途中にActive Ampが入った場合、そこでも発生し得る可能性がある。
単にMUXにFilterを入れましょうで話が終わるわけではなく、さまざまな要因でCrosstalkが発生し得るわけだ。もちろん対策を考える必要もあるが、その前にCrosstalkを定義するとともに、そのCrosstalkの強さ(というか、影響の大きさ)を評価するための物差しが必要という話が、Task Force内で出てきた。
ちなみに、このスライドは2020年12月2日に開催されたAdHoc Meetingでのスライドである。このAdHoc Meetingでは初めて、”IEEE P802.3cw Physical Layer Specification Optical Crosstalk Ad hoc“というPMDに関するプレゼンテーションも行われた。
ただ、この時点では「(PMDを含む)物理層を定義する必要がある」という話が出てきただけで、具体的な話はなされていない。まずはCrosstalk問題を話し合うのが先、というあたりだろうか。
「400GBASE-ZR」が方式としてきちんと固まるのは2022年の今頃か
さて、そのCrosstalkに関する物差しとして利用されることになったのが「EVM(Error Vector Magnitude)」である。そもそも400GBASE-ZRの場合、信号変調方式はDP-16QAMとなっている。このため信号は2次元配列になる格好であり、クロストークそのほかの影響で信号が歪んだ場合、2次元の本来あるべき位置と異なるところに信号が出現することになる。
もう少し分かりやすくしたのが以下で、理論上は左のように、データが出現する位置が、4つの象限にそれぞれ4カ所ずつ置かれることになる。
理想的な伝達状態であれば、中央の図のように理論値に近い場所にデータが集中して出現するが、伝達特性が悪いと右図のように信号が分散することになる。そこで、そのずれ具合(本来出現する場所と、実際の位置の距離を利用し、分散を取ったもの)をEVMとして取り扱うことで、うまく信号の劣化状況を取り扱える、という話だ。
このEVMとOSNRの関係、あるいはOSNとBERの関係なども示され、なのでOSNRやBERから目標となるEVMが算出でき、あとは具体的にEVMのターゲットをどの程度に設定すれば400GBASE-ZRの目標が達成できるか、そしてそのEVMターゲットを実現するためにどんなパラメーターを与えるべきか、といった議論が可能になったわけだ。
現在もTask Forceでは、こうしたパラメーターを設定する作業が行われている。最新のミーティング(2021年11月15日)では、Draft 1.2をベースに、細かな抜けの確認やパラメーターに関する討議(EVMのReference Model構築に関するものも含まれる)が続いている。
Featureに関してはもうあまり出てきていないので、2022年1月に最後のFeatureに関する議論が締め括られ、これをベースに2022年3月にDraft 2.0がリリースされる予定だが、このパラメーターに関しては、Technical Changeの期限である2022年9月までもつれ込みそうで、おそらくはスケジュールギリギリまで作業が続きそうだ。
また、現状はPMDに関する議論が全然見当たらないのも気になるところだ。2021年9月付の”802.3cw D1.2 missing baselines and TBDs“を見る限り、PMDに抜けがあるという記述は見当たらないので、何かしらが埋まって入るようだ。
ただ、そんなわけで、400GBASE-ZRに関して方式としてきちんと固まるのは2022年の今頃になりそうな感じである。逆にここで固まっていなければ、標準化そのものが廃止になりそうだ。