AppleのM1 Pro、M1 Maxを搭載した新しい14インチMacBook Pro、16インチMacBook Proの販売が開始された。本誌でも早速M1 Maxを搭載した16インチMacBook Proのレビュー、および動画レビューをお届けしてきた。
M1 ProとM1 Maxは、M1と比較してCPUの高性能コアは2倍、GPUはM1 Proが2倍、M1 Maxが4倍という規模になっていること。実際にM1 Maxの実機で確認したところ、確かにCPUに関しては約1.6倍、GPUに関しては約4倍の性能を実現していることが確認できた。ご興味がある方は上記の記事や動画をご参照頂きたい。
フルスペックとしては、M1 ProがCPUが10コア(高性能コア8+高効率コア2)でGPUが16コア、M1 MaxがCPUが10コア(高性能コア8+高効率コア2)でGPUが32コアだが、Appleの直販サイトでMacBook Proをカスタマイズしていくと、M1 Proには8コアCPU(高性能コア6+高効率コア2)+14コアGPUまたは10コアCPU+14コアGPU、M1 Maxには10コアCPU+24コアGPUというバリエーションが存在することがわかる。これらのバリエーションなぜ存在して、どのように選択すればいいのか、解説していきたい。
バリエーションのないM1、バリエーションが存在するM1 ProとM1 Max
以下の表1は13インチMacBook Pro(M1、2020)、14インチMacBook Pro(2021)、16インチMacBook Pro(2021)のそれぞれに搭載されているSoC(System on a Chip)の最大構成とバリエーションを表にしたものだ。
| M1 | M1 Pro | M1 Max | |
|---|---|---|---|
| 最大構成 | 8 CPU(4+4)/8 GPU | 10 CPU(8+2)/16 GPU | 10 CPU(8+2)/32 GPU |
| バリエーション1 | - | 10 CPU(8+2)/14 GPU | 10 CPU(8+2)/24 GPU |
| バリエーション2 | - | 8 CPU(6+2)/14 GPU | - |
これを見ると明らかなように、M1にはバリエーションは存在しておらず、M1 ProにはCPUコアとGPUコアをそれぞれ2コア削ったものと、CPUコアを2コア削ったものという2つのバリエーションがあり、M1 MaxにはGPUを8コア削ったものという1つのバリエーションがある。
まず知っておくべき事実は、これは半導体を製造する現場ではそうした設計を別に用意するのではなく、最大構成で設計し製造しておいて、その最大構成からいくつかのCPUコアやGPUコアを無効にするという形で用意されることだ。
SoCがサブストレートと呼ばれる基板に実装される際に、基板側の設定でCPUのこのコアを無効にしろ、GPUのこのコアを無効にしろという形で、フラグを立てて無効にする手法がとられている。
そのことは、別にAppleに限らず、どの半導体メーカーでも同じ手法を利用して製造している(もちろん例外もあり、別の設計が用意されることもある)。AMDだろうが、Intelだろうが、NVIDIAだろうが、ハイパフォーマンスの演算器を備えた半導体を製造するすべてのメーカーがこの手法を取り入れている。
「半導体の歩留まり」という製造時の都合
ではなぜ半導体メーカーはこうした手法でバリエーションを展開するのだろうか? いきなりその答えを言ってしまうと、「歩留まり(製造した製品の良品率)を向上させるため」だ。
おそらく本連載を含めて、本誌の半導体記事をお読み頂いている方にはそれでわかるだろうが、そうではない読者の方にはかなり丁寧な説明が必要になる。このため、ちょっと冗長だがそこを丁寧に説明していくので少しお付き合い願いしたい。
そもそもこうしたM1シリーズのような半導体はどのように製造されているのかをまず理解していこう。全部説明するには、それこそ記事が何本も必要になるほどなので、端折って簡略した説明になるが、概ね以下の図のような形で半導体は製造され、PCスマーフォンなどデバイスの組立工場に対して出荷されることになる。
半導体製造のプロセスは、主に前工程と後工程と2つに大きく分類される。ウェハと呼ばれるシリコンの板を製造する工程(この図で言うと①~③)が前工程で、そのウェハをパッケージと呼ばれるサブストレート上に実装し、必要に応じてヒートスプレッダなどを搭載していく工程(この図で言うと④~⑥)が後工程で呼ばれている。
半導体メーカーは、①のウェハの準備では、インゴットと呼ばれるウェハの原料の塊を買ってきて、直径300mm(12インチ)の円形の板に切り出す(その円形の板のことをウェハと呼んでいる)。次に、あらかじめ作成しておいたマスク、つまりは印刷時の下版のような半導体の回路を焼き付けてあるものを露光して、ウェハ上に回路を構成していく(②の露光)。そして露光が完了すると、ウェハ上に複数のダイから構成されているウェハができ上がる(CPUメーカーなどはこれがウェハですといって公開しているウェハはこの③の状態のウェハになる)。今回の例ではこの1枚のウェハに10個のCPUのダイが構築されたウェハが前工程で生成されたとする。
すると、次は後工程に入る。後工程ではまずウェハを、カッターなどを利用してダイ1つ1つに切り離す。次にそのダイを1つ1つを検査して、すべての機能が使えるのか、あるいは一部の機能しか使えないのか、あるいは全く使いモノにならないのかということを選別していく。そして良品と判別されたものは、次のパッケージへの封入工程に回ることになるが、この時に問題になるのが歩留まりだ。
⑤の検査工程では、CPUが使えるのか、使えないのかと同時に、元々想定していた機能が全部使えるのか使えないのかということを検査する。例えば、CPUが10コア構成だった場合に、10コア全部を使えるのか、10コアのうち2コアは使えず、8コアだったら使える製品、あるいは全部ダメかと検査する。
今回の図1の場合、1つのウェハで10個のダイを製造しているが、10コア全部が動く製品は3個しか作れていない。つまり歩留まりは30%という計算になる。歩留まりというのは半導体メーカーにとってコストに直結する大問題なので、歩留まりが30%程度なうちはとても出荷することができない。しかし、例えば、今回の例のように8コアでも製品として出荷できるとすると、10個のうち10コアを3個、8コアを4個とれる計算になるので、歩留まりは70%に上昇する。現代の半導体生産で70%ではとても出荷できるレベルではないが、少なくともさっきよりは圧倒的に改善したことがわかるだろう。
これが、14インチ/16インチMacBook Proに10コアのCPU、8コアのCPUがある理由だ。Appleの場合は自社の製品しか半導体を出荷していないが、例えば、Intelが先日発表した第12世代Coreのデスクトップ版でCore i9-12900Kが16コア(Pコア:8、Eコア:8)であって、Core i7-12700Kが12コア(Pコア:8、Eコア:4)であるのも全く同じ理由。Core i9-12900K(599ドル)に比べてCore i7-12700K(491ドル)が安価に設定されているのもそのためだ。
8コアのCPUになっているM1 Proを搭載した14インチMacBook Proが、10コアのCPUのM1 Proを搭載した14インチMacBook Proの価格がやや高めに設定さているのはまさにそうした仕組みの延長線上にあると考えられる。M1 Proの場合はCPUだけでなく、GPUのコア数も違うバリエーションが用意されているのでややこしいが考え方は全く同じだ。むろん、M1 MaxのGPUが最大は32コアであるのに対して、24コアのバリエーションが用意されているのも、まさにこの歩留まりという考え方が適用されてのものだと考えられる。その意味で、Appleは非常にまっとうな半導体製造ビジネスを行っていると言えるし、とても伝統的な半導体製造の考え方を適用しているということができるだろう。
逆に筆者が面白いなと感じているのは、オリジナルのM1にはこうしたバリエーションが用意されていないことだ。それが意味していることは、M1の歩留まりは最初からよかったことであり、TSMCの近年の製造技術の素晴らしさを受託しているメリットをAppleが享受しているということだと思う。
CPUやGPUの構成と値段差を勘案すると実のところコストパフォーマンスが高いのはM1 Max
このように、M1 ProとM1 Maxにバリエーションがある鍵は「歩留まり」にあるということは理解頂けたと思う。しかし、それは言ってみれば「メーカー側の理屈」であり、購入するユーザーとしては「そんなの関係ない」というのが正直なところだろう。
ではユーザーの視点で、どこに注意してどのグレードのM1を搭載したMacBook Proを購入するのがいいだろうか? そこは費用対効果で決めればいいだろう。以下の表2はメモリを32GB、SSDを512GBに固定したときのシステムの価格と、ベースグレードとの価格差を示している。メモリとSSDを併せているので、基本的にこの価格差が、ベースとなるM1 Pro(CPU8コア/GPU14コア)とほかのM1 Pro、M1 Maxとの価格差だと考えて差し支えないだろう。
| SoC | メモリ | SSD | 価格 | 最下位との差額 | 直下位との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 Pro(8CPU+14GPU) | 32GB | 512GB | 28万3,800円 | ー | ー |
| M1 Pro(10CPU+14GPU) | 32GB | 512GB | 30万5,800円 | 2万2,000円 | 2万2,000円 |
| M1 Pro(10CPU+16GPU) | 32GB | 512GB | 32万1,800円 | 3万8,000円 | 1万6,000円 |
| M1 Max(10CPU+24GPU) | 32GB | 512GB | 34万3,800円 | 6万円 | 2万2,000円 |
| M1 Max(10CPU+24GPU) | 32GB | 512GB | 36万5,800円 | 8万2,000円 | 2万2,000円 |
ベースとなるM1 Pro(CPU 8コア/GPU 14コア)からCPU 2コアが増えたM1 Pro(CPU 10コア/GPU 14コア)の価格差が2万2,000円、その中間グレードのM1 Pro(CPU 10コア/GPU 14コア)からフルスペックのM1 Pro(CPU 10コア/GPU 16コア)の価格差が1万6,000円だと考えると、CPUコア2つ分が22,000円、GPU 2つ分が1万6,000円とAppleが計算していることがわかる。
それをベースに考えると、ベースとなるM1 Pro(CPU 8コア/GPU 14コア)から、M1 Max(CPU 10コア/GPU 24コア)へは、CPU 2コア+GPU 10コアなので、2万2,000円(CPU 2コア分)+8万円(GPU 10コア分)=10万8,000円となるはずだが、実際の価格差は6万円、M1 Maxの最上位へはCPUが2コア増加と、GPUが18コア分増加なので、2万2,000円(CPU2コア分)+14万4,000円(GPU18コア分)=16万6,000円という計算になるところだが、実際には8万2,000円の価格差だ。
その意味では、想定される性能などから考えれば、実はM1 Maxを買った方が得という計算は成り立つ(あくまで数字遊びであることは認めるが……)。
そうしたことを勘案すると、予算に余裕があり、かつ筆者のような自営業で、PCの処理能力(たとえば動画のエンコード時間が短縮される、写真がより短い時間で処理される)が収入に直結する場合であれば、M1 Maxのどちらかを選ぶのがいいということは言えるだろう。それに対して、そうした処理はあまりしないけど、とにかくCPUができるだけ速くてコストパフォーマンスが高いのをと考えるなら、M1 Proの中間グレード(10コアCPU/14コアGPU)や、そもそもM1(CPU 8コア+GPU 8コア)を搭載した13インチMacBook Pro(M1、2020)で十分とも言える。
そうしたことを参照して、新しいM1 Pro/Maxを搭載した14インチ/16インチMacBook Proの選択の参考にして頂ければ幸いだ。







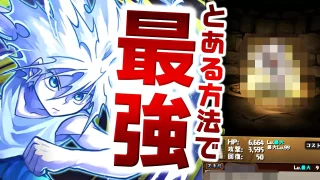












コメント