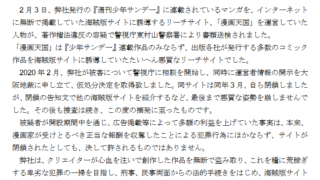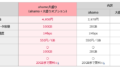2月21日から3月4日にかけて開催したウェブセミナー「CNET Japan Live 2022 社内外の『知の結集』で生み出すイノベーション」。社内の知恵を募集する社内ビジネスコンテストや、複数企業の強みを掛け合わせるオープンイノベーションなどに、今まさに取り組んでいる挑戦者たちをスピーカーとして迎えた、18のセミナープログラムで構成されたオンラインイベントだ。
2月28日は、沖電気工業(OKI)が4年間に渡って続けてきたイノベーション活動について紹介した。「全員参加型イノベーション」と銘打ち、今や世界標準として認められているイノベーション・マネジメントシステム(IMS)ISO 56002に則った「Yume Pro」プロセスを構築し、数々の実績を作ってきた同社だが、新しいことにチャレンジするための社内の意識改革や体制作りには多くの課題や苦労があったようだ。それらをどう乗り越えてきたのか、同社のイノベーション責任者を務める藤原雄彦氏が解説した。モデレーターは、CNET Japan編集長の藤井涼が務めた。

右上からCNET Japan 編集長 藤井涼、沖電気工業 執行役員 イノベーション責任者(CINO)兼 技術責任者(CTO) 藤原雄彦氏
挑戦する文化を醸成するために作った環境–1億円支援のコンテストも
企業活動において、今や利益を上げながら、SDGsやESGといった社会貢献性の重要度が高まっているとされる時代。そうした世界的な流れのなかで、OKIが社会課題へのアプローチを中心とするイノベーション活動の本格化に向けスタートを切ったのは2017年のことだ。同社代表取締役 鎌上信也氏の掛け声で検討が始まり、2018年にはイノベーション創出の仕組み「Yume Pro」を発足。「イノベーションが日常的な活動となる企業文化」を目指して、新規事業創出、既存事業の革新を進めてきた。
このYume Proは、のちにISO 56002として標準化されるIMSの内容を先駆けて採用した先進的な取り組みでもあった。2020年度にはイノベーション推進センターを発足し、「グループ全体にイノベーションプロセスを実装する」ことを目的に、Yume Proを「全員参加型のイノベーション」として全社に拡大。その活動の1つである社内ビジネスアイデアコンテスト「Yume Proチャレンジ」は、2018年度の初回が37件の応募だったところ、2021年度は254件にまで増加しているほどで、イノベーション文化の社内浸透は順調に進んでいる。

ISO 56002として標準化されているイノベーション・マネジメントシステム

「Yume Proチャレンジ」の応募件数は右肩上がり。2021年度は開催初年度の約7倍の件数に達している
とはいえ、そこに至るまでには数々の苦労もあった。2017年以降、IMSの導入に向けまずは現場の課題を探るべく、役員や新規事業の立ち上げ経験者など50人を対象にヒアリングを実施。1人につき1時間かけて話を聞き、イノベーション活動が当たり前の社内文化にするために乗り越えるべき課題を拾い上げていった。
これによって浮かび上がった課題が、「単品売り以外のビジネスモデル構築の方法を知らない」「顧客への提案能力が低い」といったもの。新規事業は成果が出づらく、「チャレンジしてもしなくても状況は変わらない」という意識も少なからずあった。また、チャレンジが推奨されても「どう行動すればいいのかわからない」という声が多く、顧客の価値にフォーカスできていない研究開発などにより、PoC(実証実験)レベルから脱却できない、あるいは「組織の縦割りが強く、協力してくれる人を集められない」という問題も。「新しいことは難しいからうまくいかない」といった物言いで諦めるような、イノベーションを阻む人も出現していた。

まずは50人の役員らにヒアリングを実施、課題を拾い上げた
それらを解決するために構築したのが、Yume Proというイノベーション活動のOS(オペレーションシステム)のようなもの。役員や部門の代表者自らが新しいプロセスでビジネスモデルを構築していくための方法論を学び、その知識を社内に広げていく教育活動を展開。さらに社外の専門家など、その道のエキスパートに支援を依頼して適切な助言を得られるようにし、社員全員がイノベーションに向けた行動を起こせるような環境を作り上げていった。

それらの課題の解決に向けた活動方法や体制、ビジョンを「Yume Pro」として規定
より具体的には、イノベーション推進の「伝道師」を担う「Yumeハブ」を各部門に設置し、互いの情報共有などを通じて横連携を強めた。また、年1回のビジネスアイデアコンテストとして「Yume Proチャレンジ」も開催した。Yume Proチャレンジは、大賞を受賞したアイデアには仮説検証等を進める資金として最大1億円の援助があり、大賞にならなかった場合でも数千万円規模の支援が得られることもあるという思い切った内容のコンテストだ。

学べる場を設け、社外の専門家から助言が得られる環境に

「Yumeハブ」や「Yume Proチャレンジ」などの仕組みを用意
同コンテストではOKIの強みを活かしたアイデアが求められるため、同社がもつ技術をデータベース化した社内ポータル「OKIPEDIA」も活用した。「OKIPEDIA」は、全社の技術情報を横ぐしで集め、各技術担当者の氏名と連絡先を掲載し、誰もが担当者に直接アクセスできるようにしたのもポイントだ。また、大企業では「現業が忙しく新しいことに取り組む時間がない」と感じる社員も少なくないが、同社では「Yume Proチャレンジに必要な時間を確保することをマネジメント層も了承」しているため、新しいことに積極的に取り組むためのハードルを下げる取り組みもしている。
重要なのは「ヒアリングを何度も繰り返し、仮説を磨いていくこと」
このようにしてイノベーション活動に参加しやすい環境を整えたわけだが、社員がアイデアを実現していくときにもう1つ重要になるのが、藤原氏によると「コンセプト構築プロセス」だ。以前は顧客からの要望に合わせて高品質の製品、ソリューションを開発する、という流れがほとんどだったが、昨今は、社会課題や中長期的な課題の解決のために、顧客自身が何に取り組めばいいのかわからない、といったことも多い。そのため、OKI自身が「顧客の課題を発見し、仮説を立て、コンセプトを検証する」というサイクルを繰り返していく「コンセプト構築プロセス」が開発の前段階で重要になってくるという。

新しいアイデアの実現には「コンセプト構築プロセス」が重要。「Yume Pro」はそのプロセスも包含している
近年は新規事業開発の際に、ビジネスの提供価値や顧客、販路、コスト、収益などの項目を整理するフレームワーク「ビジネスモデルキャンパス」を活用することが世界的に広がっている。が、「それらを埋めることが目的になっている」ことを藤原氏は指摘する。コストや収益ありきではなく、まずは「どんなお客様にどんな価値を、どのようにして提供するかが明確になることが大切」だとし、むしろ全ての項目を最初から埋める必要はないとも話す。そのためにも「顧客へのヒアリングを何度も繰り返し、仮説を磨いていくこと」が何よりも重要だと強調する。

ビジネスモデルキャンパスでは「どんなお客様にどんな価値を、どのようにして提供するか」を示すことが最も重要だとする
こうした取り組みによって、Yume Proチャレンジからだけでなく、数々のアイデアが生まれ、ビジネス化に向けて走っているプロジェクトもすでに存在している。その1つとして藤原氏が例示したのが「AIエッジロボット」だ。
AIエッジロボットは、自動で稼働している複数のロボットを、1人の人間が遠隔から監視、操作する仕組みで、SDGsで規定されている課題のうち「労働力不足」と「感染症拡大」をターゲットにしたもの。たとえばカメラを搭載した自走式ロボットの状況を逐一リモートから確認し、万一動けなくなった場合などにリモート操作で人間が対処する。ロボットの完全自動化はまだ難しく、予期せぬトラブルが発生すると施設全体の稼働が止まりかねない。人間が介入する余地のある設計にしておくことで、最小限の人材と労働力で、安定した運用が可能になるわけだ。

遠隔から複数のロボットを監視、操作できるようにした「AIエッジロボット」の仕組み

陸上の施設に限らず、洋上の監視などにも応用できる
また、OKIの強みである光通信(レーザー)技術を活かし、工場設備などの予兆保全を実現する「多点型レーザー振動計」もYume Proチャレンジ発のアイデアだ。施設や工場内の複数箇所に設置し、レーザーによって各設備の振動をリアルタイムで監視、通常とは異なる変化を検出することで機器の故障につながる前兆を発見し、予兆保全などに活かすというもの。これはSDGsの課題のうち、「老朽化問題」と「労働生産性」が当てはまる。

工場設備などの予兆保全を実現する「多点型レーザー振動計」
同じく労働生産性に該当するアイデアとしてプロジェクト化したのが、「行動変容・睡眠改善ソリューション」。「いつの間にか健康になる行動変容サービス」をコンセプトに、同社が長年研究を続けてきたという人間の行動分析アルゴリズムを応用したサービスを開発している。たとえば1日の行動をIoTデバイスなどでトレースし、行動内容によってスマートフォンにプッシュメッセージを送る、といったもの。エレベーターに乗ろうとしたときに「階段を使いましょう」とおすすめしたり、運動が少ない日の夕方に「運動しましょう」と提案するソリューション。すでに鹿島建設と共同で実験を始めているとのこと。

「いつの間にか健康になる行動変容サービス」

鹿島建設との共創が進行中。ユーザーの健康に向けた行動を促すメッセージを送るという
現場を知っている顧客やパートナーとの共創は不可欠
4年目にして、初年度の約7倍もの応募件数にまで増加しているYume Proチャレンジだが、審査では「顧客に仮説を持って行って、どれだけ声を集められているか」「OKIの強みが技術要素として入っているか」「メーカー目線ではなくエンドユーザー目線のアイデアか」といったところが判断基準になっているという。そうした点で応募アイデアの「ビジネスモデルの質が年々上がっている」ことを藤原氏自身や経営陣は感じている。
「行動したことで違った課題が出てくるだろうし、ピボットしなければならないかもしれない。それに気付いた人たちのモチベーションは俄然上がってくる。行動すること、やってみることは非常に大事だと改めて思う」と、社員が顧客に対してアクションを起こすことの大切さを改めて訴える同氏。
そして当然ながら、OKIのイノベーションも共創とは無縁ではない。新規事業の成功には「いろいろな知識を結集する必要がある。OKIはクラウド側よりエッジ側のAIに力点を置いていることもあり、現場を知っている顧客やパートナー様との共創なくしてはありえない」と前置きし、そういう意味でも「現場のデータをいかに活かすか」という視点は、これからもっと大事になってくると話す。
OKIには「現場でデータをとるためのセンシング、ネットワークなどが得意」という強みがあるため、これらを活用することで労働力不足や自然災害、交通問題などの社会課題を解決していきたいとする藤原氏。「現場を知っている方と一緒に取り組み、共創していく、そういう考え方でイノベーションを広げ、価値創出へ素早くアプローチできるようにしたい」という思いも語った。