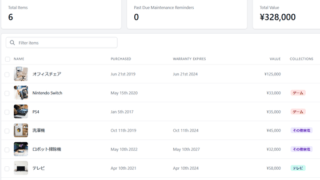こんにちは。
このシリーズの前回では、第二次世界大戦中、しかもまだ戦局もはかばかしくなかった1941年にリリースされた典型的なバカ歌がどんなにアメリカ国民を勇気づけたかというお話をしました。
今回は逆に、1930年代大不況のまっただ中でリリースされた、社会派ポピュラーソングの名曲、Brother, Can You Spare a Dime?(兄弟、10セント玉を恵んじゃくれねえか)を取り上げようと思います。
アメリカは確実に1930年代並みの大不況、ひょっとするとそれ以上にきびしい時代に突入しようとしているのに、アメリカ国民には精神的にも肉体的にもその困難に打ち勝つための備えはまったくなさそうだからです。

stacey_newman/iStock
それでは歌詞からご紹介していきましょう
They used to tell me I was building a dream, and so I followed the mob,
When there was earth to plow, or guns to bear, I was always there right there on the job
君は夢を建てているんだなんておだてられて、みんなについて行ったんだ、
耕す土地があれば耕し、銃を持たされりゃ持ち、いつもやるべきことをやってきた
They used to tell me I was building a dream, with peace and glory ahead,
Why should I be standing in line, just waiting for bread?
君は夢を建てているんだっておだてられて、しかもその先にゃ平和と栄光が待ってるとよ、
なんで今さら、パンを配ってもらうために行列つくって待ってなきゃいけねえんだ
そして、ここからがリフレインです。
Once I built a railroad, I made it run, made it race against time.
Once I built a railroad; now it’s done. Brother, can you spare a dime?
鉄道建設に駆り出されて、時間と競争するほど速い列車を走らせたのもオレだ
鉄道も造ったけど、完成すりゃお払い箱さ。兄弟、10セント玉を恵んじゃくれねえか?
Once I built a tower, up to the sun, brick, and rivet, and lime;
Once I built a tower, now it’s done. Brother, can you spare a dime?
天に届くほど高いビルを建てたのもオレだ、煉瓦やリベットやセメント使って
ビルも建てたけど、完成すりゃお払い箱さ。兄弟、10セント玉を恵んじゃくれねえか?
Once in khaki suits, gee we looked swell,
Full of that Yankee Doodle-de Dum,
軍服を着りゃ、なんとまあかっこよさに自分たちでしびれたぜ、
例のヤンキー・ドゥードルみたいな伊達姿でよ
Half a million boots went slogging through Hell,
I was the kid with the drum!
50万人の兵士たちが、重い軍靴を引きずって地獄を通り抜けてきたんだ
ほら、あのドラムを持ってたのが、オレだよ
Say, don’t you remember, they called me Al; it was Al all the time.
Why don’t you remember, I’m your pal? Buddy, can you spare a dime?
覚えてないかい? みんなにアルって呼ばれてたオレのこと? いつだってアルさ
なぜ覚えてないなんて言うんだ、マブだちじゃねえか、10セントぐらい恵んでくれよ
Once in khaki suits……以下くり返し
ビング・クロスビーの歌が決定版とされていますが、声が甘すぎてこの曲の迫力を殺いでいる気がします。
奴隷として連れてこられた黒人や、年季奉公を勤め上げれば自由人にしてやると言われてアメリカにやってきた流刑囚以外では、アメリカでこれほど生活苦のつらさを味わった人が多かった時期はなかっただろうという大不況だったのです。
ヴァースを省略しているのは残念ですが、トム・ジョーンズのいかにもウェールズの下層階級出身という歌いっぷりが、私が聴いたかぎりではいちばん合っていると思います。
トム・ジョーンズだって、実生活では比較的若いころからヒットソングを連発して、1930年代にアメリカ国民の多くが経験した突然の極貧状態は知らなかったはずですが。まあ、そのへんが、虚実ないまぜになった歌という芸術形式のおもしろさでしょうか。
1930~40年代に主としてキャバレーで活躍したグレナダ出身の黒人シンガー、レスリー・「ハッチ」・ハッチンソンはスローバラードが得意な深みのあるバリトンなので、この人ならぴったりだろうなと思いますが、ディスコグラフィーでは探し出せませんでした。
さて、私は1920年代末と世相が似てきたと思っている現代世界に戻りましょう。
銀行危機は去ったのか?
今年も、もう4分の1が終わりました。そして、3月上旬に勃発した中堅銀行の連鎖破綻以降は、金融市場も小康状態を取り戻したように見えます。
そして、2022年を通じてS&P500株価指数の足を引っ張ってきた大手ハイテク銘柄が、たった3ヵ月ですさまじい株価上昇を演じて、なんと時価総額トップ15銘柄だけで1兆8000億ドルも時価総額を増やしました。次の2枚組グラフの上段です。
残りの約485銘柄の時価総額減少が、誤差の範囲内に思えるほどの大躍進です。でも、下段をご覧ください。FAANG5社のうちで、そのときどきで売上増加率がちょうどまん中の3番目になる企業の増収率は激減し、0%に限りなく近づいているのです。
成熟した大企業の利益率が急上昇することはめったにありません。(急降下はありますが。)増収率が下がっているということは、利益総額の増加率もどんどん限定的なものになっているということです。
「これでまた、ハイテク大手主導のブル相場が再来する」と考えるのは、あまりにも楽観的でしょう。ハイテク大手に一本かぶり状態の株価回復は、花形企業の増収増益率が低下しているだけに、非常に危険です。
株式市場の堅調さとは裏腹に、経済の血液とも言うべき銀行預金の減少幅は、アメリカ史上最高額、すなわち世界史上最高額に達しています。
コロナ危機に突入する直前の2019年に月間で4500億ドルの激増があったので、このくらい預金が減ったほうがバランスが取れると思われるかもしれません。でも、当時激増した預金はそのまま眠っていたわけではなく、さまざまな方面に投融資されているはずです。
そうした投融資先の代表が、ヘッジファンドが不振を極めている昨今、金融業界全体の稼ぎ頭になりつつあった未上場株ファンドや特別買収目的会社(SPAC)でしょう。
未上場株自体はその名のとおり未上場ですが、さまざまな未上場株を買い集めたファンドの中には上場しているものもあり、そのうち最大手5社のレバレッジ(テコの原理で借金によって業容を拡大すること)は、次のグラフのように急上昇しています。

未上場株ばかりを集めたファンドに、なぜこれほど大きな資金需要があるのかと首を捻りたくなる債務の激増です。前回の未上場株ブームが起きていた2014~15年に3000億ドル強だった純債務額は、直近で7000億ドルと2倍以上に膨らんでいました。
預金総額の激減で投融資の縮小を迫られた銀行は、おそらく未上場株ファンドやSPACのような冒険的要素の濃い投融資先から資金を引き揚げていくでしょう。
そこで資金繰りができなくなって破綻する未上場株やSPACが出てくるのは、アメリカ金融市場にとってむしろ健全な変化になるだろうと私は見ています。
もともとしろうと投資家を欺して出資させて上場直後の高値で売り抜けようという意図が見え透いた銘柄が多く、軒並み上場直後の高値から80~90%台の値下がりとなっていたサイクルが資金難で促進されれば、欺される人の人数やだまし取られる金額が減るからです。
ほんとうに怖いのは地銀の資金難
そう簡単に済ませてはいけないのが、地方銀行株ETFの価格がシリコンバレーバンク破綻直後の底値を割りこんだという事実です。
預金の激減、株価急落で地方銀行の資金繰りが苦しくなると、地場産業の中小零細企業への融資が、滞りがちになります。
ご覧のとおり、大手から中堅までの銀行融資は、大手企業向けのほうがずっと多く、総資産10億ドル未満の中小銀行の融資だけは中小企業向けのほうが多くなっています。
そして、利益総額では大手・中堅企業のほうが中小零細企業より多いのですが、勤労者の大半は中小零細企業に勤めているのです。
贈収賄が合法化された第二次世界大戦後のアメリカでは、巨額のロビイング投資ができる基幹産業の大手企業にとって有利で、それができない中小零細企業に不利な方向にどんどん法律や制度が歪められてきました。
その結果、アメリカの民間企業従業員の週給は、現在にいたってもまだ1973年ニクソン大統領辞任直前の水準に到達したことがないという状態なのです。
この先も地方銀行の破綻が相次ぐというような事態になれば、現状でも苦しいアメリカの勤労者たちは、さらにきびしい経済環境に置かれることになるでしょう。
アメリカは異常に若死にする人の多い国
世界中どこでも人生最大の危機は1歳未満の乳児期であり、そこさえ切り抜ければかなり多くの人が順調に60代、70代まで生き抜くことができると言われています。
ところが、先進諸国の中でも最大で、世界一豊かな経済を運営してるはずのアメリカが、この乳児期を無事に切り抜けたのに、その後若くして亡くなる人が異常に多い国なのです。
右側のグラフでご覧のとおり、75歳に到達した人たちのあいだでは、とくにアメリカ国民の平均余命が短いという兆候はありません。
ところが、左側の5歳児が40歳に到達する前に亡くなってしまう確率で言えば、アメリカは他の先進諸国の約4倍も夭折する人の多い国なのです。
こちらのカーブをこまかく見ると、15歳ぐらいまではそれほど大きな違いはなく、16歳頃から差が出始め、18~19歳になると急上昇が始まることがわかります。
この差が開き始める年齢から判断すると、アメリカ国民の中に早死にする人が多いのは、急性慢性のアルコール・薬物中毒、自殺をふくむ自傷行為による死、そして殺人、傷害致死などの暴力の被害に遭ったための死が多いからだろうと想像がつきます。
その推測が正しいことは、次のグラフが証明しています。

コヴィッド元年に当たり、1~44歳の年齢層でも8900人がこの「大疫病」で命を落とした2020年でも、この年齢層で最大の人命を奪ったのは約5万人の薬物中毒であり、2~3位はともに2万2000~3000人の犠牲者が出た自殺と自動車事故、4位が約1万9000人の殺人でした。
やっと5~6位に下がった段階で、1万6000~7000人が亡くなった心臓病と癌という病気が死因となっています。
急性の薬物・アルコール中毒死、薬物・アルコール依存症が主因となる衰弱死、自殺の3つをまとめて、絶望死と呼んでいます。アメリカでは青少年期から壮年期に絶望死で亡くなる人が多いので、先進国としては異常なほど夭折人口が多くなっているのです。
急性中毒死にしても、慢性の依存症による衰弱死にしても、はっきり自殺をする「勇気」はないけれども長年にわたって常用していれば死期を早めることがわかっていても止められないという意味では、緩慢な自殺と言ってもいいでしょう。
絶望死の中でも薬物中毒と自殺が激増中
現代アメリカ社会は、そこまで病んでいるのです。その経年変化を見ていると、非常に気がかりな傾向が表れています。
3つの絶望死に、殺人や傷害致死などの対人暴力による死を比較すると、アルコール中毒死は横ばい、対人暴力死は減少傾向にあるのに、薬物過剰摂取死は1980年代から一貫して激増中で、自傷行為による死は21世紀に入って激増の気配を見せています。
アルコール中毒死は、郡別実績が最大の郡の犠牲者数を示す上髭の頂点は年によって変動しますが、全国平均と郡別実績の中の中央値は人口10万人当たりで3~4人という数値がほとんど変動していません。経年変化は皆無に近いと考えていいでしょう。
意外な気がしますが、殺人や傷害致死などの対人暴力の犠牲者数は1980~90年代を頂点に減少に転じていたようです。
第75百分位(上から26%目)を上辺、第25百分位(上から76%目)を下辺とする長方形がどんどん底浅になっているのはアメリカ全土に存在する郡の半分がこの狭い範囲内に収まっていた、すなわち郡ごとのばらつきも非常に小さくなっていたことを意味します。
ただし、ここでもコロナ騒動によるロックダウンやワクチン接種の強要などがマイナスの影響を及ぼしていることは否定しがたいようです。
ロックダウンやマスク着用の強制などが、市民生活を不安定にしていた2020年5月25日に、それほど重大とも思えない犯罪で現行犯逮捕されたジョージ・フロイド氏が警官数名による不必要な暴行を受けて亡くなりました。
それ以来、「黒人の命も大切だ(Black Lives Matter、BLM)」運動の激化もあり、それに反対する勢力との暴力的な対決もありで、沈静化傾向にあった大都市の殺人犠牲者数が激増しています。
2022年の大都市殺人犠牲者数ランキングでは、ニューオリンズの74.3人を始めとして、セントルイス、ボルチモア、デトロイト、メンフィス、クリーブランドの6都市が、2014年の郡別殺人犠牲者数10万人当たり最大値の約37人をはるかに上回る数値となってしまいました。
アメリカという国では、殺人や傷害致死などの対人暴力による犠牲者の数は、かなり鎮まったように見えても何かのきっかけさえあれば一挙に噴出するマグマのようなものだと思います。
そして、20世紀中はほぼ横ばいだった自傷行為による死が、2000~14年では上から強い力によって引っ張り上げられたように郡別実績の最高値、75百分位と25百分位で構成される長方形、郡別実績の中央値、全国平均値が揃って上昇しています。
とくに、郡別実績の最高値は他の3つのカテゴリーよりはるかに高い人口10万人当たり100人近い数字となっていて、自殺者数が激増している郡の存在を示しています。
少なくとも2014年までは徐々に減少していた殺人に代わって自傷行為による死が増えていたとすれば、具体的に対象となる人物を特定できない殺意が、自分に向けられていたのではないかという気もします。
最大の脅威は薬物過剰摂取死の激増
しかし、なんと言っても最大の脅威は、薬物摂取死の激増ぶりです。そのすさまじさは、次の地図グラフでおわかりいただけるでしょう。
なんと、1980~2014年の34年間で3.5倍未満であれば横ばいと変わらないほど小さな変化だということになっているのです。いちばん濃い色で塗られた郡ではこの間に50.5倍から84.7倍というとんでもない増え方をしていました。
具体的には、ウエストバージニア、オハイオ、インディアナ、ケンタッキーの4州が交わるあたり、ラストベルト(錆びついた帯)と呼ばれた地域が最大の密集地帯です。
製造業全盛期の繁栄が過ぎ去ってから、時代に取り残されままさびれ続けている地域ですが、そこからイリノイ州を隔てて西に行った、ミズーリ州東側のイリノイ州との州境地帯も似たような土地柄です。
ミシシッピ州北西部とオクラホマ州北東部は、それぞれ人種的マイノリティ問題を象徴するような歴史を抱えています。
州全体が貧しいミシシッピ州の中でも、北西部は南北戦争後奴隷身分からは解放されたものの、遠くに移住するための交通網も資金もなく、解放前と同じ土地に住み着いたままの黒人が多かった土地です。
シェアクロッパー(折半小作人)と呼ばれて、白人の旦那方に奴隷時代よりひどい搾取を受けてきた頃のハンデを未だに取り返すことができず、貧困にあえいでいる黒人世帯が多いのです。
オクラホマは準州だった頃には全土をインディアン居留地にするはずでしたが、土地を欲しがる白人世帯がなだれ込んできたために、結局インディアンが半放牧的な遊動生活をするにはあまりにも狭い土地しか残らず、貧困なインディアン世帯の多い地域になりました。
大都市の薬物中毒犠牲者は1980年頃にはもうかなり多くなっていたという事実もありますが、34年間での薬物中毒犠牲者激増地域には、大都市圏の享楽的な退廃はほとんどありません。
おそらく、1980年代から90年代半ばまでは非合法薬物の密売組織なども存在しなかったような土地ばかりでしょう。
劇的な変化は、1995年にアメリカ食品医薬品局(FDA)が鎮痛剤の許認可基準を大幅に緩めて、パデュー製薬のオクシコンティンというオピオイド(アヘンもどき)を医師の処方箋さえあればかんたんに買える薬にしてしまったときに起きました。
患者に「よく効く鎮痛剤を」と求められると、オクシコンティンの依存症形成リスクの高さを知っている医師は、何度も同じ患者に処方箋を書いてそのたびに多額のキックバックがもらえるオクシコンティンを最優先で勧めるようになります。
オクシコンティンだけでも、あちこちの医師に処方箋を書いてもらって同時に大量を服用すれば、致死量になります。また依存症を形成してしまえば、次第にもっと強い刺激を求めて、フェンタニルなどの危険性の高いオピオイドを混ぜて服用するようになります。
そうなると、非合法薬物の密売組織も商売になるので進出します。アメリカの貧困地帯には薬物中毒犠牲者の多さという特異なお荷物がついて回るのは、製薬会社から巨額のワイロをもらっているFDAなどの「監督官庁」が製薬会社を儲けさせる行政に徹しているからです。
もちろん、自分の懐さえ温まるのであれば平然と薬物依存症患者を乱造する処方箋を書きまくる悪徳医師が、アメリカでは標準的な医師の姿であることも見逃せませんが。
肥満もまた致命的な水準に
突然話が変わると思われる方もいらっしゃるでしょうが、私が外資系証券会社のアナリストとして欧米の機関投資家回りをしていた頃、客先に連れて行ってくれたイギリス人セールスマンが1930年代大不況のドキュメンタリーを見ながら言ったことが忘れらません。
「今度あんな大不況が来たら、東アジア諸国は立ち直ってもっと繫栄するだろうけど、欧米諸国は再起不能で没落していくだけだろうな」とつぶやいたのです。
「なぜ?」と訊くと「プロポーションを見りゃわかるじゃないか」ときました。日本人の中でも胴長・短足にかけては余人の追随を許さない私としては、胴長・短足に何か大不況時に有利な点があるのかと興味深々で「プロポーションのどこが?」と訊き直しました。
「ボロは着てるけど、今の東アジアの人たちみたいにすっきり痩せてるからさ。あれなら過酷な肉体労働にも耐えるし、ムダに食費がかさむこともないだろう。我々も若い頃はぶくぶく肥ったアメリカ人を軽蔑してたけど、クルマ社会化したら同じように太ってしまった」
彼自身は中年イギリス人にしては珍しく贅肉のないすっきりとした体形でしたが、そう言われてみれば確かにイギリス人の同僚や商売敵たちには、ちょいポチャからかなポチャの人たちが多かったのです。さすがに大手金融機関には明らかな肥満体はまずいませんでしたが。
その肥満体の人たちの多さですが、現在ただ今のアメリカ社会は、我々がそんな会話を交わした頃よりさらに数段深刻になっています。2011年時点でさえ、次の地図グラフでご覧いただくとおりでした。
そもそもアメリカでは肥満の定義自体がだいぶ「きびしく」なっています。日本ならBMIが25以上なら全部肥満ですが、アメリカでは25以上30未満は「太りすぎ(Overweight)」と呼んでいて、BMI30以上の人だけを肥満としています。
その定義でも、2011年の段階ですでにアメリカ中探しても肥満体の住民が20%未満という州も、特別区も、自治的未編入領域なる不可解な「領土」も存在しませんでした。
しかし、この時点では州民の25%未満が肥満体という州もかなりの数存在していた一方、35%以上が肥満体という州はまだ存在しなかったのです。
たった10年でどれほど変わるものか、ご覧ください。
アメリカ全土50州、1特別区、3自治的未編入領域全部を眺め渡しても、住民の25%未満が肥満体という行政区画は、ワシントンという合衆国政府の首都1市だけからなるコロンビア特別区のみになってしまいました。
そして今や、住民の30%以上が肥満体という行政区画が圧倒的な多数派になっています。その中には10年前には存在しなかった住民の35%以上が肥満体という州が17、自治的未編入領域がプエルトリコとバージン諸島の2つになっています。
ウエストバージニアとケンタッキーにいたっては、住民の40%以上が肥満体です。
また、黄色の楕円形でかこった部分にご注目ください。薬物過剰摂取死の犠牲者が異常に増えた地域がすっぽりこの中にふくまれると同時に、肥満率も高い州が揃っているのです。ある程度の所得水準を達成した人たちにとっては、肥満は自己管理の問題です。
でも、アメリカでは肥満率の高さも、薬物過剰摂取死の激増も貧困問題なのです。そしてそれは、連邦議員レベルの政治家たち、高級官僚、大手企業がグルになって自分たちの得になるように法律制度を変えていくかぎり、永遠に解決しようのない貧困問題なのです。
アメリカでは5歳児の4%が40歳に到達する前に亡くなってしまうというグラフを見たとき私が直感したのは、アメリカは25人1チームの団体競技でひとり永久退場のままゲームをしているようなものだということでした。
アメリカ全土を覆う肥満率の高さを見ていると、20人1チームの団体競技でひとり永久退場のままゲームをしているようなものではないかと思うようになりました。
今度の大不況がアメリカにとっては1930年代大不況よりはるかに悲惨なものになることは、間違いないと考えます。
■
増田先生の新刊「人類9割削減計画」が発売中です。ぜひご覧ください。