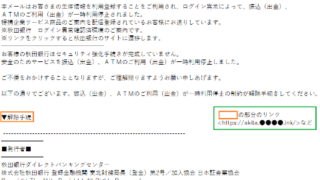本誌CNET Japanが主催するオンラインセミナー「CNET Japan Live 2023」が、2月1日から28日までの1カ月間にわたって開催された。テーマは「共創の価値を最大化させる『組織・チーム・文化づくり』」。新規事業開発や共創、あるいは組織風土の改善などに取り組んできた企業が、その経験をもとに成功のヒントを明かす20のセッションからなるイベントだ。
14日には、全社で全員参加型イノベーションの実現に取り組んでいるOKI(沖電気工業)によるセッションが行われた。同社執行役員で、イノベーション責任者(CINO)でもある藤原雄彦氏が、新規事業を生み出す土壌作りのために行ってきた5年間の活動内容を総括し、イノベーションに向けた組織変革を実現するためのヒントを提示した。
イノベーションによる価値の創出はビジネスにおいて必然

沖電気工業株式会社 執行役員 兼 イノベーション責任者 藤原雄彦氏
藤原氏が最初に強調したのは、「イノベーション」は「マーケティング」と並び、企業にとって当たり前の活動であるという点だ。経営学者であるピーター・ドラッカーの「ビジネスに必要なものはマーケティングとイノベーション」という言葉を引用し、「イノベーション」はバズワードでも、全く新しい考え方でもなく、あくまでマーケティングなどと同様に「企業が継続して行うべき活動」であると説明した。
マーケティングは「顕在化した顧客課題を解決」するもので、イノベーションは「潜在的な顧客ニーズを探索し、顧客と共に価値を創造」するものであるとして、それぞれ異なる役割がある。近年は、SDGsやESGなど社会貢献が企業に求められており、それに伴って「社会課題の解決こそが利益につながる」状況だからこそ、イノベーションの重要性はますます高まっているという。

企業活動においては社会課題へのアプローチが重要
そうした中で、OKIは2018年よりイノベーションに向けたさまざまな取り組みを進めている。例えば、「イノベーション・ダイアログ」と題し、経営層と社員が2週間に1回、直接対話する時間を設けたり、社内のイノベーション実践者の声を直接届ける「Yume Proフォーラム」を開催している。
また、ビジネスアイデアコンテスト「Yume Proチャレンジ」を毎年開催しており、アイデアの事業化に向けたブラッシュアップを支援する「加速支援者」や、各部門の横結合を促進する“伝道師”「Yumeハブ」などの仕組みでイノベーションの全社実践を強力にサポートしている。
そして、「ISO 56002」として標準化された「イノベーション・マネジメントシステム(IMS)」を導入し、基本方針や規程、プロセスガイドラインを策定する仕組みも構築した。

OKIのイノベーション実践を支える多角的な取り組み

標準化されたイノベーション・マネジメントシステム(IMS)を採用
現場のイノベーション活動を強力にバックアップする体制の構築
しかし、最初からすべての仕組みや体制が整っていたわけではない。OKIは組織として目指すべき姿を描きながら、試行錯誤を重ね、着実に改善を積み重ねてきた。
2017年当初の取り組みは、まず新規事業開発を経験したことのある部長職以上と全役員を含む50名にインタビューを実施し、イノベーション活動を阻む要因を探るところから始めた。
そこから見えてきたのは「新しいことをやってもやらなくても変わらない」企業文化であること、「OKIの目指す姿」の方向性が部署によって異なっていること、受注型の案件が多く顧客への提案能力が磨かれていなかったこと、製品を売るという単純な形以外のビジネスモデル構築の方法を知らないこと、といった組織の課題を浮かび上がらせた。

経営層にインタビューし、浮かび上がった課題
そういった課題に対し、同社はISO 56002に則ったIMS「OKIイノベーション・マネジメントシステム」、通称「Yume Pro」を策定した。イノベーションによって社会課題や顧客の問題を解決するため、「イノベーションが日常的な活動となる企業文化」を目指し、グループ全体にイノベーション・プロセスを実装し、さらに同社グループのリソースをフル活用できる体制を構築するというコンセプトを掲げている。また、「矢印革命」と称し、受注開発型の企業から提案型の企業への変革を目指している。

課題解決に向け、組織体制の変革を図る
しかし、現場の社員からは、「新しいことに取り組むべきだと言われても、どう行動したらよいかわからない」という声や、「協力者を集められない」、「既存事業が忙しく、新しいことに取り組む時間がない」といった意見も寄せられている。そこで、同社では「Yume Pro」プロセスを最大限に活用するさまざまな仕掛けで、これらの課題の解決に取り組んできた。

「行動の仕方がわからない」という声に対しては研修やワークショップなどを充実させた
まずは、グローバルなイノベーションの考え方を社員に学んでもらうための研修・ワークショップを開催し、専門家によるアドバイスが得られる機会を設けた。また、情報セキュリティや内部統制を含む既存の業務システムにIMSを取り込み、新しい取り組みの手順・運用を確立している。

「協力者を集められない」ことについては、「Yumeハブ」や「Yume Proチャレンジ」を制度化し、社内DBも整備
組織の縦割りが原因で協力者を集められないという問題に対しては、各部門から選定したイノベーション“伝道師”の交流の場として「Yumeハブ」を設置し、優秀なアイデアに最大1億円の予算がつくビジネスアイデアコンテスト「Yume Proチャレンジ」を制度化。さらに、保有技術などをデータベース化して社内リソースを把握・活用できる「OKI PEDIA」という情報ポータルも整備している。

マネジメント層の理解も進め、従業員が新しいことに取り組む時間を確保
また、「新しいことに取り組む時間がない」という声に対しては、イノベーションの必要性を社内外へ情報発信しているほか、従業員が「Yume Proチャレンジ」に取り組む時間の確保をマネジメント層が理解するよう意識統一を徹底している。中長期的な目標を組織内で共有し、熱意を醸成する活動も展開している。
OKIのイノベーションは「実践モード」に
OKIがここまで環境づくりや支援体制を重要視しているのは、いくら仕組みができたとしても、それにチャレンジする人材に実力が伴わなければ絵に描いた餅になりかねないため。
それを藤原氏は「プールに水が入った状況」に例え、「プールにどんなきれいな水を張っても、泳ぎ切れるスイマーを作っていかなければ意味がない」と話す。事業化までやりとげる人材を育てるには、従業員が確実に行動を起こせるプロセスガイドライン、イノベーション教育、専門家による加速支援といった多角的な支援が必要と考え実践している。

「泳ぎ切れるスイマー」を育成するための環境作りに注力
また、グローバルに活用されている価値、顧客、コスト、収益といった9つの要素を1枚のシートに整理し、ビジネスモデルを客観的な視点から検討していく「ビジネスモデルキャンバス」という手法について解説した。OKIでももちろん活用しているが、藤原氏は注意を促している。
だいたいの人は9つある要素のうち書きやすいところから埋めたくなる。日本企業の多くは3つ目の“どうやって”から入っていきがちなのだとか。とくに製造業では、十分な技術力があるだけに「最初にモノを作ってしまう」ことで、余計なロスが発生することも少なくない。
しかし、書き方には「順序がある」と同氏。「まず“誰(顧客)”に、“何(どういう価値)”を提供するのか、そしてそれを“どうやって”やるのか」が重要で、その順番で記入していくのが正解。課題を見つけ、仮説を立て、そのうえで「何度も顧客にヒアリングを繰り返し、解像度を上げる」。それを「アジャイルに続けていく」ことが重要だと語る。

ビジネスモデルキャンバスは「誰に」「何を」「どうやって」の順番で書くべきだという
人事評価でも「チャレンジする人が評価される」仕組みを
2018年から続けている「Yume Proチャレンジ」の応募件数は、初年度の37件から2022年度には319件と、年々増加している。同社の強みであるセンシング、ネットワーク、リアルタイム、ロボットといった領域におけるアイデアが中心となっている。イノベーション意識の高まりはもちろんのこと、最も優秀なアイデアに1億円、2位や3位でも数千万円という予算面の充実した支援が、応募者増の一因となっているようだ。
また、既存事業と比べて、すぐに大きな成果を出しにくい新規事業は人事評価の面で不利とされるが、OKIでは「チャレンジする人が評価される仕組み」になってきているとのことで、同社のイノベーションの加速に貢献していると考えられる。
藤原氏によると、IMSにあるデザイン思考のプロセスはGAFAのような大手プラットフォーム企業でもすでに活用されており、今や「グローバルな共通言語」となっている。企業間でも共通言語を用いることで、コミュニケーションロスが少なく、共創がより進みやすくなる。「多くの企業と共創し、共創パートナーとともに社会の大丈夫をつくっていきたい」というのが同氏の願いである。