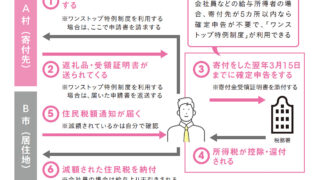Bill Chizek/iStock
ロシアのウクライナ侵攻を契機に昨今、日本の安全保障をめぐる論議が活発である。政府は先ごろ閣議決定した「骨太の方針」なるものに、防衛力を「5年以内に抜本的に強化する」と明記した。
こうした論議のなかで、「専守防衛」という言葉をしばしば聞く。この言葉はもともと政府の側が使ったものだが、いまでは政府の姿勢に反対したり、疑問を呈する立場から使われることが多い。例えば、6月3日の「防衛予算の増額、冷静さ欠く議論は危うい」と題した毎日新聞の社説には、こんな一節がある。
「確かに、安全保障環境の変化に応じた防衛力の整備は必要だ。ただし、専守防衛との整合性や、さまざまな政策の中での優先順位などを考慮した、冷静な議論が求められる」
「敵基地攻撃能力」や、その言い換えである「反撃能力」についても、「専守防衛」との関連で議論を呼んでいる。例えば、5月30日の朝日新聞朝刊で、佐藤武爾・編集委員が書いた長文の解説記事の見出しは、「空文化する『専守防衛』 核心避け、「敵基地攻撃」呼び方論争」である。
憲法9条は「戦争放棄」と「戦力不保持」を謳う。その解釈の変遷には触れないが、かつては自衛隊の存在そのものを違憲としていた人々が、今日、自衛隊を容認する根拠の一つが「専守防衛」であるように思える。「専守防衛」という言葉によって、日本の自衛隊の装備や活動に枷をはめることによって、護憲の立場を維持しようとするのである。
先にも述べたように、もともと「専守防衛」は政権側が言い出したものだった。だから、朝日新聞の解説記事が、岸田政権が打ち出した「防衛力の抜本的強化」に対して、「空文化」という文脈で、「専守防衛」を語るわけである。
政権側は「防衛力の増強は専守防衛を逸脱するものではない」と主張する。他方、その「空文化」が指摘される。では、そもそも「専守防衛」とは、いかなる意味なのか。『防衛白書』(2006年度版)は、次のように定義している。
相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢
私は防衛問題の専門家ではないし、ましてや具体的な防衛戦略について語る知識はない。だが、この定義には強い違和感を覚えていた。「何かおかしい」という感じである。
少し前に刊行された本だが、樋渡由美『専守防衛克服の戦略――日本の安全保障をどう捉えるか』(ミネルヴァ書房、2012年)を読んで、私の感じた違和感の正体が分かった。
著者は上智大学教授。安全保障問題を軸に戦後の日本政治史を研究している方である。本書の入り口で、著者は「専守防衛」という考え方の問題点を端的に2点指摘している。
まず、「専守防衛」の前提にある「攻撃と防御が機械的に区分できる」という考え方がおかしい。テクノロジーの発展とともに新たな兵器が登場し、攻撃・防御のあり方が大きく変化している現代、この前提は通用しない。今日、攻撃力をもたなければ有効な防御や抑止はできないというのである。
さらに、「専守防衛」の考え方は、こうした攻撃力をもっぱらアメリカの軍事力に求める。つまり「専守防衛」は日米同盟と不可分なのである。世界最強の軍事力を保有し、沖縄をはじめ日本国内各地に基地を持つアメリカとの同盟を前提にしなければ、そもそも「専守防衛」は成り立たないにもかかわらず、この点が国民に明確なメッセージとして伝わっていないという。
後者について、従来から、日本有事の際、「自衛隊は盾、米軍は矛」といった比喩が語られてきた。私は、それこそ「矛盾」ではないか、と思っていた。感覚的に言うと、「専守防衛」を掲げつつ、なんだ「攻撃」はよその国に頼むのか、虫がよすぎないか、といったところである。
政府は防衛費を5年以内にGDPの5パーセントにする目標を掲げる。多くの人が批判するように、私も本末転倒と考える。これからの日本の安全保障を考えるには、自衛隊にはいかなる装備が必要なのか、有事の際、日米同盟をいかに運営していくのか、といった具体的な問題を検討していくことが入り口になるべきだろう。
だが、「専守防衛からの逸脱」「専守防衛の空文化」を指摘し、「日本は平和外交に専念せよ」と主張して事足れりとする言説は、ある意味で無責任ではないか。むろん外交が大切なことに異論があるわけではない。だが、安全保障問題において、「専守防衛」は、それを掲げれば皆がふれ伏すような「黄門の印籠」ではない。
■
奥 武則
法政大学名誉教授。近現代日本のジャーナリズム史を研究。著書に『ジョン・レディ・ブラック――近代日本ジーナリズムの先駆者』(岩波書店)、『増補 論壇の戦後史』(平凡社ライブラリー)など。