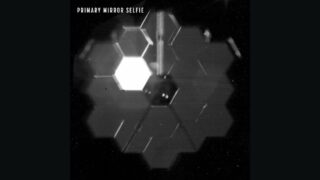東京二期会とリンツ州立歌劇場の共同制作:モーツァルト『魔笛』(宮本亞門演出)の再演を9月9日に東京文化会館で観劇。初演を観たのはついこの間という気がしていたが、2015年なので早くも6年が経っている。登場人物が現実世界からゲームの世界へ入っていく、という亞門さんの斬新なアイデアには最初驚かされたが、今ではすっかり愛されるプロダクションとなり、リンツでは30回以上も上演されている。

公演二日目の9月9日はBキャストの歌手たちが登板し、ザラストロ斉木健詞さん、タミーノ市川浩平さん、夜の女王 髙橋維さん、パミーナ盛田麻央さん、パパゲーノ近藤圭さん、モノスタトス升島唯博さん、二期会合唱団が活躍した。指揮者はリトアニア生まれの気鋭の若手ギエドレ・シュレキーテ、オーケストラは読売日本交響楽団。
有名な「序曲」で、この演出の設定が語られる。やんちゃな三人の少年が家の中で遊んでいて、おじいちゃんを困らせている。そこにリストラされたお父さんが帰宅。息子たちに向かってカバンを振り回して暴れ出す。お母さんが買い物袋をたくさん抱えて帰ってくる。大きな宅配ピザが届く。お父さんとお母さんはケンカして、お母さんはアタッシュケースを持って家を出てしまう…普通のテンポだと7分半くらい(クレンペラーだけ倍近くかかる)の序曲の中で、一家が崩壊寸前の危機であることが描かれ、リストラ父さんはゲーム画面の中に飛び込んでタミーノに変身(ここで序曲が終わる)。プロジェクターによるゲーム画面の中で大蛇を怖がる歌を歌い、ここから通常のオペラ通り(!)三人の侍女がタミーノを救う。
覚えているようで、結構たくさんのことを忘れていた。三人の息子たちは三人の童子となり、現実世界では父親であるタミーノを導く。タミーノがひとめ絵姿を見て愛し、救出する夜の女王の娘パミーナは、家出をしていった妻だ。タミーノ市川浩平さん、パミーナ盛田麻央さんがはじけた演技でみずみずしい歌唱を聴かせた。盛田さんが主役級の役をやられるのを初めて聴くが、度胸も華もあって、姿も可愛い素敵なパミーナだった。大きなバスト(作りもの)をむき出しにした三人の侍女(角南有紀さん、宮澤綾子さん、岡村彬子さん)も、溌剌としたよく響く声で舞台を活気づかせる、3人ともオレンジやピンクやパープルの大きなウィッグをつけ、ゲームのキャラクターのような姿をしていて、華やかな魔女といった雰囲気だ。
パパゲーノ(近藤圭さん)は幸福のピエロのような衣裳で、たくさんの演技をするが、今回の上演で新たに発見したのは、『魔笛』におけるパパゲーノの重要さだった。
2015年から6年経って、世界は本当に変わった。パパゲーノの歌う歌詞、語る台詞のすべてが「本当に正しい」と思えた。この鳥刺しパパゲーノは判で押したように「すごいものなんかになりたくない! 普通でいい!」と主張し、サディストのエリートたちを困らせるのだ。
『魔笛』のハイライトといえば、ソプラノが超絶技巧のハイトーンで歌う「夜の女王」のアリアだが、亞門版『魔笛』での夜の女王は異形のモンスターで、巨大なバストをむき出しにし(威嚇的な母性の表現か)、電気ショックで逆立ったようなパンクヘアで舞台に現れる。この役を歌った髙橋維さんは、本来なら娘のパミーナを歌いそうな可憐な女性だが、初演でも同じ衣装で夜の女王を歌い、迫力の演技で客席を圧倒した。髙橋さんは一種の天才で、誰よりも抵抗なく虚構の世界へすっと入っていくタイプで、ヘンデルの『ジューリオ・チェーザレ』でクレオパトラ役を演じたときから、何があっても動じない大物ぶりを発揮していた。誰もが舞台では変身するが、高橋さんの鮮やかな変貌ぶりはちょっとすごい。
それにしても、若い女性が巨大なバストのついたコスチュームを着て舞台で歌うというのは、結構傷つくことなのではないだろうか。亞門さんはそれも計算済みで、歌手にやらせているのか。髙橋さんの「夜の女王のアリア」は、危なっかしいところがひとつもなく、演劇的な意図がはっきりとした素晴らしい歌だった。この女王は激しいけれど、もともとは優しい女性だったのだ。夫の死後、さまざまなものを奪われ。不安になり、怒りと焦燥に焼き尽くされて今のような姿になった…そんなストーリーが全部浮かんでくるアリアで、誰もがアスリート的に「挑む」歌が、ここではそうは聞こえなかった。
モーツァルトの『魔笛』は台詞芝居つきのオペラ(ジングシュピール)なので、歌手たちは独語で演技をする。亞門演出の前は実相寺昭雄さんの演出で(『ウルトラマン』の怪獣がゾロゾロ出て来るというユニークなもの)芝居部分は日本語だった。2015年の新演出からドイツ語の芝居になったのは、リンツ州立劇場との共作であり、時代の肌感覚としても日本の歌手がドイツ語の台詞で演じるのが自然になってきたからだろう。台詞にはスピードがあり、どの歌手も頑張っていたと思う。
三人の童子は、ドイツ/オーストリアではウィーン少年合唱団やテルツ少年合唱団の選抜メンバーがこの歌を歌うことが多い。尾島怜さん、九木元秀至さん、寺島昇さんの3人は、綺麗な声ですべてのドイツ語の歌を歌った。どれだけ練習して、あれだけの歌を歌えるようになったのだろう。ウィーン少年合唱団どころではなく、すごい。こんな素晴らしいことを成しえたのだから、彼らの未来は明るいだろう。

パミーナが囚われた神殿の教祖であるザラストロは、亞門演出では脳内皮質丸出しのエイリアンとして描かれる。左右にぴったりついている二人の重臣も脳みそ人間で、頭脳だけが発達したおかしな存在に見える。そのことで、ザラストロの歌がすべて狂信的な教義の歌に聴こえるのは痛快だった。ザラストロを徳の高い人と解釈する演出も多いから、この大胆な転回は素晴らしい。オペラの構図をひっくり返す。どんな悪い母親でも、帰りたがっている娘と無理やり引き離すのは人道的ではないし、ザラストロがタミーノに課す「エリートの通過儀礼」も、よくよく考えると何やらきな臭い。モーツァルトは最初から、ザラストロを妖しい存在として捉えていたはずだ。そうでなければ、パパゲーノがあんなに生き生きとした「女とうまい酒と食べ物だけあれば満足!」という歌を歌うわけがないのだ(そのせいで、モーツァルトは早死にさせられたという説もある)。
ザラストロの神殿にいるゴリラたちのことも、すっかり忘れていた。エリート養成所であるはずの城の中に、なぜか5頭のゴリラがいる。縦横に動き回るゴリラのユーモラスな動きもオペラに含蓄をもたらしていた(中に人が入っている)。裏切り者の侍従モノスタトスも、やっていることは獣と同じようなことで、ザラストロの目を盗んでパミーナを襲おうとする。冒頭で、パンツ一枚になる「未遂」のシーンがあり、ひやりとした。同じ神殿にいる博士たちも、一皮むけばこういう存在ということなのだろうか。重そうな頭部を抱えてザラストロの低音を歌うバスの斉木健詞さんが、黒光りするようないい声を聴かせた。
2022年の世界は、ザラストロのものでも、試練を克服したタミーノのものでもなく、パパゲーノのものだ。タミーノは官僚世界に入り、ザラストロに従い、エリート社会で忖度しながらせせこましく生きていくしかない、落ちこぼれのパパゲーノには、自由もあるしなんでもある。ザラストロ的世界とは、バッハ会長や菅総理、河野大臣がいる世界で、たくさんのモノスタトスとゴリラがいる。そんな城の「メンバー」になったからといって、何だというのだ。こんな感想は亞門演出とは関係ないかも知れないが、「未来を握っているのはパパゲ―ノなのだ」と強く思った。
ギエドレ・シュレキーテの指揮は読響から室内楽的な美しい響きを引き出し、きびきびとしていて良かったが、ときどき歌手たちの呼吸が苦しそうに聴こえたのは、譜面には書かれていないコンマ何秒かの歌手への気づかいが、まだ身についていないからかも知れない。ピットはシュレキーテがいることで華やいだが、当初キャスティングされていたリオネル・ブランギエならどう振ったかな、と想像してしまった。ブランギエの振るモーツァルト・オペラも将来聴いてみたい。
ゲームの次元から現実の次元にタミーノ=父親が帰還し、弁者のおじいちゃん、三人の童子の息子たち、パミーナの妻と再会するラストシーンは、オペラのイシスとオシリスの賛歌の最後をうまく使ったもので、ストップウォッチで測ったわけではないが、だいたい1分か2分くらいのことだったと思う。演出家の「匠の技」を感じずにはいられない見事なラストで、やっぱり前回もこのシーンでは泣けたことを思い出した。歌手たちのドイツ語もどんどんうまくなり、オペラが語りかけて来るものもいよいよ大きかった。7月の『ファルスタッフ』はコロナの影響で一日公演が減ってしまったが、『魔笛』は全4公演が無事行われたのも、喜ばしいことだった。